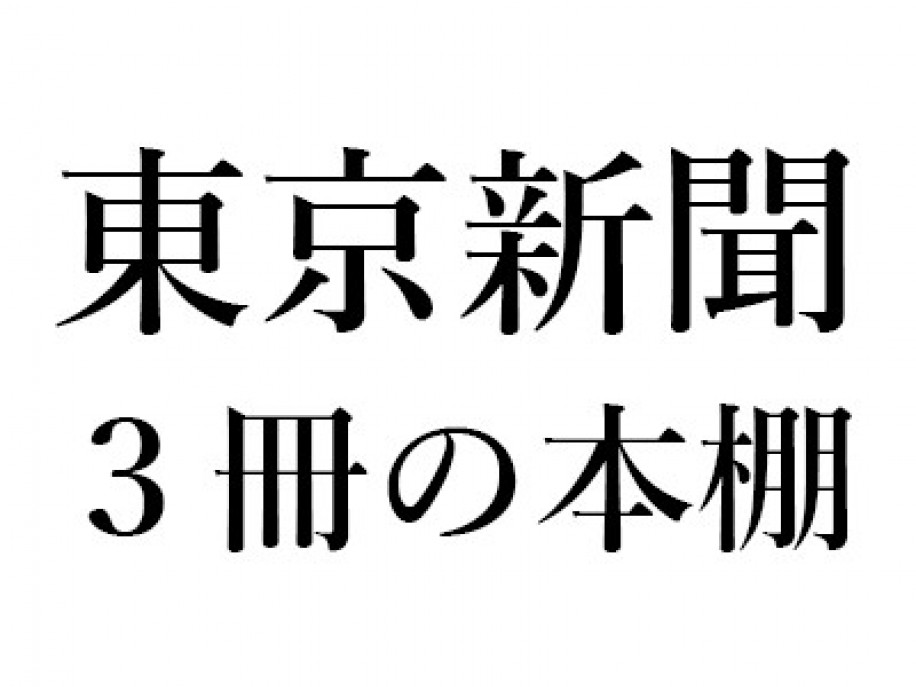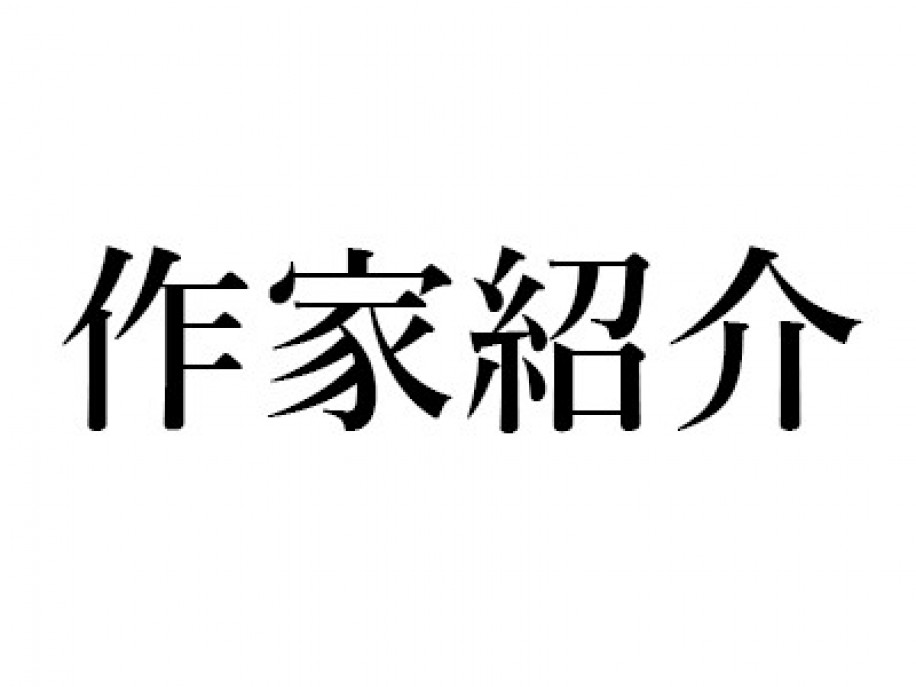書評
『ハルキ・ムラカミと言葉の音楽』(新潮社)
書名のハルキ・ムラカミについては、もはや説明はいらないだろう。著者のアイデアか、訳者や編集者の思いつきかは知らないが、この人名表記は村上春樹がいまや国境を越え、世界中で読まれていることを示唆している。
濃密な内容のわりには読みやすく、村上春樹論にふさわしい文章だ。作家の生い立ち、文学との出会い、多感な青春期の出来事、小説を書き始めるきっかけなどの伝記的な事実から、ポピュラー音楽、アメリカ文学との関係、作品誕生にまつわるエピソード、海外での読まれ方にいたるまで、幅広く語られている。村上春樹について、これほど多角的に検討される例は珍しい。
冒頭から村上春樹のファンと自称する著者は、作家との個人的な親密関係をまったく隠そうとしない。研究対象とのあいだに取るべき距離を忘れたのではない。読者との交信を大切にする作家にとって、日常的な感覚を持ち続けるのは、読み手の周波数をキャッチするのに不可欠なことだ。村上春樹が社交的な匿名性にこだわっているのもそのためであろう。事実、この作家は文壇からもメディアからも遠く離れている。著者は作家との親しい関係を生かし、作品の解読においてそうした情報を最大限に活用した、おかげで、村上春樹のまぶしい後光に目が眩みがちな読者は、創作現場の緊張や村上春樹劇場の楽屋をのぞき見ることができた。
作家の成長を一本の軸に、処女作の『風の歌を聴け』(講談社)から、最新の『東京奇譚集』(新潮社)にいたるまで、一作も洩らさずに徹底的に吟味された。小説のみならず、エッセーや講演内容まで目を配り、HPでの読者とのやり取りでさえ見落とさなかった。完全無欠な作家論を目指すためだが、村上春樹の世界を愛したファンとしての、個人的な情熱も後押しをしたのであろう。こうして、物語の内容も主題も構成も違う作品群から、作家独特の美学体系が魔法のように抽出された。著者は名付けて「言葉の音楽」という。
作品批評としてはまぎれもなく一級品だ、読みながらE・アウエルバッハの名著(『ミメーシス』)が思い出された。テクストに即した読みは文字どおり微に入り細を穿っている。作家が何を語ろうとし、読者がなぜ感動したかが、わかりやすく解き明かされた。
長年、夏目漱石を研究してきた著者が村上春樹の世界と出会ったのはまったくの偶然だ。出版社から翻訳の可否についての問い合わせがあり、それに答えるためにこの流行作家を読み始めた。それ以来、村上春樹の魅力にとりつかれた。だが、日本近代文学の厚い素養は、この現代作家の研究においても無駄ではなかった。
レイモンド・カーヴァー、F・スコット・フィッツジェラルドをはじめアメリカ作家との関係をたどっていくと、村上春樹の世界は彼らとの想像力の往来のなかで生まれたことがわかった。だが、著者の探究はここにとどまらない。村上春樹が近代文学という大木とどのような関係にあるかも鋭く見抜いた。このもっとも「非日本的な」作家は、私小説の自伝的な約束事をうまく利用して、まったくの虚構を作り上げた。村上春樹が起こした文体の革命は、漱石以来の文学的な文脈の上に成り立つものだ。その批評眼の確かさに改めて驚かされた。
村上春樹がハルキ・ムラカミになったのも、ジェイ・ルービンのようなよき理解者がいたからであろう。
【この書評が収録されている書籍】
濃密な内容のわりには読みやすく、村上春樹論にふさわしい文章だ。作家の生い立ち、文学との出会い、多感な青春期の出来事、小説を書き始めるきっかけなどの伝記的な事実から、ポピュラー音楽、アメリカ文学との関係、作品誕生にまつわるエピソード、海外での読まれ方にいたるまで、幅広く語られている。村上春樹について、これほど多角的に検討される例は珍しい。
冒頭から村上春樹のファンと自称する著者は、作家との個人的な親密関係をまったく隠そうとしない。研究対象とのあいだに取るべき距離を忘れたのではない。読者との交信を大切にする作家にとって、日常的な感覚を持ち続けるのは、読み手の周波数をキャッチするのに不可欠なことだ。村上春樹が社交的な匿名性にこだわっているのもそのためであろう。事実、この作家は文壇からもメディアからも遠く離れている。著者は作家との親しい関係を生かし、作品の解読においてそうした情報を最大限に活用した、おかげで、村上春樹のまぶしい後光に目が眩みがちな読者は、創作現場の緊張や村上春樹劇場の楽屋をのぞき見ることができた。
作家の成長を一本の軸に、処女作の『風の歌を聴け』(講談社)から、最新の『東京奇譚集』(新潮社)にいたるまで、一作も洩らさずに徹底的に吟味された。小説のみならず、エッセーや講演内容まで目を配り、HPでの読者とのやり取りでさえ見落とさなかった。完全無欠な作家論を目指すためだが、村上春樹の世界を愛したファンとしての、個人的な情熱も後押しをしたのであろう。こうして、物語の内容も主題も構成も違う作品群から、作家独特の美学体系が魔法のように抽出された。著者は名付けて「言葉の音楽」という。
作品批評としてはまぎれもなく一級品だ、読みながらE・アウエルバッハの名著(『ミメーシス』)が思い出された。テクストに即した読みは文字どおり微に入り細を穿っている。作家が何を語ろうとし、読者がなぜ感動したかが、わかりやすく解き明かされた。
長年、夏目漱石を研究してきた著者が村上春樹の世界と出会ったのはまったくの偶然だ。出版社から翻訳の可否についての問い合わせがあり、それに答えるためにこの流行作家を読み始めた。それ以来、村上春樹の魅力にとりつかれた。だが、日本近代文学の厚い素養は、この現代作家の研究においても無駄ではなかった。
レイモンド・カーヴァー、F・スコット・フィッツジェラルドをはじめアメリカ作家との関係をたどっていくと、村上春樹の世界は彼らとの想像力の往来のなかで生まれたことがわかった。だが、著者の探究はここにとどまらない。村上春樹が近代文学という大木とどのような関係にあるかも鋭く見抜いた。このもっとも「非日本的な」作家は、私小説の自伝的な約束事をうまく利用して、まったくの虚構を作り上げた。村上春樹が起こした文体の革命は、漱石以来の文学的な文脈の上に成り立つものだ。その批評眼の確かさに改めて驚かされた。
村上春樹がハルキ・ムラカミになったのも、ジェイ・ルービンのようなよき理解者がいたからであろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする