前書き
『サン=テグジュペリの世界 〈永遠の子ども〉の生涯と思想』(講談社)
子ども向けの小さな物語が、どうして二十世紀最高の書物になったのか
はじめに
サン=テグジュペリは、なによりもまず、『星の王子さま』の作者です。『星の王子さま』は彼の最高傑作であるばかりか、二十世紀最高の書物のひとつでもあります。じっさい、『星の王子さま』は、マルクスの『資本論』などと並ぶ二十世紀の大ベストセラーであり、世界中の言語に訳されています。この子ども向けの小さな物語が、どうしてそれほど偉大な書物になったのかと不思議にも思うひとも多いのではないでしょうか。そしていまもなお、子どもからおとなまで、世界中の多くの人びとが『星の王子さま』を読み続け、また愛し続けていますが、その魅力の秘密はどこにあるのかという疑問も湧いてきます。
もっと具体的な疑問もあると思います。たとえば「たいせつなことは、目に見えない」という作品中何度も出てくる言葉について、その〈目に見えないたいせつなこと〉というのはいったいなんだろうかという疑問も、『星の王子さま』を読んだ読者の心にいつまでも残るだろうと思います。あるいは、これもしきりに出てくる「飼いならす」という言葉はなにを意味しているのか、と自問するひともいるでしょう。
そうした問題とも深く関連しますが、やはり作品中、おとなにはほんとうのこと、かんじんなことが分からない、おとなは生きるとはどういうことか分かっていない、おとなはおかしい、おとなは変だ、などという言葉がしきりに出てきます。逆に、「子どもたちだけが、自分はなにを求めているのか、分かっている」とも言われています。つまり、子どもだけがほんとうのこと、かんじんなこと、生きることの真実を知っているということです。それでは、ほんとうにたいせつなこと、人間の真実というものを子どもだけが知っている、おとなはそれを知らない、あるいはおとなになることによってそれを忘れてしまう、というのはいったいどういうことなのか、またなぜなのか。そうした疑問も、『星の王子さま』を正しく理解するうえで大きな..になると思います。
本書は、以上のような疑問をいつも念頭に置きながら、サン=テグジュペリの生涯をできるだけ丹念にたどり、またその時々に書かれた彼の著作を綿密に読み解いていくことによって、そうした謎がおのずから明らかになっていくことを意図するものです。
ところで、子どもだけが、ほんとうにたいせつなこと、生きることの真実を知っているということは、言い換えるなら、子どもは真実の世界に生きており、子どもこそが真実の人間である、ということにほかなりません。じっさい、子ども時代に生きた世界こそが真実の世界であり、子ども時代の自分こそがほんとうの自分であったという思いをサン=テグジュペリは生涯にわたって持ち続けました(「子どものとき以来、ぼくはほんとうに生きていると実感したことがないような気がします」I-780)。言うまでもなく、『星の王子さま』は、彼自身の子ども時代という源泉から生まれた作品です。
しかし、人間はだれも、おとなになることによって、子ども時代から追放されてしまいます(「自分の子ども時代から追放されてしまうなんて、おかしな追放です」I-783)。そして、たいていのおとなたちは、子ども時代のことを、そしてかつて子どもであった自分のことを忘れてしまいます(「おとなだって、はじめはみんな子どもでした。(でも、そのことを忘れずにいるおとなは、ほとんどいません)」)。
しかしサン=テグジュペリは、自分の子ども時代のこと、そしてかつて子どもであった自分のことを忘れることができませんでした。そのため、彼はおとなになりきることができなかった人間だったと言ってよいかもしれません。いずれにせよ、子ども時代の世界こそ真実の世界であり、子ども時代にそうであった自分こそほんとうの自分であると思い続ける人間にとって、おとなの世界を生きることが、またおとなとして生きることが、どれほど生きづらいことであったかは容易に想像できます。彼は、おとなの世界にほかならないこの現実社会を、つねに居心地の悪さ、窮屈さを感じながら、いわばよそ者として、不器用に生きねばなりませんでした。
失敗と挫折、混乱や波瀾に満ちたサン=テグジュペリの生涯は、どこかドタバタ喜劇めいており、それ自体として見ても面白いし、興味深いのですが、彼自身はこうした人生を懸命に生きることを通して、おとなの世界である現実社会、さらにはまさしくおとなの世界として成立し発展してきた近代および現代という時代にたいする批判意識を研ぎ澄ますと同時に、みずからの内面空間そのものとしての子ども時代の世界のヴィジョンを明確化していきます。言うまでもなく、現実社会、そして近代および現代という時代にたいする批判意識と子ども時代の世界のヴィジョンは表裏一体の関係にあります。
第二次世界大戦という世界の破局のなかで、サン=テグジュペリは、文明の復興、そして人間の復活のためには、子ども時代の世界のヴィジョンをよみがえらせるほかに道はないと思うようになりました。『星の王子さま』もまた、そんな思いから生まれた作品にほかなりません。
【関連オンラインイベント情報】2022/04/30 (土) 13:00 - 14:30 武藤 剛史 ×鹿島 茂、武藤 剛史 『サン=テグジュペリの世界〈永遠の子ども〉の生涯と思想』(講談社)を読む
書評アーカイブサイト・ALL REVIEWSのファンクラブ「ALL REVIEWS 友の会」の特典対談番組「月刊ALL REVIEWS」、第40回のゲストは仏文学者の武藤 剛史 さん。メインパーソナリティーは鹿島茂さん。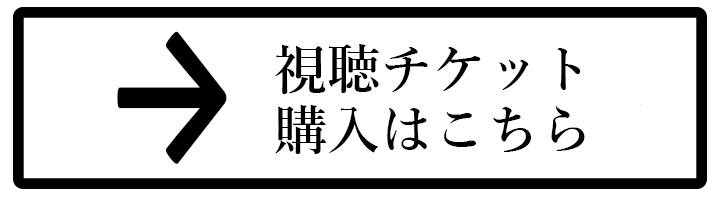 https://peatix.com/event/3238735/view
https://peatix.com/event/3238735/viewALL REVIEWSをフォローする





































