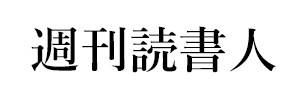書評
『パレスチナ』(いそっぷ社)
手塚治虫の『アドルフに告ぐ』は、戦前の神戸にあったドイツ人社会を舞台に、手塚が幼少時から親しんできたコスモポリタニスムを十全に発揮した長編漫画であった。ヒトラーが実はユダヤ系であるという秘密を偶然に知ってしまったユダヤ人の少年と、彼の親友で、ドイツに戻ってナチズムに熱烈帰依してしまうドイツ人の少年。神戸とベルリンに引き裂かれた彼らの奇妙な友情を、この漫画は第2次大戦を背景に語っている。文字通り波乱万丈の物語だが、エピローグだけは読み終わって、これはちょっと困ったなという印象をもった。そこではイスラエル国家が樹立された後、今では壮年となった二人の主人公が中東戦争のおりに、イスラエルとアラブの両側に属し宿命の死闘を演じるのである。かつてナチスに加担した少年は、第三帝国崩壊後も反ユダヤ主義に凝り固まり、イスラエルに対し憎悪の応酬に出る。
どうして手塚はこうした受難のユダヤ人=イスラエル、ナチズム=パレスチナ解放勢力、といった単純にして誤った図式を採用してしまったのだろうか。わたしは長らくこれを疑問に思ってきたが、最近になってようやくその解決の手がかりを認めた。1954年にイスラエルとハリウッドが共同で制作した『高原24応答せず』(ソロルド・ディケンスン監督)のなかに、ナチスSSの残党がエジプト軍に加わり、第1次中東戦争のさいにイスラエルの独立を阻止せんと攻撃を仕掛けてくるという挿話を発見した。これはイスラエルに反対する者はすべてナチスの類であるという悪質なプロパガンダである。洋画ファンであった手塚は、当時イスラエル映画として唯一本邦で公開されたこの戦争映画をおそらく観ており、そのときの記憶からかのエピローグの想を得たのではないだろうか。
日本の漫画がパレスチナをめぐって抱え込んでしまったこうした不幸な偏見をなんとか覆し、その負債を解決することはできないだろうか。だが『忍者武芸帳』の時代の白土三平ならいざ知らず、苛酷な商業主義のなかで自転車操業を強いられている現在の日本の漫画家に、はたしてそれが可能だろうか。わたしがジョー・サッコの『パレスチナ』に出会ったのは、そう考えていたときであった。
サッコは大学でジャーナリズムを学んだアメリカの漫画家である。1991年から翌年にかけてイスラエル占領下にあるヨルダン川西岸とガザをくまなく歩き回り、インティファーダに沸き返る民衆に混じって数多くのことを見聞した。帰国後彼は見聞をもとにしてこの作品を描きあげ、「コミックス・ジャーナリズム」という独自のジャンルの創始者となった。1996年に出版されたこの漫画は、すでに韓国語までを含めて16の言語に翻訳されている。
『パレスチナ』のなかで、語り手はカイロからバスでパレスチナに入る。いくたびもイスラエル軍による検問を抜け、乗り合いバスを乗りかえ、市場の雑踏に圧倒され、さまざまな人々と対話する。息子を殺された父親。長らく不当逮捕され、獄中にあった青年。こちら側をユダヤ人だと思い込んで、石を投げるポーズを示し、小銭を強請る子供たち。どこまでも甘いコーヒーを御代りしながら、屈辱と恐怖の日々を語る男たち。土砂降りのなかで語り手はインティファーダで殺された最初の子供の墓を訪れ、若者たちの歌と踊りの宴に参加する。彼は状況を説明され、驚き、悲しみ、怒ると同時に、そこに居合わせた人々からさまざまな質問を受ける。あなたの国にも兵隊はいるのか。兵隊は人を撃ったりするか。いつ国に帰るのか。最後に彼はイスラエル領内のテルアヴィヴに至り、ユダヤ人たちと対話をする。一度勝ち取った士地を譲れないと、彼らは頑強に主張し、語り手が占領地での悲惨を語りだすと、怒って声を高くする。ここに描かれていることは、多少形こそ違え、わたしが以前パレスチナ・イスラエルに滞在していたときに幾たびも体験したことでもあり、サッコという漫画家の目の鋭さに共感するところが大きい。
サッコはけっして占領下にあるパレスチナ人を、理想化も聖人化もしていない。彼らは、そう日本でいうなれば青木雄二の『ナニワ金融道』の登場人物のように、欲望をもち、自分の権利を主張し、困難な状況のなかでなんとか活路を見出そうと四苦八苦している。作者はけっして彼らを前に、客観的にして中立的な観察者として振舞っているわけではない。彼は観察を開始した瞬間から、「客観」や「中立」といったていのいい観念が不可能となってしまう状況に巻き込まれてしまい、みずからの拠って立つ位置をつねに再検討しつつ、悩み、怒り、思考を続けている。『パレスチナ』は漫画を通してなされた記録の書であると同時に、報道をめぐるモラルの思索の書でもあるのだ。
実をいうと、この漫画はわたしがアメリカ在住の友人と組んで、みずから日本語に翻訳紹介を考えていたものであった、それを諦めたのは、小野耕世が訳筆をとっておられると聞いたからである。氏が海外のコミックスに深い造詣をもっていることはつとに知られているが、ここでより重要なことは、彼がスピーゲルマンの『マウス』の翻訳者でもあるという事実だろう。アウシュヴィッツに送られたユダヤ人の悲劇を鼠に託して語ったこの漫画には、すでに漫画史の古典ともいうべき評価がなされている。その訳者が次に『パレスチナ』の翻訳に向かったことの背後には、今日のパレスチナこそが過去のアウシュヴィッツの反復であるという歴史認識が横たわっている。おそらく氏もまた筆者同様、日本漫画においてこうしたコミックス・ジャーナリズムがいつ興隆することになるのだろうかと、強い期待を抱いておられるのではないだろうか。
『パレスチナ』の序文を執筆しているのは、白血病でもはや幾許かの生命もなかったエドワード・W・サイードである。どうやら彼は息子がたまたま買ってきたこの漫画を手にとって、衝撃を受けたようである。サッコは漫画のなかでも告白しているが、サイードの読者でもあった。そのサイードが作品の全体が完成したのを待って、強い興奮のもとにこの「たぐいまれな描写者」への絶賛の言葉を書き記している。そのエッセイの随所に、彼が少年時代に親しんできた漫画への追憶が顔を覗かせていることは、実に興味深い。ところでサッコの漫画には、相棒として日本人写真家のサブローなる人物か登場し、作者と思しき語り手と対話をすることで、観察者というイデオロギー的な位置を相対化する役割を担っている。これは誰か実在のモデルがいたのだろうか。気になるところである。
【増補版】
【この書評が収録されている書籍】
どうして手塚はこうした受難のユダヤ人=イスラエル、ナチズム=パレスチナ解放勢力、といった単純にして誤った図式を採用してしまったのだろうか。わたしは長らくこれを疑問に思ってきたが、最近になってようやくその解決の手がかりを認めた。1954年にイスラエルとハリウッドが共同で制作した『高原24応答せず』(ソロルド・ディケンスン監督)のなかに、ナチスSSの残党がエジプト軍に加わり、第1次中東戦争のさいにイスラエルの独立を阻止せんと攻撃を仕掛けてくるという挿話を発見した。これはイスラエルに反対する者はすべてナチスの類であるという悪質なプロパガンダである。洋画ファンであった手塚は、当時イスラエル映画として唯一本邦で公開されたこの戦争映画をおそらく観ており、そのときの記憶からかのエピローグの想を得たのではないだろうか。
日本の漫画がパレスチナをめぐって抱え込んでしまったこうした不幸な偏見をなんとか覆し、その負債を解決することはできないだろうか。だが『忍者武芸帳』の時代の白土三平ならいざ知らず、苛酷な商業主義のなかで自転車操業を強いられている現在の日本の漫画家に、はたしてそれが可能だろうか。わたしがジョー・サッコの『パレスチナ』に出会ったのは、そう考えていたときであった。
サッコは大学でジャーナリズムを学んだアメリカの漫画家である。1991年から翌年にかけてイスラエル占領下にあるヨルダン川西岸とガザをくまなく歩き回り、インティファーダに沸き返る民衆に混じって数多くのことを見聞した。帰国後彼は見聞をもとにしてこの作品を描きあげ、「コミックス・ジャーナリズム」という独自のジャンルの創始者となった。1996年に出版されたこの漫画は、すでに韓国語までを含めて16の言語に翻訳されている。
『パレスチナ』のなかで、語り手はカイロからバスでパレスチナに入る。いくたびもイスラエル軍による検問を抜け、乗り合いバスを乗りかえ、市場の雑踏に圧倒され、さまざまな人々と対話する。息子を殺された父親。長らく不当逮捕され、獄中にあった青年。こちら側をユダヤ人だと思い込んで、石を投げるポーズを示し、小銭を強請る子供たち。どこまでも甘いコーヒーを御代りしながら、屈辱と恐怖の日々を語る男たち。土砂降りのなかで語り手はインティファーダで殺された最初の子供の墓を訪れ、若者たちの歌と踊りの宴に参加する。彼は状況を説明され、驚き、悲しみ、怒ると同時に、そこに居合わせた人々からさまざまな質問を受ける。あなたの国にも兵隊はいるのか。兵隊は人を撃ったりするか。いつ国に帰るのか。最後に彼はイスラエル領内のテルアヴィヴに至り、ユダヤ人たちと対話をする。一度勝ち取った士地を譲れないと、彼らは頑強に主張し、語り手が占領地での悲惨を語りだすと、怒って声を高くする。ここに描かれていることは、多少形こそ違え、わたしが以前パレスチナ・イスラエルに滞在していたときに幾たびも体験したことでもあり、サッコという漫画家の目の鋭さに共感するところが大きい。
サッコはけっして占領下にあるパレスチナ人を、理想化も聖人化もしていない。彼らは、そう日本でいうなれば青木雄二の『ナニワ金融道』の登場人物のように、欲望をもち、自分の権利を主張し、困難な状況のなかでなんとか活路を見出そうと四苦八苦している。作者はけっして彼らを前に、客観的にして中立的な観察者として振舞っているわけではない。彼は観察を開始した瞬間から、「客観」や「中立」といったていのいい観念が不可能となってしまう状況に巻き込まれてしまい、みずからの拠って立つ位置をつねに再検討しつつ、悩み、怒り、思考を続けている。『パレスチナ』は漫画を通してなされた記録の書であると同時に、報道をめぐるモラルの思索の書でもあるのだ。
実をいうと、この漫画はわたしがアメリカ在住の友人と組んで、みずから日本語に翻訳紹介を考えていたものであった、それを諦めたのは、小野耕世が訳筆をとっておられると聞いたからである。氏が海外のコミックスに深い造詣をもっていることはつとに知られているが、ここでより重要なことは、彼がスピーゲルマンの『マウス』の翻訳者でもあるという事実だろう。アウシュヴィッツに送られたユダヤ人の悲劇を鼠に託して語ったこの漫画には、すでに漫画史の古典ともいうべき評価がなされている。その訳者が次に『パレスチナ』の翻訳に向かったことの背後には、今日のパレスチナこそが過去のアウシュヴィッツの反復であるという歴史認識が横たわっている。おそらく氏もまた筆者同様、日本漫画においてこうしたコミックス・ジャーナリズムがいつ興隆することになるのだろうかと、強い期待を抱いておられるのではないだろうか。
『パレスチナ』の序文を執筆しているのは、白血病でもはや幾許かの生命もなかったエドワード・W・サイードである。どうやら彼は息子がたまたま買ってきたこの漫画を手にとって、衝撃を受けたようである。サッコは漫画のなかでも告白しているが、サイードの読者でもあった。そのサイードが作品の全体が完成したのを待って、強い興奮のもとにこの「たぐいまれな描写者」への絶賛の言葉を書き記している。そのエッセイの随所に、彼が少年時代に親しんできた漫画への追憶が顔を覗かせていることは、実に興味深い。ところでサッコの漫画には、相棒として日本人写真家のサブローなる人物か登場し、作者と思しき語り手と対話をすることで、観察者というイデオロギー的な位置を相対化する役割を担っている。これは誰か実在のモデルがいたのだろうか。気になるところである。
【増補版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする