書評
『ガリ版文化を歩く―謄写版の百年』(新宿書房)
豊かなガリ版の世界
小学生のころ、学級通信係でガリ版新聞を作っていた。家にヤスリ板と鉄筆と、ニスで黄色く塗った手動の刷り機を置き、休みの日もせっせと仕事をし、広げて乾かす。そんな経験をもった人には『ガリ版文化を歩く』(新宿書房)は懐かしい一冊である。志村章子さんの、たんねんな資料発掘と現場探訪、つまりよく働く足で書かれたこの本は、ガリ版と同じような手仕事のあとがある。読んでいる私の周りに、あのロウ原紙のにおいと、ジージーという鉄筆の音が鳴り響く。
ガリ版は小さなタンポポ
美しい花が咲く中では
だれも見向きもしない
でも人知れず道のすみっこで
小さな花を咲かすだろう 安藤信義
このメディアづくりの機械が日本に生まれたのは明治二十七年、発明者は堀井新治郎父子、滋賀の人である。簡単、速い、見てきれい、考えを人々に伝える道具としてさまざまに活用されてきて百年。コピーやワープロの普及で消えゆく技術に見えるが(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)、じつはどっこい生きている。
著者はテレビの台本をいまもってガリ版で作っている荒川区の会社、ゆりがおか児童館のガリ版機関紙から話をはじめる。亡びゆく技術を惜しむという後ろ向きでない明るさがうれしい。
山形の冬澤未都彦さんの究極のガリ版印刷。その名をガリグラフィという。一時間半で三十字しか切れない。一日八時間ヤスリ板に向かっても半ページ。しかしその大判の出版物「イーハトーヴ密造会社」や「山月記」を私も持っているが、りん、とした息をのむ美しさ、気品である(本書の表紙や扉にも冬澤さんの作品が用いられている)。
「新しいものは過去の中にあるんだと思いましたね」という佐藤勝英さんは、二十代の若さで謄写印刷に向かった。松本の赤羽藤一郎氏の技術を学び、いまは熊本で「黒船工房」を開く。ガリ版はか細いながら、誇らかに継承されている。
さかのぼれば宮沢賢治。花巻の農学校や羅須地人協会の活動にガリ版を活躍させたが、それは短い東京時代のたまものだった。賢治は本郷の炭団(たどん)坂の下の四畳の下宿に住み、本郷通りにあった文信堂という謄写プリント店の筆耕、つまりガリ切りをした。これも賢治の下積み時代と文学史上では片づけられるが、どうして、彼は言葉を伝える技術をここで習得したのではなかったか。
そんな楽しく豊かなガリ版の世界を著者は次々と開いてくれる。たとえば二・二六事件の戒厳司令部による文書「下士官ニ告グ」もガリ版で、銀座伊東屋から召し上げた機械で刷られたこと。生活綴り方運動の生んだガリ版文集。土佐原紙という手すきのロウ原紙があったこと。女性たちのさまざまなガリ版ミニメディア。タイの電気も来ない農村でもいま、“トウシャバン”が活躍していること。アメリカ軍占領下の沖縄久米島でガリ版印刷の切手が作られていたこと……。
一人が一人と向き合って話すのがコミュニケーションの基本。しかし、謄写版は一人が十人に、五十人に思いを伝える道具である。そこでアッという世界が広がる。しかし、それが五千人、一万人とならないところが、また謄写版の健全さである。
もし、東京で大震災が起きたら、と私は考える。電気に頼るメディアは使えないだろう。地域雑誌を発行している私は、どこに井戸があるか、路地の年寄りは無事か、そんなことを謄写版で刷るのだろうか。それとも手書きで電柱に貼って歩くのかなあ、と。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
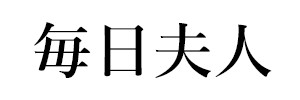
毎日夫人(終刊) 1993年~1996年
ALL REVIEWSをフォローする





































