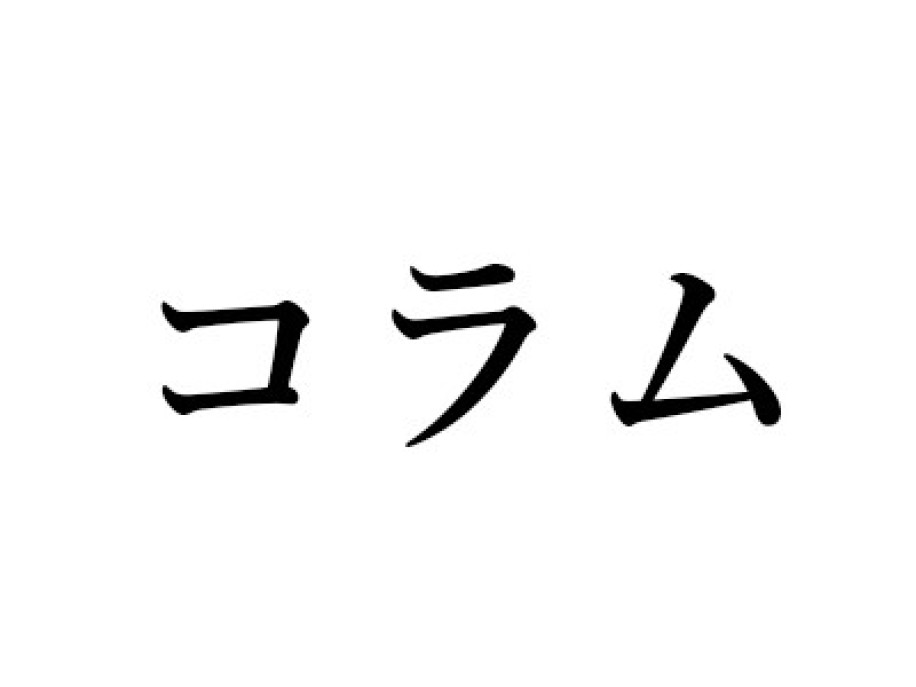書評
『戦国時代の足利将軍』(吉川弘文館)
国際政治学の成果を援用
去る5月、ベルギー・オランダを訪問した。安達峰一郎関係資料の情報を得るためだった。その旅は、第1次世界大戦後に常設国際司法裁判所の所長として、国際法による国家間の紛争解決に努め、オランダで国葬された安達の足跡をたどるものであったが、国際法が根付いていない当時の安達らの苦労が偲(しの)ばれた。本書の書評を安達の話で始めたのは、著者によれば戦国時代の足利将軍は、あたかも国連のような役割を果たし、現在の国家のような戦国大名たちのゆるい連合の上に立って、大名間の問題解決・調停を担うなど、重要な役割を果たしていたというからだ。
著者の山田康弘氏は、聖学院大学などで非常勤講師を務める戦国大名と幕府関係史の新進気鋭の専門家である。従来、戦国時代の足利将軍に関しては、群雄割拠の時代として位置づけられてきたこともあって、さほど重要視されず、傀儡(かいらい)にすぎないとされてきた。しかし、室町幕府成立期以来、足利将軍は一貫して、自己の直属軍などの基盤は弱かったものの、諸大名のゆるい連合の上に、大名間の問題解決・調停などを担い、栄典を授与するなどの機能を果たしてきたという。
最後の室町将軍足利義昭は、織田信長の傀儡と考えられがちだが、独自に裁判権を行使し、諸大名に栄典を与えていた。信長と決裂し、1573(元亀4)年に京都を追われるが、毛利氏に担がれ、鞆(岡山県)を拠点に将軍としての役割を果たしていた。それゆえ、室町幕府の滅亡とは、義昭が信長に京都を追われた73年ではなく、豊臣秀吉に屈し、小大名となった87(天正15)年とする。
本書の最大の魅力は、国際政治学の成果を援用して、戦国大名を国家に、室町幕府が体現する天下を国連に対比しつつ、足利将軍の役割を活写している点であろう。近年は、北条氏時代の鎌倉将軍など、傀儡とされてきた将軍権力に光が当てられつつあるが、本書の視角は、鎌倉将軍を理解するうえでも示唆に富むように思える。
[書き手] 松尾 剛次(まつお けんじ・山形大人文学部教授)
ALL REVIEWSをフォローする