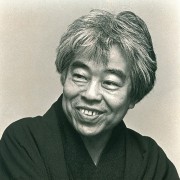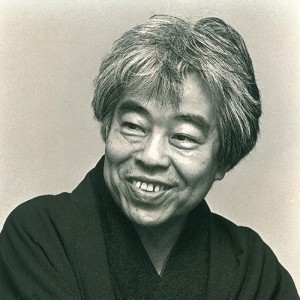書評
『ふぉん・しいほるとの娘』(新潮社)
吉村昭の長編歴史小説は、これまでに「冬の鷹」「北天の星」「漂流」などがあるが、この「ふぉん・しいほるとの娘」は、シーボルトの娘お稲の生涯を中心に、歴史の動きを幅ひろくもりこみ、時代の群像を描き出した労作である。
この作品の取材にあたって、吉村昭は長崎や宇和島を数回訪れ、図書館、古本屋、郷土史家などをたずねまわり、大型の本棚二つがいっぱいになるほどの参考文献をあつめたというが、その丹念な努力を反映して、文政六年七月にフォン・シーボルトが来日して以後、明治三十六年八月の楠本伊篤(お稲の後の名)の死去にいたる八十年間のさまざまなできごとや、彼女の波瀾に富んだ人生、さらにその周辺の人々の動きなどが綿密にうつされ、重厚な歴史ドラマを形成している。
シーボルトはドイツの格式ある医家の出身で、日本にたいするつよい関心からオランダの陸軍外科少佐として来日し、西洋医学の普及にあたり、多くの日本人から師として慕われたが、オランダ政府の命令で日本の国情を研究する任務をも帯びており、高橋作左衛門を通じて日本の地図を入手するという国禁を犯したために、強制送還される。
丸山の遊女其扇はシーボルトに愛され、お稲を生んだが、この事件によって生後二年半のお稲とともにシーボルトと別れ、本名のお滝にもどって、やがて俵屋時治郎に嫁し、お稲も時治郎を新しい父として成長した。しかしシーボルトの血をひく彼女は、つよく学問を好んだので、十四歳のときに伊予の卯之町で医者をしている父の弟子二宮敬作のもとに預けられた。
敬作はお稲に産科医となることをすすめ、彼女は女性として前人未踏の学問の分野へ歩み出すことになる。だがその後、さらに専門的な知識を得るために、岡山の石井宗謙のもとで学んでいるとき、宗謙に手ごめにされ、娘を生んだことは、一時は学問への情熱さえ失わせるほどの衝撃だった。しかし二宮敬作にはげまされ、ふたたび卯之町へ行って産科医としての腕をみがくのだ。やがて彼女は禁令がとけて来日した父と長崎で再会、以後、長崎と宇和島を往復し、維新後は東京へ出て女医としての評判を得るが、晩年は故郷へもどってしずかな余生を送る。
その間、時代の激動は彼女の周辺にもさまざまな波紋を描くが、多くの苦難を経て新しい女性の道を歩みながらも、彼女は日本の女としての意識をもちつづけた。
このドラマティックな素材を、作者は感情をおさえた筆致でたどっているが、それは歴史そのものがドラマであり、あくまでも史実をふまえて書きたいという意図によるものであろう。これまでの他の作品にみられるノン・フィクションの手法を生かしているわけだが、そのためお稲やシーボルトの像が、かえって明確に刻みこまれているのだ。
【下巻】
この作品の取材にあたって、吉村昭は長崎や宇和島を数回訪れ、図書館、古本屋、郷土史家などをたずねまわり、大型の本棚二つがいっぱいになるほどの参考文献をあつめたというが、その丹念な努力を反映して、文政六年七月にフォン・シーボルトが来日して以後、明治三十六年八月の楠本伊篤(お稲の後の名)の死去にいたる八十年間のさまざまなできごとや、彼女の波瀾に富んだ人生、さらにその周辺の人々の動きなどが綿密にうつされ、重厚な歴史ドラマを形成している。
シーボルトはドイツの格式ある医家の出身で、日本にたいするつよい関心からオランダの陸軍外科少佐として来日し、西洋医学の普及にあたり、多くの日本人から師として慕われたが、オランダ政府の命令で日本の国情を研究する任務をも帯びており、高橋作左衛門を通じて日本の地図を入手するという国禁を犯したために、強制送還される。
丸山の遊女其扇はシーボルトに愛され、お稲を生んだが、この事件によって生後二年半のお稲とともにシーボルトと別れ、本名のお滝にもどって、やがて俵屋時治郎に嫁し、お稲も時治郎を新しい父として成長した。しかしシーボルトの血をひく彼女は、つよく学問を好んだので、十四歳のときに伊予の卯之町で医者をしている父の弟子二宮敬作のもとに預けられた。
敬作はお稲に産科医となることをすすめ、彼女は女性として前人未踏の学問の分野へ歩み出すことになる。だがその後、さらに専門的な知識を得るために、岡山の石井宗謙のもとで学んでいるとき、宗謙に手ごめにされ、娘を生んだことは、一時は学問への情熱さえ失わせるほどの衝撃だった。しかし二宮敬作にはげまされ、ふたたび卯之町へ行って産科医としての腕をみがくのだ。やがて彼女は禁令がとけて来日した父と長崎で再会、以後、長崎と宇和島を往復し、維新後は東京へ出て女医としての評判を得るが、晩年は故郷へもどってしずかな余生を送る。
その間、時代の激動は彼女の周辺にもさまざまな波紋を描くが、多くの苦難を経て新しい女性の道を歩みながらも、彼女は日本の女としての意識をもちつづけた。
このドラマティックな素材を、作者は感情をおさえた筆致でたどっているが、それは歴史そのものがドラマであり、あくまでも史実をふまえて書きたいという意図によるものであろう。これまでの他の作品にみられるノン・フィクションの手法を生かしているわけだが、そのためお稲やシーボルトの像が、かえって明確に刻みこまれているのだ。
【下巻】
ALL REVIEWSをフォローする