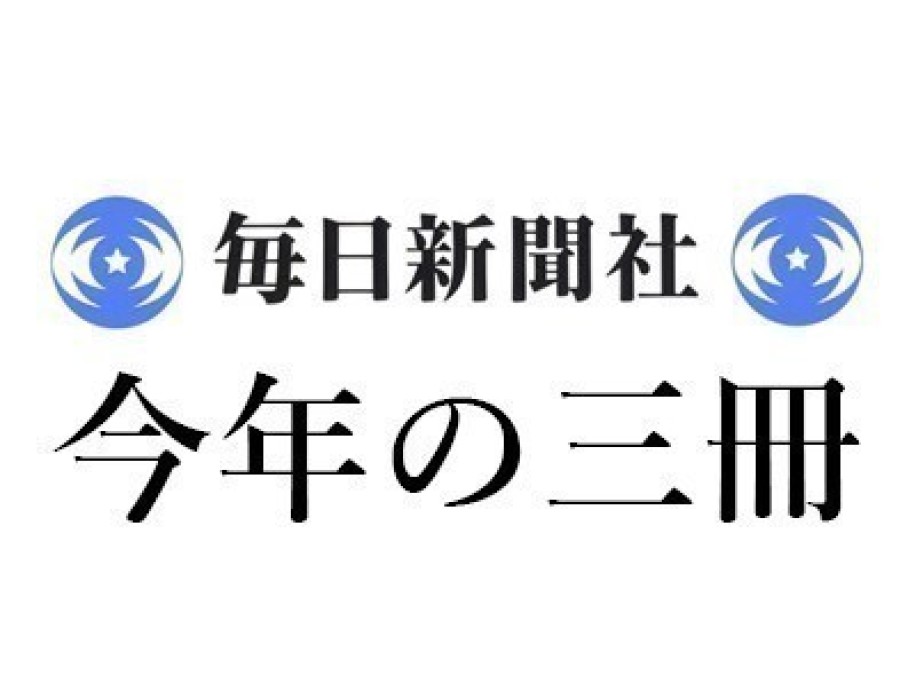書評
『犯罪』(東京創元社)
女を見る目がなかっただけじゃないか。
フェーナー氏のことを、そう単純に片づけてしまえる人は幸せだ。
フェーナー氏は二十四歳の若き医師。二度しか女性体験のなかった彼は、三歳年上で床上手のイングリットにすっかりのぼせあがってしまい、出会って十日もたたないうちにプロポーズしてしまう。ところが、新婚旅行で訪れたカイロで、イングリットが過去につきあった男たちとの失望と挫折のエピソードを告白。金切り声で「あたしを捨てないと誓って!」とフェーナー氏に迫ったのだ。
ここからフェーナー氏の生き地獄のような人生が始まる。際限なく繰り出される小言。容赦なく浴びせられる罵倒。二人は一緒に寝ることもなくなるが、フェーナー氏は女性に言い寄られても、決して浮気をしない。親身になって治療することで知られる医師フェーナー氏は、毎日、イングリットが目覚める前に家を出て、遅くまでクリニックで過ごし、家にいる時は丹精こめて庭の果樹園の世話をすることで、すっかり太ってしまった妻と必要以上接触しないよう努めるようになる。
六十歳になる前の夜、フェーナー氏はイングリットがゴミ箱に捨てた結婚記念アルバムの中から、たった一枚救い出したクフ王のピラミッドの前に立つ自分と妻の写真を見る。
高名な刑事事件弁護士であるフェルディナント・フォン・シーラッハが、現実の事件に材を得て書き上げたという短篇集『犯罪』の、冒頭に置かれた「フェーナー氏」は、誓うという行為の中に最初から種を宿している背信の芽を摘み続けたあまり、そのすぐ近くに破滅という実がなりかけていることに気づけなかった、誠実で真面目な男の半生を描いて、いつまでも心に残る見事な一篇に仕上がっている。フェーナー氏は女を見る目がなかった――たしかにそうだろう。でも、それだけじゃない。女を見る目がなかっただけなら、気づいた時点で離婚でも何でもすればいいんである。フェーナー氏は女を見る目がなかったんじゃない。自分という男の成り立ちを見る目がなかったのだと、わたしは思う。そして、恐ろしいことに、たいていの人間は、自分を見る目には恵まれていないのである。
チンピラ三馬鹿トリオが犯した強盗事件が思わぬ展開を見せてオチが可笑しい「タナタ氏の茶盌」、O・ヘンリー「賢者の贈り物」の猟奇版ともいうべき「幸運」、羊の眼をくり抜き続ける伯爵家の御曹司の話「緑」、ある不幸な手違いから、二十三年間ずっと同じ展示室の見張りをし続けた警備員が精神を失調させていくさまを描いた「棘」、エチオピアの寒村を豊かにした銀行強盗の半生を描いて心温まる「エチオピアの男」など、人間の精神、その発露としての行為がもたらす不可思議や滑稽さや哀しみを伝えて、短いのに読み応えある十一篇を収録。ミステリーファン以外にもおすすめしたい一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
フェーナー氏のことを、そう単純に片づけてしまえる人は幸せだ。
フェーナー氏は二十四歳の若き医師。二度しか女性体験のなかった彼は、三歳年上で床上手のイングリットにすっかりのぼせあがってしまい、出会って十日もたたないうちにプロポーズしてしまう。ところが、新婚旅行で訪れたカイロで、イングリットが過去につきあった男たちとの失望と挫折のエピソードを告白。金切り声で「あたしを捨てないと誓って!」とフェーナー氏に迫ったのだ。
フェーナーは突然理解した。これは愛する者同士の会話ではない。扇風機、カイロ、ピラミッド、客室の熱気、すべてが一瞬にして消し飛んでしまった。フェーナーは少し身を引くと、イングリットの目を見つめ、なにをいっているか自覚しながら、「誓うよ」とゆっくり告げた。
ここからフェーナー氏の生き地獄のような人生が始まる。際限なく繰り出される小言。容赦なく浴びせられる罵倒。二人は一緒に寝ることもなくなるが、フェーナー氏は女性に言い寄られても、決して浮気をしない。親身になって治療することで知られる医師フェーナー氏は、毎日、イングリットが目覚める前に家を出て、遅くまでクリニックで過ごし、家にいる時は丹精こめて庭の果樹園の世話をすることで、すっかり太ってしまった妻と必要以上接触しないよう努めるようになる。
六十歳になる前の夜、フェーナー氏はイングリットがゴミ箱に捨てた結婚記念アルバムの中から、たった一枚救い出したクフ王のピラミッドの前に立つ自分と妻の写真を見る。
その夜、フェーナーは人生を終えるまで囚われの身なのだと自覚した。カイロで捨てないと誓った。今が困難なときだからこそ、誓いを守らなければならない。(略)写真が目の前でかすんだ。服を脱ぐと、裸のまま浴室の鏡の前に立ち、長いあいだ自分の姿を見つめた。それから浴槽の縁にすわり、大人になってはじめて泣いた。
高名な刑事事件弁護士であるフェルディナント・フォン・シーラッハが、現実の事件に材を得て書き上げたという短篇集『犯罪』の、冒頭に置かれた「フェーナー氏」は、誓うという行為の中に最初から種を宿している背信の芽を摘み続けたあまり、そのすぐ近くに破滅という実がなりかけていることに気づけなかった、誠実で真面目な男の半生を描いて、いつまでも心に残る見事な一篇に仕上がっている。フェーナー氏は女を見る目がなかった――たしかにそうだろう。でも、それだけじゃない。女を見る目がなかっただけなら、気づいた時点で離婚でも何でもすればいいんである。フェーナー氏は女を見る目がなかったんじゃない。自分という男の成り立ちを見る目がなかったのだと、わたしは思う。そして、恐ろしいことに、たいていの人間は、自分を見る目には恵まれていないのである。
チンピラ三馬鹿トリオが犯した強盗事件が思わぬ展開を見せてオチが可笑しい「タナタ氏の茶盌」、O・ヘンリー「賢者の贈り物」の猟奇版ともいうべき「幸運」、羊の眼をくり抜き続ける伯爵家の御曹司の話「緑」、ある不幸な手違いから、二十三年間ずっと同じ展示室の見張りをし続けた警備員が精神を失調させていくさまを描いた「棘」、エチオピアの寒村を豊かにした銀行強盗の半生を描いて心温まる「エチオピアの男」など、人間の精神、その発露としての行為がもたらす不可思議や滑稽さや哀しみを伝えて、短いのに読み応えある十一篇を収録。ミステリーファン以外にもおすすめしたい一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする