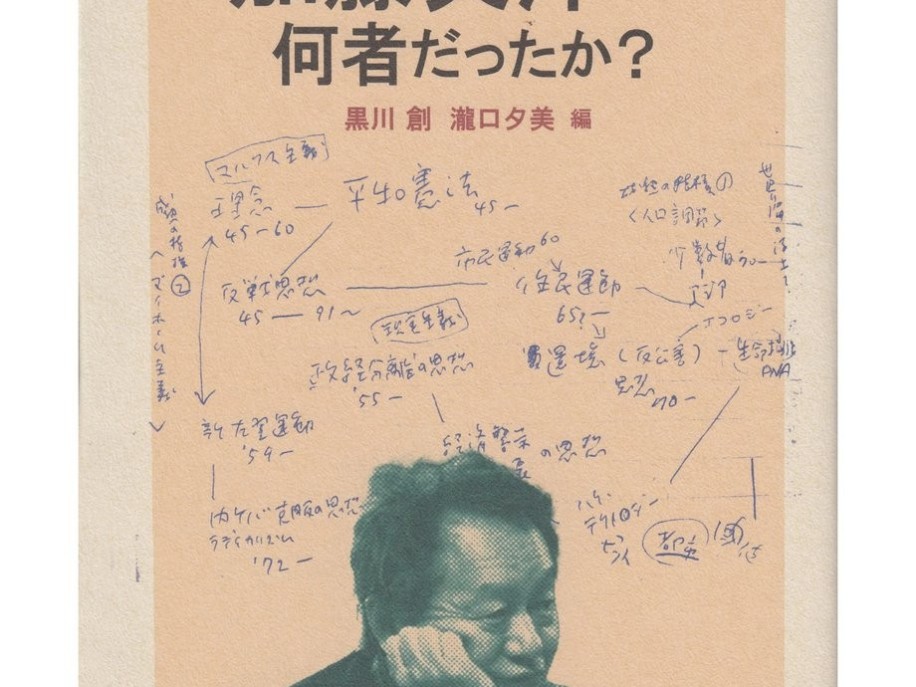書評
『パリ日記―特派員が見た現代史記録1990-2021 第5巻 オランド、マクロンの時代 2011.10-2021.5』(藤原書店)
国家・国民考える最適のたたき台
二年前、本書の第Ⅰ巻を本欄で取り上げたさい、著者が仏国防研究所財団理事長ポール・ビュイス将軍から「[ソ連の]民族運動との対峙は続く。ウクライナ共和国が抵抗する時には事態はもっと深刻になる」という「予言」を引き出したのはすごいと記したが、しかし、そのときにはよもや数カ月後にウクライナ戦争が勃発するとは思いもしなかった。以後、続巻が出るたびに熟読してきたが、最終巻である第Ⅴ巻を読み終えたいま、二一世紀の未来予測に不可欠なドキュメントかもしれないと思えてきた。というのも、産経新聞パリ支局長退任後にフリーランサーの立場から取材してきた問題をテーマ別に編集したこの最終巻は移民、暴動、テロ、環境、EUなどを扱い、国家や国民について考える最適のたたき台となっているからだ。
たとえば、フランスにおける移民と郊外暴動・テロとの関係は、新哲学派の哲学者アンドレ・グリュックスマンによれば、第五共和制の創設者ドゴールがフランスについて抱いた「ある種の想念(イデ)」を参照することで初めて説明可能となる。「[伝統的な考えでは]祖国というのは領土であり、国民のいるところだ。ところがドゴールにとっては、祖国とはそれを超えたもの、つまり一つのイデである。具体的にいうなら『自由、平等、博愛、非宗教』というイデだ」
一つにはドゴール死後五〇年で右派ばかりか左派までがドゴール主義者になってきたこともあるが、もう一つ、第五共和制憲法の「フランスは一にして不可分な、非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である」という自国定義がフランス人の思考を強く規定するに至っているという理由もある。
「つまり、『非宗教』とは、宗教的規律から解放されるがゆえに『自由』であり、公共の場で宗教的あるいは共同体的外見とは無縁であるがゆえに『平等』であり、信仰とは関係ない市民的空間を構築できるがゆえに『博愛』であるというわけだ」
ところで、近年、フランス生まれの子はみなフランス人という生地主義や、公的環境では非宗教性を義務づけられるという同化主義などの国是に対し、真っ向からこれを否定する人が増えてきたという現象が観察されている。パリでアラビア語の声高な会話を耳にするかと思えば、自分はラシスト(人種差別主義者)だと居直る反移民の人も増加している事実からもそれは明らかだ。移民自体も同化拒否の移民と同化容認の移民とに分裂し、テロリストも移民ならテロ犠牲者も移民という事件が頻発する一方、一にして不可分な共和国という理念を否定する極右も出現してきているのである。
では、こうした風潮を象徴するルペン率いる国民連合が次回の大統領選挙に勝利するかといえば、著者は政治学者のルネ・レモンの次のような言葉を参照しつつ、否定的な意見に傾く。「オーストリアなどで右派と極右との連合政権が誕生することがあるが、フランスではありえない。右派と極右の間には深くて渡れない川があるからだ」
今や二一世紀そのものの問題となりつつある「移民とテロ・暴動」という「フランス的問題」に対する最高の解説書。
ALL REVIEWSをフォローする