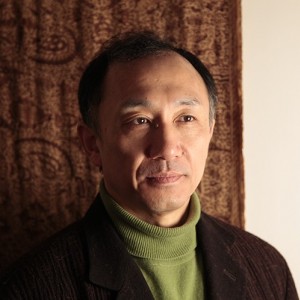書評
『中央銀行はお金を創造できるか―信用システムの貨幣史―』(名古屋大学出版会)
歴史知識と現状判断、大胆に融合
黒田日銀の「異次元の金融緩和」は、見事なまでの空砲、空論に終わった。主唱者たちは「家計が消費に企業が投資にお金を使わないのはデフレのせい」と強弁、消費と投資を回復させるため日銀にインフレ目標の設定と金融緩和を迫った。ところがどうだ。昨年来、露ウ戦争で輸入物価が上昇、国内物価もインフレになったというのに、消費も投資も低調なまま。需要不振についての理解が根本から間違っていたのだ。この失政がもうひとつ明らかにしたことがある。「日銀は市中を流通する貨幣量(マネーストック)を自由に増やせる」という前提も誤りだった。日銀は金融機関から国債を購入、日銀内の口座に振り込んでマネタリーベースを増やしたのだが、異次元なのは口座に蓄積された残高に過ぎなかった。著者の計算では2012年から22年までで5・21倍に達したものの、市中へ流出した日銀券は1・49倍に止まった。
中央銀行は市中の流通貨幣量を管理しうると思い込む人は理論家に多い。1970年代には小宮隆太郎、90年代には岩田規久男が、日銀の通貨量管理の甘さを批判した。その岩田が2013~18年に日銀に乗り込み副総裁を務めたが、インフレにするどころかマネーストックの拡大も思い通りにはならなかった。
貨幣は経済活動の内部で求められて初めて口座から引き出される。中央銀行は間接的にしか影響を与えられない。著者はこれを貨幣創出の「内生説」と呼び、外から管理しうるとする「外生説」は「神話」ないし「天動説」と断定する。
著者はイギリス金融史の泰斗。外生説と内生説の対立は近代イギリス経済史で幾度となく繰り返されてきた。ながらく決着のつかなかったこの論争を歴史から振り返り、内生説の正しさを主張したのが本書である。詳細な歴史知識と大胆な現状判断の融合は圧巻だ。
第Ⅰ部は18世紀以降のイギリス金融史。通貨学派が金兌換制や国際金本位制により「外」から貨幣価値を保証しようと試みたものの、金融恐慌は防止できなかった。銀行学派が唱えたように、金融機構全体の安定は経済の「内」から支えるしかなく、イングランド銀行は民間銀行から「銀行の銀行」「最後の貸し手」へと転じて、中央銀行となった。2014年、同行は明確に内生説を表明するに至った。
では経済の「内」には何があるのか。貨幣が導入される以前から信用取引が営まれ、口座振替を通じて債権・債務が決済されたというのが本書の主張で、第Ⅱ部は振替決済システムの生成を追っている。12~13世紀シャンパーニュ大市では地域内の錯綜する貨幣を克服するために想像上の「計算貨幣」が開発された。17世紀のアムステルダム銀行では振替決済システムが形成された。16~17世紀にはロンドンの金細工商、ゴールドスミスが金を保管する受領証として手形を発行、現代のイングランド銀行券に印刷されている文言「支払いを約束します」はその名残だという。
最先端の経済思想にも言及している。「信用の先行」は近年、考古学や古代史・人類学で証拠が発見されている。MMT(現代貨幣理論)には貨幣を負債ととらえながら中央銀行が自由に発券できるとするのは矛盾と指摘する。
ALL REVIEWSをフォローする