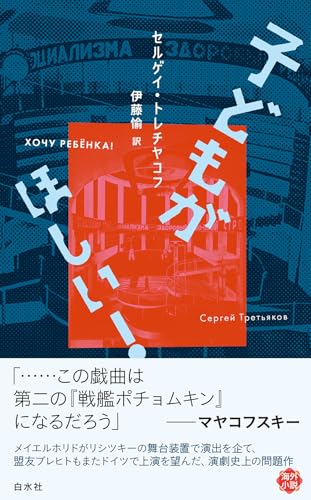書評
『チェヴェングール』(作品社)
言語の可能性を酷使した最先端の実験
現代ロシア小説の「大発見」と言えるものが、二つある。どちらもスターリン時代に書かれながら、生前は出版できず、作家の死後出版されて知られるようになり、ロシア小説史を書き換えるほどの衝撃を与えた作品である。その一つは、ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』。日本でもいち早く翻訳され、広く読まれている。そして、もう一つがプラトーノフ(一八九九―一九五一)の『チェヴェングール』である。この作品は一九二九年頃には執筆が終わっていたが、作家の存命中にまとまった長編として出版されることはなかった。一九七二年にパリで先駆的な版が出たものの、非常に不完全な形だった。そしてペレストロイカの最中の一九八八年に旧ソ連で初めて、作品の全体像を示す形で出版されたのである。
しかし、二〇世紀ロシア小説史上最大の問題作であることは専門家の間でよく知られながらも、いままで日本語に翻訳されないままだった。あまりに特異なロシア語で書かれていて、翻訳がことのほか難しかったからである。この作品を翻訳しようという試みは三〇~四〇年も前からいくつかあったようだが、おそらくすべて挫折したのだろう。
今回ようやくその『チェヴェングール』がリーダブルな日本語で読めるようになったことについては、まだ三〇歳そこそこの、とても若くて恐れを知らない優秀な訳者二人の「蛮勇」に感謝しなければならない。
この長い小説をあえて一言で要約すれば、一九一七年のロシア革命から「戦時共産主義」、「ネップ」(新経済政策)の時期を背景に、ロシア民衆の間で共産主義コミュニティがいかに成立し、崩壊したかをめぐって展開する、登場人物たちの遍歴の物語である。「チェヴェングール」とは、南ロシアに設定された架空の町で、その名前の由来も不明だが、作中にはその名前は「未知の国へ誘うざわめき(グール)に似ていた」という、ちょっとロマンチックな説明がある。
主人公のドヴァーノフは、野戦ボリシェヴィキ部隊司令官であるコピョンキンとともに、どこかに実現しているかもしれない共産主義を求めて「ひらいた心で」旅をし、チェヴェングールに行き着くのだ。この町についてドヴァーノフはこう言う。「共産主義をどこかで探す必要なんてあるのかい、同志コピョンキン?(……)チェヴェングールには共産主義を阻むものは何もないから、自分で勝手に生まれるんだ」。ただしこれが一種架空のユートピアだとしても、普通私たちが思い描く革命の産物とはずいぶん趣をことにしている。この町で人々は物質的な豊かさに背を向けて、働くのを止(や)め、皆の代わりに働く労働者は唯一、太陽(?)だというのだから。真面目なのか、冗談なのか、よく分からない理屈だ。
『チェヴェングール』は近代小説の約束事を無視して、生硬な政治用語や観念を駆使し、観念そのものが登場人物であるかのような神話的な物語を紡いでいく。ユートピアと反ユートピアを平然と同居させ、両者の区別を消滅させる。百年近く前に書かれた作品だが、いま読んでみると、小説という仕掛け、いや言語そのものの可能性をぎりぎりまで酷使した、現代でも最先端の実験であることが分かるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする