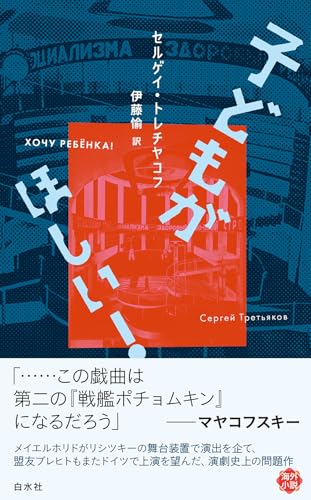書評
『理不尽ゲーム』(集英社)
時代と文学の奇跡的な共振
小説の舞台は、ベラルーシの首都ミンスク、時はこの国が旧ソ連から分離独立してから八年も経っていない一九九九年。著者はベラルーシの新進気鋭の作家である。書き出しは、一昔前によくあった青春小説のようだ。春の夕べ、芸術専門学校でチェロを専攻している十六歳のフランツィスクは、隣の部屋で長電話をしているばあちゃんに気づかれないようにこっそりアパートを抜け出そうとする。中庭で友達とサッカーをするためだ。ところがばあちゃんは耳ざとくそれに気づき、チェロの練習にはげむよう孫を叱りつける。どうやら少年は優等生ではなく、退学寸前らしい。別のある日、フランツィスクは学校一の美人のナスチャとのデートに出かけるのだが、驟雨(しゅうう)を避けるために地下通路に殺到した群衆に押しつぶされて、回復の見込みのない昏睡(こんすい)状態に陥ってしまう。するとナスチャはさっそく別の男の子と付き合い始める。母親さえも息子の回復を早々と諦め、再婚相手の医師との新しい生活設計を考える。ただばあちゃん一人が希望を捨てず、病室に泊まり込み、孫に寄り添い続けた。「いちばんすごい奇跡はいつも、望みがないときに起きるんだよ」と言い張って。昏睡状態は十年以上続き、ばあちゃんもついに寿命が尽きて亡くなった直後に、なんとフランツィスクは意識を取り戻すのだ。
目覚めて彼が見た世界は、十年前より良くなってはいない。いや、それどころか、以前にも増して強権政治の独裁が強まり、とうてい事実とは思えない「理不尽」がまかり通り、次期大統領選の有力な対立候補は不可解な首吊り「自殺」をし、現大統領の圧勝という明らかに捏造と思われる選挙結果に抗議して広場に出た人々の波は膨れ上がり、「革命の始まり」かと思えたのも束の間、警察に手荒に蹴散らされて手当たり次第に逮捕される。昏睡し続けて何も変わらなかったのは、じつは、主人公ではなく国のほうだったのか?
小説の中に固有名は出てこないのだが、これはもちろん、「ヨーロッパ最後の独裁者」が大統領を延々と務める国のほぼ現実の物語である。いや、小説は二〇一〇年で終わっているが、二〇二〇年には大統領選の不正に抗議するさらに激しい国民運動が盛りあがり、権力による国民に対する暴力はエスカレートし、現実はザミャーチンが『われら』で描いた恐ろしいディストピアにさらに近づいたのだから、文学を凌駕(りょうが)してしまったとも言えるだろう。
しかし、フィリペンコの作品は、決して事実の記録だけに価値のあるドキュメンタリーではない。これは若く優れた文学的才能が現実に最大限寄り添った結果、ある特別な歴史的瞬間に生じた、時代と文学の奇跡的な共振の産物である。もちろん、日本とは無縁の遠い国の他人事では済まされない。むしろ世界中いたるところで起こり得ることを、悪夢のようなおとぎ話に凝縮して示したものだ。小説の結末では、ドイツに出国した主人公が路上でチェロを弾き、その写真を日本人観光客の一団が嬉しそうに撮る場面が出てくるが、なんという皮肉だろうか。
著者と同じくらい若い訳者の意気込みが伝わる訳文で、解説にも力がこもっている。生きのいい外国文学の翻訳はこうでなくちゃ。
ALL REVIEWSをフォローする