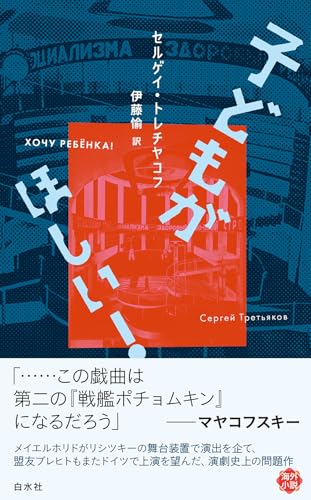書評
『ロシア文学の教室』(文藝春秋)
作品を「体験」して生きてゆく読書
著者は最近活躍が目覚ましい新世代のロシア文学者。本書は斬新なロシア文学入門書であると同時に、さわやかな学園青春小説でもある。というのも、二〇二二年の春、都内のある大学で行われたロシア文学の授業を追った「文学講義小説」の体裁を取りながら、講義に並行して、受講する学生たちの友情や恋愛も描き出しているからだ。教室の外の世界では、二月末からロシアのウクライナ侵略戦争が始まり、それが教室にも影を落としている。世間ではロシアと名の付くものをすべて忌避する動きも出ているなか、今まで通り平然とロシア文学を安全な教室で読んでいられるものだろうか?主人公湯浦(ゆうら)は大学のロシア文学科の二年生だ(その名前はロシアの男性名ユーラに通じる)。彼はテレビや新聞の報道で毎日のように伝えられる戦争の様子に心を痛め、「なにか世界のものすごくたくさんの人を巻き込んでいく巨大な渦の発生を見たような恐ろしさ」を感ずる。つまり、現実世界で進行している戦争とリンクしながら、ロシア文学の読解が進んでいくのだ。
授業のやりかたがまたユニークだ。授業を担当するのは、枚下(まいした)先生といって、その名は「巨匠」「名人」を意味する「マイスター」をもじったもののようだ。この教授、魔法のような力を持っているらしく、学生たちを作品の中に誘い込み、その世界を「体験」させたうえで、学生たちと議論しながら「戦争」「国家」「恋」「喜劇」「愛」「悲劇」「死」「時間」といったごく基本的な言葉の意味を問い直すことを通じて、文学作品を読むのはどういうことか、教えていく。
かくして湯浦は、ゴーゴリの『ネフスキイ大通り』を扱う第一講では十九世紀のサンクトペテルブルグの目抜き通りを歩き回る。そしてプーシキンの『盗賊の兄弟』を取り上げた第二講では、自らが盗賊となる。さらにゲルツェンが一八四八年パリの二月革命の渦中で書いた手記『向こう岸から』を課題図書とした第四講では、革命下のパリを思い描きながら「ゲルツェンに手伝ってもらうような心持ちでいま起きている戦争を思う」といった具合だ。
本書は全十二講の構成で、その他の作家としてドストエフスキー、レールモントフ、ゴンチャロフ、ツルゲーネフ、ネクラーソフ、チェーホフ、ゴーリキー、ガルシン、トルストイを一講につき一人ずつ扱い、全体として十九世紀初頭から二十世紀初頭までのロシア文学の名作(小説・詩・戯曲)を取り上げている。作品の選択は必ずしもそれぞれの作家の一番有名な代表作ではなく、普通の教科書のように文学史の流れが体系的に記述されているわけではない。しかし、著者はそもそも枚下先生の口を通して、文学テクストを教科書のなかに取り込もうとすると「一種の暴力性がともなう」と指摘し、文学史的な乱暴な価値判断に対して強く批判的であることがうかがわれる。
本書で一貫して実践されるのは、抽象的な知識ではなく、「体験」を通じて心を動かし、生きるための原動力を獲得するような読書である。実際の大学の授業が文学史的知識や批評理論に偏りがちなのに対して、本書はあくまでも読書の喜びの原点に立ち返ろうとする、貴重な試みになっている。
ALL REVIEWSをフォローする