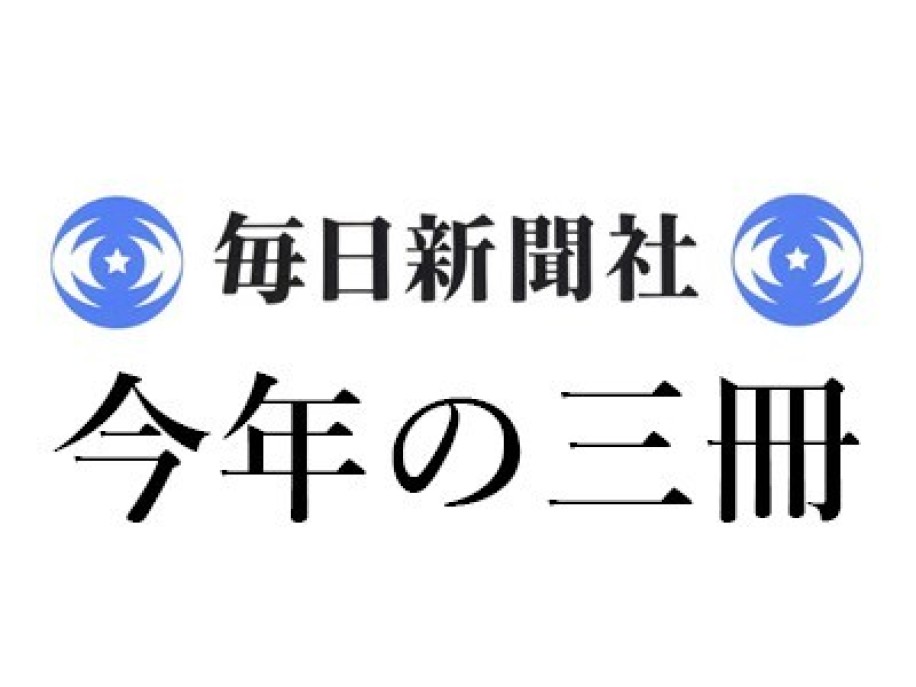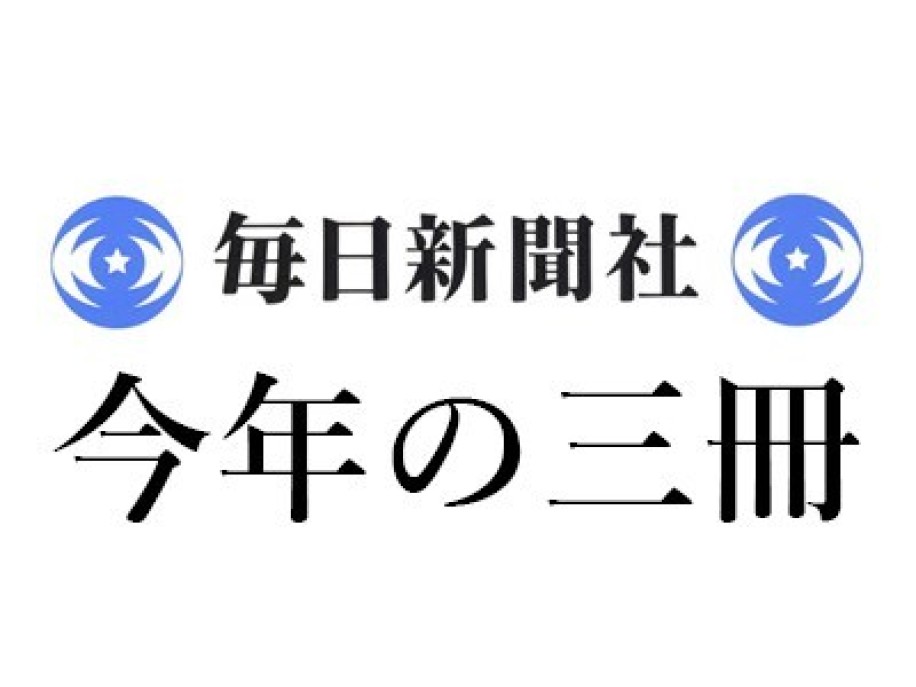書評
『陽気なお葬式』(新潮社)
「いまここ」に漂う透徹した明るさ
チャーミングな人間たちが、ぞろぞろでてくる小説である。一人の男が死ぬ話なのに、本のなかに満ちている(というか、本のなかからはみだしてきそうな気がする)のは死ではなく生だ。人が生きるというのはどういうことか、絵のように目に見える具体性を持って、音楽のように心に触れ、余韻を残すやり方で、ウリツカヤは書いてみせる。人は生きる時代を選べないし、生まれる場所を選べない。この小説の舞台はニューヨークだが、生粋のアメリカ人というのはでてこない。登場人物の多くは亡命ロシア人であり、そうでない登場人物も、イタリア人だったりパラグアイ人だったりイスラエル人だったりする。人種や宗教、文化による差異を、身をもって体験してきた、いまもしている人たち。
で、真夏の、「うだるような暑さ。湿度、百パーセント」、「すべてがいまにも融解し、半液体となった人々がゆらゆらとブイヨンスープの大気のなかを彷徨(さまよ)っていくよう」なマンハッタンの、あるアパートの一室でアーリクという男が死にかけている。アーリクは画家で、亡命ロシア人だ。部屋には彼の妻の他に、愛人や昔の恋人やその娘や、医者や友人や神父やラビや、その他誰だかよくわからない人までが、来たり帰ったり泊まったり、ほとんど住んでいるみたいだったりし、アーリクに話しかけたり薬を塗ったり、何かたべさせたり音楽を聴かせたりする。死にかけのアーリクを囲んで記念写真(!)を撮ったりもする。一人ずつ誰もに過去があり、アーリクとの思い出があり、現在の生活がある。女たちの色鮮やかさ(脆(もろ)そうな妻、実務的な昔の女、おっぱいの大きな愛人、自閉症ぎみだが賢い十五歳の少女、他にもまだいる)には息を呑(の)むし、それぞれの人生の数奇さ、豊かさ、したたるような物語性とおもしろさには陶然となるのだが、さらにそれらすべての向こうに、アーリクという男の、汲(く)めど尽きせぬ静かな魅力がある。「ねえアーリク、モスクワでの生活って、つらかった?」。十五歳の少女に尋ねられ、アーリクはこうこたえる。「ばかだな、素晴らしかったよ……。おれは、どこにいたって素晴らしい日々を送れるんだ……」。そして、実際にそれを裏づけるようなエピソードが、まわりの人々の回想のなかから幾つもみずみずしく立ちあがってくる。
亡命者というのは故郷と過去の人生を捨てた、あるいは無理矢理それらから切り離された人だと言えるのかもしれないが、アーリクは故郷ごと、人生ごと移動し続けた。だから彼の人生はすべて、いまここにある。真夏のマンハッタンのアパートの一室に。この、いまここにあるという一点の確かさ故に、小説は透徹したあかるさを漂わせる。アーリクだけではない。登場人物の誰もが多くの困難にさらされながら人生ごと生きのびて、いまここにいる。だからアーリクの死にかけているその部屋は、みんなの人生の全部が集まった場所になり、ある種の活気さえ孕(はら)む。
回想場面以外は全編を通じてほとんど寝ているだけのアーリクだが、最後に読者は彼から贈り物をもらうことになる。まるで自分も昔から彼を知っていたかのような、強いなつかしさにたじろぎ、彼を失う悲しみに胸を塞がれながらも、祝福されたように感じることになる(はずだ)。(奈倉有里訳)
ALL REVIEWSをフォローする