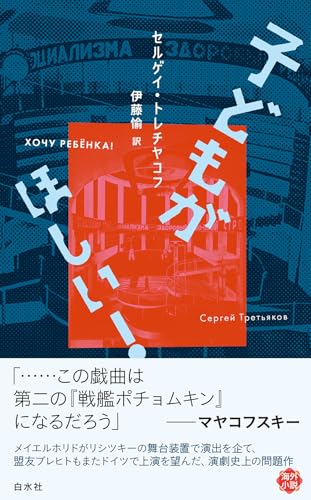書評
『親衛隊士の日』(河出書房新社)
現実と重なるディストピア小説
ロシアがウクライナに侵攻を開始したとき、ロシアの現代作家ソローキンは即座にエッセイを発表した。「プーチン 過去からのモンスター」と題されたその文章のなかでソローキンはプーチンを評して<自分自身の絶対的な権力、帝国的な攻撃性、ソ連崩壊のルサンチマンによってあおり立てられた敵意、西側の民主主義に対する憎悪をたっぷりと吸い込みながら、怪物は年を追うごとに力を蓄え、次第に成長していった>と述べた(『文藝』夏季号)。侵攻開始から9カ月近く経ったいま、その分析の正確さにあらためて驚く。長編小説『親衛隊士の日』の舞台は2028年のモスクワ。現在から6年後のその世界では、帝政ロシアが復活している。小説は皇帝の親衛隊士、アンドレイ・ダニーロヴィチのある日を描く。
原著の発表は2006年。日本語訳の単行本が河出書房新社から出たのが13年9月。そのときぼくは、たんにイワン雷帝の時代を近未来に蘇らせたディストピア小説としか思わなかった。よくできているし、ソローキンお得意のおぞましい描写も随所に出てくるし、おもしろい。でも、まさか現実になるとは……。
その半年後の14年3月、ロシアはクリミアを併合した。非道ではあるが、8年後にウクライナ侵攻が起きるとは思わなかった。ぼくはプーチンの怪物性についてあなどっていたのだ。また、いくらプーチンが暴走してもロシア国民がそれを許さないだろうと信じていた。甘かった。
プーチンは『親衛隊士の日』に描かれている皇帝にならんとしている。21世紀のイワン雷帝に。
『親衛隊士の日』の世界では、皇帝が絶対的な権力を握っている。その手となり足となるのが親衛隊士たちだ。彼らは国家の敵を取り締まる。罪をでっち上げ、暴力と略奪の限りを尽くす。あるいは皇帝の身内の犯罪をもみ消す。
小説ではイワン雷帝の時代の16世紀と近未来の21世紀が奇妙なかたちで融合している。携帯電話やAIアシスタントなどハイテクが普及し、会議もリモートで行われる。親衛隊士たちのクルマは真紅のメルセデスベンツ。しかし彼らの行動は中世のよう。たとえば主人公の労働服=仕事着は<十字架の刺繡が施された白い肌着、斜め襟の赤いシャツ、金銀の糸で織りあげられ、貂(てん)の縁飾りがつけられた錦のジャケット、ビロードのズボン、靴底に銅を打ちつけたモロッコ革の赤いブーツ>。出勤を見送る「ばあや」は聖人のイコンを抱き、十字を切り、聖母マリアらに主人公を守りたまえと祈る。クルマのバンパーには犬の生首(この日は<毛むくじゃらのウルフハウンド>)が、トランクには箒が括りつけられている。訳者のあとがきによると、イワン雷帝の親衛隊士たちも馬の首に犬の首を縛りつけ、鞭の柄に箒の形をした獣の毛を括りつけていたそうだ。
21世紀の皇帝と親衛隊士たちは国民に厳格な秩序を強制しながら、自分たちは賄賂を取り、略奪や性暴力を繰り返し、違法ドラッグに耽り、性的狂乱に明けくれる。皇帝の権威に服従・追従し、媚びへつらう快楽と、その権威を利用して弱い者に暴力を行使する快楽が彼らを貫く。だが、親衛隊士たちの欲望が現代日本の私たちと無縁だと言い切れるだろうか?
ALL REVIEWSをフォローする