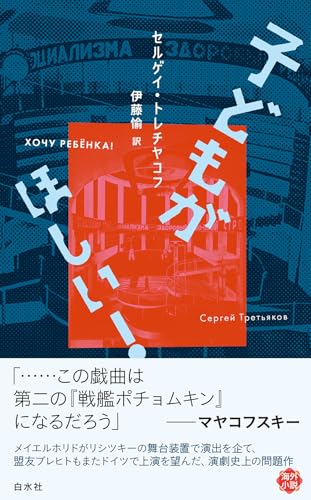書評
『ステパンチコヴォ村とその住人たち』(光文社)
ユーモアの限度超えた陰惨さ、真骨頂
ロシアの文豪ドストエフスキーといえば、『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』といった後期の大長編が圧倒的に有名である。その一方で、『ステパンチコヴォ村とその住人たち』(一八五九年作)という知られざる「ユーモア小説」のことは聞いたこともない、という読者が多いのではないだろうか。小説の語り手は、大都会ペテルブルクに住む、まだ二十二歳のセルゲイ青年。おじのロスタネフ元大佐が住む郷里の村からやってきた召使に、村で奇怪な事態が出来していると聞かされて驚愕し、おじに手紙で問い合わせるのだが、返事は曖昧で奇妙なものばかり。そのうえ、おじのところに住み込んでいるおじの子どもの家庭教師とすぐにも結婚するように、と提案されてしまうのだ。そこでセルゲイは村で何が起こっているかを明らかにし、窮地に陥っているらしいおじを救うべく、意気込んでステパンチコヴォ村に乗り込むのだが……。
村でセルゲイが見たのは、想像もできなかった大混乱。「ノアの方舟」のように多彩な人々がおじの家に暮らしているのだが、そろいもそろって変人奇人ばかり。その中に横暴な独裁者のように君臨しているのがフォマーという五十がらみの男である。彼はロスタネフの母(将軍夫人)にとりいって絶大な権力をほしいままにし、ばかげた気まぐれや無理難題を周囲の人々に吹っ掛けて従わせているのだ。彼は「怪物的な自尊心の持ち主」で、自分の権威を少しでも脅かしそうな人に対して常軌を逸した猜疑心と敵意を燃やすのである。
その彼が将軍夫人と手を組んで、ロスタネフ元大佐を裕福だが頭の空っぽな「色情狂」の女と結婚させようとしている。一方、当の元大佐は可憐な住み込み家庭教師にぞっこん惚れこんでいるのだが、自分からはその気持ちを告白できないでいる。そもそもこのロスタネフという男は稀に見る優しい性格の持ち主で、何か頼まれたら決して嫌とは言えず、フォマーや母親が機嫌を損ねれば、悪いのは自分だといつでも納得してしまうのだ。
フォマーとロスタネフという二つの極端なキャラクターの創造は、作家の才能の賜物だろう。かくして、世にも稀な性格の人物たちの思惑が複雑に絡みあい、金と恋をめぐって予想外のドタバタが二日間に凝縮されて展開する。そして呆然とした読者の目の前で、ごく卑俗な内容と崇高な理念のグロテスクな混淆(こんこう)、道化的でナンセンスなくどくどしさ、登場人物が集合してカーニバル的な様相を示す劇的な場面などが交錯する。この時期ロシアでは、いまだに廃止されない農奴制のもと社会は深刻な矛盾に苦しんでいたはずだが、ドストエフスキーの筆は社会問題には向かわず、饒舌な言葉の奔流の中で自意識のドタバタ劇場を繰り広げる。それは確かに可笑しいのだが、あまりに常軌を逸していて、ユーモアの限度を超えた陰惨な印象を与えるほどだ。しかし、それこそがドストエフスキーという作家本来の持ち味ではないか。
本作はこれまでも翻訳されて全集には収録されていたが、全訳が文庫版になったのは今回が初めてである。端正な新訳でこの「怪作」が蘇ったことを喜びたい。ここに描かれていることは、現代日本の政治やカルト問題にも通じる側面があり、決して他人事ではない。
ALL REVIEWSをフォローする