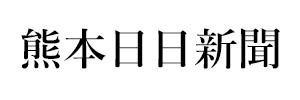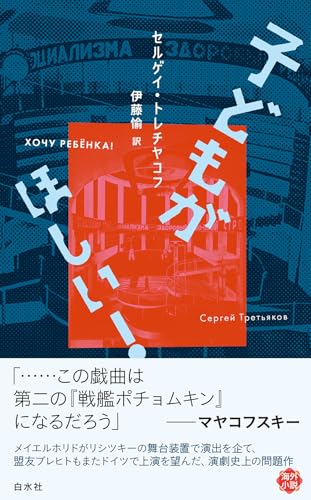書評
『トランス=アトランティック』(国書刊行会)
物真似がうまい、やたらやかましいタレントがいるじゃないですか。柳沢慎吾。たとえば、あの人になってみるわけです。柳沢慎吾の落ち着きのない目で世間を眺めてみる。柳沢慎吾のとりとめもない精神で世界について考えてみる。柳沢慎吾のけたたましい口で喋ってみる。それって、かなり世界の見方、感じ方に変更を強いられるはず。で、小説を読むってのは、そういう経験を指すのではないかと。自分とは違う精神構造や世界観の持ち主の主観を一度通した物語を生きてみる。そのことによって、それまで当たり前だと思っていたり、現実だと思っていた、自分なりの“確信”に揺らぎが生じる。優れた小説には慣習や常識で曇った目を浄化する働きがあるわけです。
たとえば、全体主義っていう、個人の生活や考えは国家全体の利害に従うべきだっていう思想がありますよね。ある種の共産主義体制とかファシズムとかを、わたしなんかはすぐ思い浮かべますけど、このテーマを扱っても、当然のことながら作家によってずいぶん描き方は異なってくるわけです。ロシアのソルジェニーツィン、中国の莫言(モー・イェン)、ドイツのケストナー。それぞれ面白いくらいタッチが違います。そして、わたしは小説というものは、テーマではなく、どちらかといえばそうしたタッチの差異こそを楽しむべき芸術だと思っているのです。
今回紹介するゴンブローヴィッチなんかも、両大戦間期のポーランド・ナショナリズムを批判した『フェルディドゥルケ』によって過剰な政治的読解がされたあまり、なかなか広く自由に読まれることがなかった不幸な作家なんですが、この『トランス=アトランティック』をひもとけば、そんな先入観はどっかに吹き飛んでしまいます。いや、ここでも、描かれているのは世界大戦に巻き込まれた祖国ポーランドを襲うスターリン主義への怒りだったりするんです。でも、それを活写するゴンブローヴィッチの筆致はといえば――。
語り手は、アルゼンチンに渡って祖国に帰れなくなった小説家の「小生」。そうはいっても生計を立てなくてはならないので、ブエノスアイレスのポーランド人社会に生きる男たちと接触します。ところが、永遠の青二才たる「小生」の目に映るそうした人々はバカばかり。スターリン主義に染まり、自由なものの見方をあっさり捨て去ってしまうような大人どもが大きな顔をしている祖国なんかもういらない。「小生」はアルゼンチン人のゲイが発した「あんた、自分がポーランド人だってことに嫌気が差したりしない?(略)どこまでいっても受苦と受難の連続じゃなかった?(略)別な何か、新しい何かへと変身したい願望はない?」「あんた、口癖のように祖国、祖国って言うけれど、それって何なの? それより孫国の方がステキじゃない?」という言葉に共鳴し、アホでマヌケな大人どもを叩き潰すことを決心するのです。
という粗筋は、でも、実はあまり意味がありません。こんな理路整然とした、つまり、つまらないストーリーでは全然ないからです。ゴンブローヴィッチが自らの主観を託した「小生」という人物は、聡明にはほど遠い、どちらかといえば道化的存在なので、彼が行く先々で巻き起こす事件は、常に騒々しい笑いを伴います。実は作者がこの作品の中で繰り出している言語実験は、わたしのごとき一小説ファンでは太刀打ちできないほど深遠なのですが、嬉しいことに決して難解ではありません。恥をかき冷や汗をかきながら支離滅裂な行動を繰り返す「小生」のキャラクターのユニークさや、反復とズレを繰り返しながら刻まれるリズミカルな文章が生み出すユーモアに乗せられて、一気に最後まで読まされてしまう。これはそんな読みやすい実験小説なのです。
ゴンブローヴィッチになったつもりで、今、この世界を眺めてみる。すると、ずいぶんグロテスクな場所に見えてきて、パーティの席で大恥をかいた「小生」のように、出口目指して「すたすた、すたすた、すたすた歩き」をしたくなります。柳沢慎吾になるよりも、それはずいぶん知的で滑稽で哀しく怖ろしい経験になるのではないでしょうか。
【この書評が収録されている書籍】
たとえば、全体主義っていう、個人の生活や考えは国家全体の利害に従うべきだっていう思想がありますよね。ある種の共産主義体制とかファシズムとかを、わたしなんかはすぐ思い浮かべますけど、このテーマを扱っても、当然のことながら作家によってずいぶん描き方は異なってくるわけです。ロシアのソルジェニーツィン、中国の莫言(モー・イェン)、ドイツのケストナー。それぞれ面白いくらいタッチが違います。そして、わたしは小説というものは、テーマではなく、どちらかといえばそうしたタッチの差異こそを楽しむべき芸術だと思っているのです。
今回紹介するゴンブローヴィッチなんかも、両大戦間期のポーランド・ナショナリズムを批判した『フェルディドゥルケ』によって過剰な政治的読解がされたあまり、なかなか広く自由に読まれることがなかった不幸な作家なんですが、この『トランス=アトランティック』をひもとけば、そんな先入観はどっかに吹き飛んでしまいます。いや、ここでも、描かれているのは世界大戦に巻き込まれた祖国ポーランドを襲うスターリン主義への怒りだったりするんです。でも、それを活写するゴンブローヴィッチの筆致はといえば――。
語り手は、アルゼンチンに渡って祖国に帰れなくなった小説家の「小生」。そうはいっても生計を立てなくてはならないので、ブエノスアイレスのポーランド人社会に生きる男たちと接触します。ところが、永遠の青二才たる「小生」の目に映るそうした人々はバカばかり。スターリン主義に染まり、自由なものの見方をあっさり捨て去ってしまうような大人どもが大きな顔をしている祖国なんかもういらない。「小生」はアルゼンチン人のゲイが発した「あんた、自分がポーランド人だってことに嫌気が差したりしない?(略)どこまでいっても受苦と受難の連続じゃなかった?(略)別な何か、新しい何かへと変身したい願望はない?」「あんた、口癖のように祖国、祖国って言うけれど、それって何なの? それより孫国の方がステキじゃない?」という言葉に共鳴し、アホでマヌケな大人どもを叩き潰すことを決心するのです。
という粗筋は、でも、実はあまり意味がありません。こんな理路整然とした、つまり、つまらないストーリーでは全然ないからです。ゴンブローヴィッチが自らの主観を託した「小生」という人物は、聡明にはほど遠い、どちらかといえば道化的存在なので、彼が行く先々で巻き起こす事件は、常に騒々しい笑いを伴います。実は作者がこの作品の中で繰り出している言語実験は、わたしのごとき一小説ファンでは太刀打ちできないほど深遠なのですが、嬉しいことに決して難解ではありません。恥をかき冷や汗をかきながら支離滅裂な行動を繰り返す「小生」のキャラクターのユニークさや、反復とズレを繰り返しながら刻まれるリズミカルな文章が生み出すユーモアに乗せられて、一気に最後まで読まされてしまう。これはそんな読みやすい実験小説なのです。
ゴンブローヴィッチになったつもりで、今、この世界を眺めてみる。すると、ずいぶんグロテスクな場所に見えてきて、パーティの席で大恥をかいた「小生」のように、出口目指して「すたすた、すたすた、すたすた歩き」をしたくなります。柳沢慎吾になるよりも、それはずいぶん知的で滑稽で哀しく怖ろしい経験になるのではないでしょうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする