書評
『幸田露伴』(筑摩書房)
幸田露伴――露一滴
春以来、私の仕事かばんに入っていたのは、ちくま日本文学全集の『幸田露伴』である。持ち歩くに良い。文庫版にしては堅牢なつくりの角々がだいぶ痛んできた。地下鉄の中で、喫茶店で人待つ間に、どこでも開いて拾い読みをする。日常の憂さを忘れる。露伴の気宇にのまれるのである。
身には疾(やまい)あり、胸には愁(うれい)あり、悪因縁(あくいんねん)は遂(お)えども去らず、未来に楽しき到着点(とうちゃくてん)の認めらるるなく、目前に痛き刺激物(しげきぶつ)あり、慾(よく)あれども銭なく、望みあれども縁(えん)遠し、よし突貫してこの逆境を出(い)でむと決したり」(『突貫紀行』)。
この強い文章にいくたび勇気づけられたことか。北海道余市の電信技士だった二十歳の露伴が、文学を志して忽然、脱出する記録である。小樽、岩内、寿都(すっつ)、松前、函館と歩きに歩き、海峡を渡って浅虫、野辺地、三の戸と海岸線を下り、夜どおし歩いてようやく郡山から汽車に乗る。東京までおよそ一ヵ月。しかしこの激しく悲槍な徒歩行のなかにも、読書あり、痛飲あり、シャレあり。きのこづくめの宿の飯に閉口したり、久しぶりの若い女性の姿に感銘したりする。眼はなんともあたりまえで、体の動かし方はやわらかい。
夏中は「観画談」「幻談」「雪たたき」の頁をめくれば涼しくしていられた。大学生が奥州の雨夜、山寺に泊る「観画談」にこんなくだりがある。「自分の生涯(しょうがい)の中(うち)のある日に雨が降っているのでは無くて、常住不断(じょうじゅうふだん)の雨が降り通している中に自分の短い生涯がちょっと挿(はさ)まれているものででもあるように降っている」。ついに「世界はただこれ ザアッ というものに過ぎない」。ひるがえって「このザアッというのがすなわちこれ世界なのだナ」と思うに到る。それで「性が抜けて、そして眠に落ちた」というのだが、ここを読むといつも心がほどけ、落ちつく。
歴史小説「雪たたき」の冒頭は雄渾だ。深い雪の中を悠然と歩くのは何者なのか、そう思ったとき、すでに物語にはまり込まされている。「どんな運にでもぶつかってくりょう、運というものの面(つら)が見たい」とこの男「にッたり」と笑う。この胆力は自然主義の「青白きインテリ」には見られないところだ。
さらに「幻談」。江戸湾で釣りの最中に、溺死者がひっかかる。隠語で「お客さん」という中浮きの水死人がじつにいい竿を持っている。「それは旦那、お客さんが持って行ったって三途川(さんずのかわ)で釣をする訳でもありますまい」と船頭がいうので、主人公は死人がつかんだ竿尻に親指をかけてぎくりとやってしまう。「指が離れる、途端に先主人(せんしゅじん)は潮下(しおしも)に流れて行ってしまい、竿はこちらに残りました」。そして翌日、またあの竿が現われる。体の重みがなくなってふわふわと波に漂いそうな気さえする。
幸田露伴の文学は今日完全にアクチュアリティーを失っている。露伴の名はまだ多少は知られているかもしれないが、その作品はもはやほとんど読まれてはいないだろう(『幸田露伴の空間』)
と、すでに三十年前、露伴を「壮大な落日」にたとえたのは故篠田一士であった。
私自身、仕事の必要で『五重塔』をくり返し読んだほか、『一國の首都』や書簡集ぐらいにしか触れていない。だから今度のこの本は事件だった。
有名な『五重塔』は岩波文庫にまかせ、軽い上質な人情噺「太郎坊」や「貧乏」で幕をあける。新字新仮名、ルビつきのゆったりした組みで読むと、露伴てどこが難しいのと乗せられる。
「太郎坊」とは二十年来用いた猪口(ちょこ)の愛称である。賤しからず豊からず暮らす家の夕餉の平和な風景、主人は庭に水を打ち、湯に行ったのち縁側で烟草(たばこ)をふかす。その間に細君は燗をつけ、鰺(あじ)の塩焼を肴に運ぶ。「さぞお疲労(くたびれ)でしたろう」と妻がねぎらえば、「労働ぐらい人を幸福にするものは無いかも知れないナ」と主人が受ける。ここを読むとあアと悲しくなる。ついぞそんな言葉をつれあいにかけ得なかった。水を打つ庭はなく、長く親しんだ器もなく、こんなしっくりした仲の夫婦もいまやそうはいまい。その猪口が割れて主人の初恋が穏やかに語られる。
「貧乏」はこれよりずっと下町だろう。遠慮ない夫婦の会話に恋着がほのみえる。帯や衣類(きもの)を飲むほどお銭(あし)がなくとも、この女房は少しもめげない。金や世間体で選んだ男ではないのだ。「一体苦(にが)み走(ばし)りて眼尻(めじり)にたるみ無く、一の字口の少し大(おおき)なるもきっと締(しま)りたるにかえって男らしく、娘にはいかがなれど、浮世の鹹味(からみ)を嘗(な)めて来た女には好かるべきところある肌合なり」
この男が、「厭気(いやけ)がさしたらこの野郎に早く見切りをつけやあナ。惜いもんだが別れてやらあ。汝(てめえ)が未来(このさき)に持っている果報の邪魔(じゃま)はおれはしねえ」。ぐっとくるセリフだ。
いわれた女は「修行(しゅぎょう)を積んだものか泣きもせず、ジロリと男を見たるばかり」「何が何でもわたしゃアいいよ、首になっても列(なら)ぼうわね」。
露伴の女が古いなどとはいわせまい。この意気地と情愛、気合と人間の真率さこそ自立の根拠ではないか。女性にぜひ読んでほしい二作である。
「鵞鳥」はありがたかった。御前製作をする栄誉を得た鋳造師若崎の煩悶と同僚中村の励まし、意地の張り合いを描いた佳品。二人とも職人上りの美校教授らしいが、たぶんふさふさした髪の中村とは高村光雲、痩形小づくりのまめな若崎とは岡崎雪聲のことだろう。光雲には『光雲座談』があるが、雪聲の人となりを知る資料は少ない。モデル小説として読むのは邪道だろうが、岡倉天心とも親交があり、明治三十一年のいわゆる美校騒動では公平な論評をくずさなかった露伴がこの二人をどう描くか。中村の老練、若崎の実直、二人の同時代の名人をじつに生き生きと書き分けている。
選択と配列も見事、松山巌の解説も絶品だ。本書を入門とすれば、岩波版の随筆選集、小説選集がある。絶版だが全集もある。当分楽しめそうだ。と思うとまた少し、生きる勇気が湧く。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
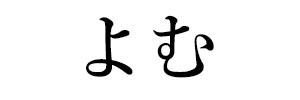
よむ
ALL REVIEWSをフォローする




































