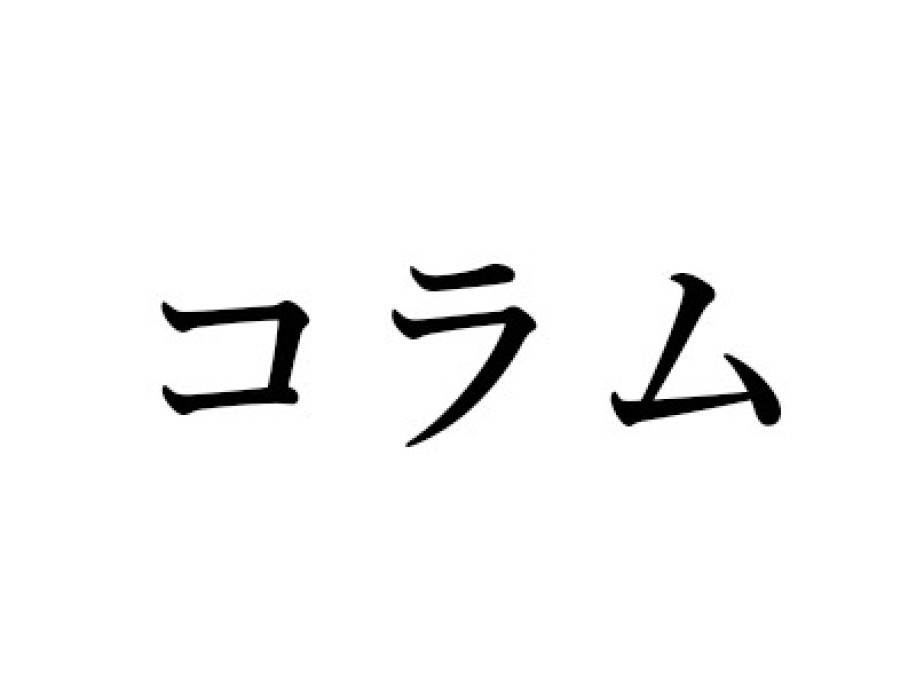読書日記
鹿島茂「私の読書日記」週刊文春2017年12月21日号 石井洋二郎『時代を「写した」男ナダール 1820-1910』(藤原書店)、巖谷國士『澁澤龍彦考/略伝と回想』(勉誠出版)
週刊文春「私の読書日記」
×月×日
引っ越しというのは多くの苦痛を伴うが、悪いことばかりではない。蔵書の取捨選択をしているうちにこんなものまで持っていたんだという発見があるからだ。今回の最大の発見は、行方不明になっていた「パンテオン・ナダール」が出てきたこと。「パンテオン・ナダール」とはナダールが同時代の詩人・小説家・劇作家・批評家・作曲家・画家・彫刻家など総計二五〇名(第二版二七〇名)の群像を描いた巨大な石版画で、ナダールのカリカチュアをコツコツと集めていた私はナダール・コレクションの締めくくりとして、どうしてもこの「パンテオン・ナダール」が欲しかったのである。ようやく手に入れたのが一〇年ほど前だが、その後、何回か引っ越しを繰り返すうちにどこかに仕舞いこまれ、見当たらなくなってしまっていたのだ。私はナダールに限らず一九世紀フランスのカリカチュアに関してはそれなりのコレクションを有しているのだが、カリカチュアというのは日本では不人気らしく、展覧会開催の手を挙げてくれる美術館が一つもないのは残念。さて、ナダールであるが、評伝を書くのだったらこれほど面白い人物はいない。私もいずれ手をつけようと資料を集めていたのだが、日本にいてはアクセスできない原資料があったため執筆を諦めていたところ、ここに来て日本人の手になる評伝が二冊ほど刊行された。そのうちの一冊が石井洋二郎『時代を「写した」男ナダール 1820-1910』(藤原書店 8000円+税)。これ以上はないというほど徹底的に調べられた優れた評伝である。
ナダールことフェリックス・トゥルナションは一八二〇年にパリで生まれ、一時リヨンに移るが、子供時代はパリで過ごす。免許医の医学校に通うが、在学中から新聞に投稿を始め、パリに戻ってボヘミアン生活に身を投じる。ボヘミアン時代に知り合ったのがボードレールで、生涯の友となるが、興味深いのは後にボードレールのミューズとなる黒白混血の女優ジャンヌ・デュヴァルは最初、ナダールの愛人だったこと。二人の親友は時を置いて同じ女性に恋したのである。やがてナダールは「シルエット」や「コルセール=サタン」などの絵入り新聞でカリカチュールも担当するようになり、イラストレーターとして頭角をあらわす。カリカチュア新聞の王シャルル・フィリポンと知り合って一八四八年から「ジュルナル・プール・リール」でベルタルやドレなどと戯画を競い、二月革命に際してはポーランドの独立を助ける義勇軍に参加したり、外務大臣の官房長官となった出版人エッツェルの密偵としてポーランド各地を旅する。帰国後は、エッツェルが創刊した反ボナパルティスト新聞「ルヴュ・コミック」でルイ・ナポレオン・ボナパルトを揶揄する連作「レアック氏」を発表し、風刺画家としての地歩を固める。
一八五一年のルイ・ナポレオンのクーデター以後は詩人や作家、芸術家などの顔を描くカリカチュールに専念。ここから「パンテオン・ナダール」の構想が生まれてくる。「パンテオン・ナダール」制作の過程で必要から人物写真の撮影技法を覚え、次には肖像写真家として重きをなすが、常に新しい冒険を求めてやまない性質ゆえに空中撮影や地下撮影に挑戦、見事これに成功する。そして次には空中撮影の経験から気球での冒険に乗り出し、この分野でも第一人者となる。
と、このようにナダールの経歴はざっと記しただけでも十分に面白いが、しかし、いざ細部をつめようとすると、これが意外に難物なのである。というのも本人が晩年に書いた自伝の類いがかなり曖昧に書かれていたり、自己弁護を含むものだから、証言の裏をいちいち取らなければならないからである。謎の詩人ロートレアモンの傑作評伝『ロートレアモン 越境と創造』で実証の物凄さを見せつけた著者にふさわしく、本書はこの裏取りが卓越しており、「ナダール」という名前を巡る兄(フェリックス)と弟(アドリアン)の確執を実際の裁判記録に当たって確認したり、写真技術は「パンテオン・ナダール」制作中に習得したとする自伝の証言の不確かさを例証したりと、オビにある通り、「決定版評伝」となっている。
しかし、本書の目的はじつは別のところにある。それは一九世紀の「人物交差点」ともいうべきナダールを介して、一九世紀という時代そのものを浮かび上がらせることである。本書は、「歴史をいろどる数多くの著名人との交流関係を通して、彼が生きた一九世紀フランスという時空の肖像を描きだそうとする試みである。特に、これまでは『文学史』『思想史』『芸術史』といった個別の文脈に切り離して語られることの多かったこの世紀の文化の多様な担い手たちを、ナダールという固有名詞をいわば蝶番にして相互に結びつけ、彼の覗きこんだレンズを通して新たな相貌のもとに照射することができればと思う」。この試みは十分に成功しているようである。
×月×日
現在、私は個人的にALL REVIEWSという無料の書評再録サイトを運営しているが、御遺族の許可を得て、そこに澁澤龍彦の書評も掲載している。ランペドゥーサ『山猫』、ケネス・クラーク『ザ・ヌード』、三島由紀夫『午後の曳航』、谷崎潤一郎『瘋癲老人日記』、宮沢賢治『新編 銀河鉄道の夜』などだが、これがほれぼれとするほど見事な書評なのである。まさに書評芸! それはさておき、目下、澁澤龍彦没後三十年を記念する「澁澤龍彦 ドラコニアの地平」展が世田谷文学館で開催中(十二月十七日まで)であるが、それに合わせて、メイン・コーディネーター巖谷國士の澁澤龍彦論を集大成した『澁澤龍彦論コレクション』全五巻が勉誠出版から刊行されている。その第一巻が『澁澤龍彦考/略伝と回想』(3200円+税)。澁澤龍彦と最も個人的に親しかった著者だけに、世間一般の澁澤像とは違うポルトレが巧みに描かれている。たとえば、著者が強調するのは、一九七〇年八月末、楯の会の制服に身をくるんで現れた三島由紀夫に見送られて羽田空港からヨーロッパに旅立った澁澤龍彦が、この旅を契機に大きく変わったという事実である。それまでは明らかに一種のユートピストとして、城壁にかこまれた小宇宙のような空間の維持・強化をこととしていた澁澤龍彦の文学が、時間へと、水へと、流動的な自己へと溶けひろがっていったのは、旅という契機にかかわることではなかったろうか
とりわけ、イタリアやスペインなどの「南」への旅が澁澤龍彦の中にあった「何か」を開いたのである。それは、あるいは少年時代に惑溺した南洋一郎や島田啓三の南洋文学への回帰だったのかもしれないが、しかし、むしろ、少年だった頃の「私」、あえて封印してきた「私」との出会いであったというべきなのである。
エッセーからフィクションへ、ストイックな博物誌からロマネスクな短篇小説へという変貌、あるいは生長は、かならずしもジャンル上の進化だけを意味するものではない。やがてフィクションとして開花することになるいくつかの「観念の萌芽」には、「私」をめぐるそれもふくまれていた。澁澤龍彦における小説への出発は、未知なる「私」との出会いだった。そして、それは同時に、それまでの彼自身の全作品活動をも回顧しつつその新しい「私」のうちに再統合してゆく、「旅」としての文学のはじまりでもあったように思われる
そうした「私」が大きく開花したのが『高丘親王航海記』だが、その時にはすでに病魔が澁澤龍彦の肉体を深く蝕んでいた。しかし、トータルな意味では、澁澤龍彦は幸せな作家だといえる。最良の理解者に恵まれたばかりか、没後三十年の回顧展にも多くのファンが駆けつけているのだから。どうやら、澁澤龍彦という「モダンな親王」は死後も永遠に幸福な旅を続けているようである。
ALL REVIEWSをフォローする