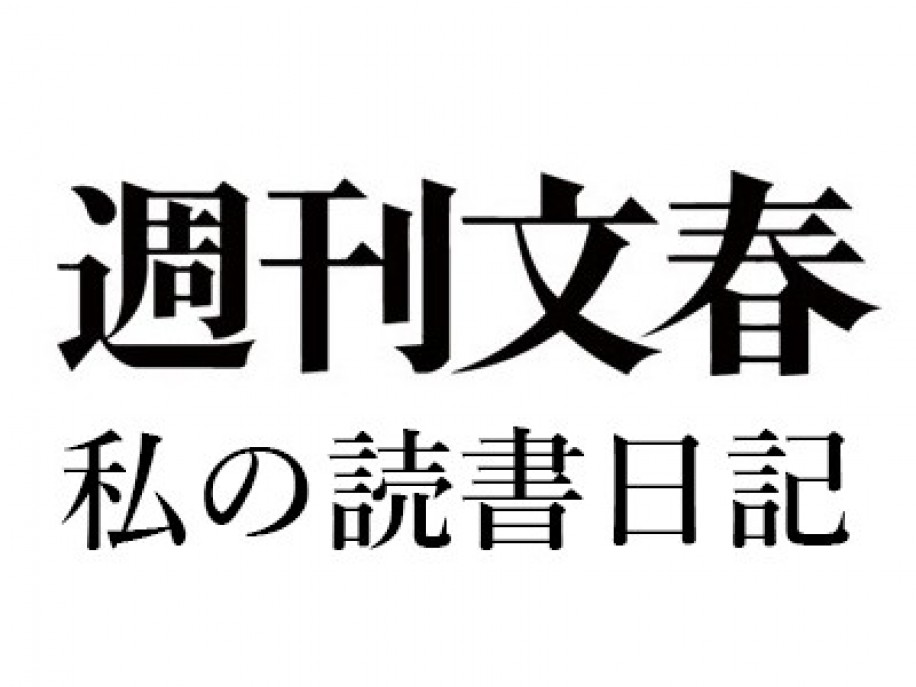書評
『宇宙飛行の父 ツィオルコフスキー: 人類が宇宙へ行くまで』(勉誠出版)
夢物語から具体的アイディアへ
正直のところ、今はSFにあまり関心はなく、映画でも、いわゆるスペース・オペラなど、全く観なくなったが、戦前海野十三の作品に魅せられた名残で、まだSFに関心を失っていなかった一九六〇年代初期、どういうわけかツィオルコフスキーの作品が幾つか集中的に日本に紹介されたこともあって、当時SFとして翻訳を読んだ覚えがある。その後も、SF作家ではなく、宇宙開発の先駆者としての彼の名前を、頭の隅にとどめることはできたが、その仕事の全容や、彼の生涯については、全く無頓着に過ぎたことが、本書を読んでまことに恥ずかしい。一九五七年、世界はひとつのニュースに震撼させられた。ソ連が、スプートニクと称する人工衛星を、人類史上初めて、地球圏外に送り出したことが報じられたからだ。それから四年、一九六一年にはボストーク計画の第一号が、ガガーリンを乗せて人類宇宙飛行に成功している。上に述べたツィオルコフスキー翻訳の小ブームは、まさしくこの出来事に符節を合わせたものだったはずだ。もっとも、以来六十年の今日、日本人十二人目の宇宙飛行士が宇宙ステーションに滞在中とは予想されなかったろう。
それらの宇宙計画の父と呼ばれるコンスタンチン・ツィオルコフスキー(一八五七―一九三五)は、コサックの血を引く父親とタタール系の母親との間に生まれた。生地は広大なロシアのほぼ中心あたりの僻村(へきそん)であった。父親は、コサックの血統と同時に貴族の血筋も受け継いでいた。妻は十回以上の出産に恵まれたが、育ったのは六人であったという。コンスタンチン生誕の頃のロシアは、当然ロマノフ王朝下、しかし、クリミア戦争の敗北直後で、農奴解放運動など、すでに激動期に入っていた。
比較的教養のある家庭に育ったコンスタンチンを、思いもかけぬ災厄が襲った。十歳の時だ。猩紅熱(しょうこうねつ)が彼の聴力を奪ったのである。左耳だけが、辛うじて微かな可聴性を示した。彼自身の告白によると、彼の華々しくもなく、孤独な生涯がここに決まったのだという。その後、手近なものを利用しながら、様々な工夫を凝らしてモノづくりに励んだという。
こうして著者は、ロシア語の原典をも掘り起こしながら、ツィオルコフスキーの生涯を丹念に描いていく。そこには面白い工夫もある。例えば著者が「紙上寄席」と名付けた部分で、本書に何回か登場する。要するに、落語仕立ての会話を構成してみせることで、読者の関心を繋ぎとめるという仕掛けだ。最初の寄席は、一八六五年ジュール・ヴェルヌが発表した『月世界へ行く』(邦訳は新装版、江口清訳、創元SF文庫、二〇〇五年)に関わる部分で登場する。コンスタンチンは、この書物(ロシア語訳)に大きな衝撃を受ける。それも、冒険フィクションとしてではなく、リアルな課題として受け止めたところに、彼のユニークさがあった。重力の束縛をどう切り抜けるか。具体的な課題が頭に浮かんだというから、まさしく夢物語を超えた受け取り方をされている。宇宙開発への基本的なきっかけが、ヴェルヌの作品であったことは確からしい。
もう一つの重要なエピソードは、アレクサンドル2世暗殺計画に参画して処刑された「テロリスト」の一人キバルチッチを巡るものである。この人物は、幼いころから数学の天才で、テロ運動の中で火薬の製造などにも研究と工夫をしたらしい。その推力で、人間を宇宙へ送るというアイディアが結びついたようだ。彼を中心とするテログループは、収監中、裁判の行方よりも、どうやったら宇宙空間に飛び出せるか、を議論しあったという、弁護士の証言が引用されている(キバルチッチの肖像は、今ウクライナの切手に採用されているという)。彼が残したロケットの推力などに関する計算書と説明手記とが、死後に残された(一八八一年)。ほとんど同じころ、正確には二年後に、ツィオルコフスキーも、似たような内容のアイディアを示すメモを残している。両者の間には関係はないから、これも歴史上しばしば起こる「同時発見」の事例と考えるべきだろうか。時代の先端が、その方向に熟しつつあったとも解釈できよう。
その後、宇宙開発への限りなき研究を続けながら、公的に最初の創造的仕事はむしろ空想科学小説『月の上で』の刊行という形をとった。一八九三年ツィオルコフスキー三十六歳のときのことである。その後も数年は、小説の執筆に精力を注ぎながら、宇宙船の設計に繋がる乗り物(例えば、当時ヨーロッパでブームになり始めていた飛行船など)の設計などに、具体的な成果を示しつつ、理論的な方面でも、次々に重要な文書を残すことになる。その詳細な経緯や、ソ連・ロシアが、その後彼の仕事をどのように評価したか、という点まで、丹念に追求した本書は、類書がないこと、また著者の対象への温かいまなざしが感じられることで、興趣溢れる読み物となった。
ALL REVIEWSをフォローする