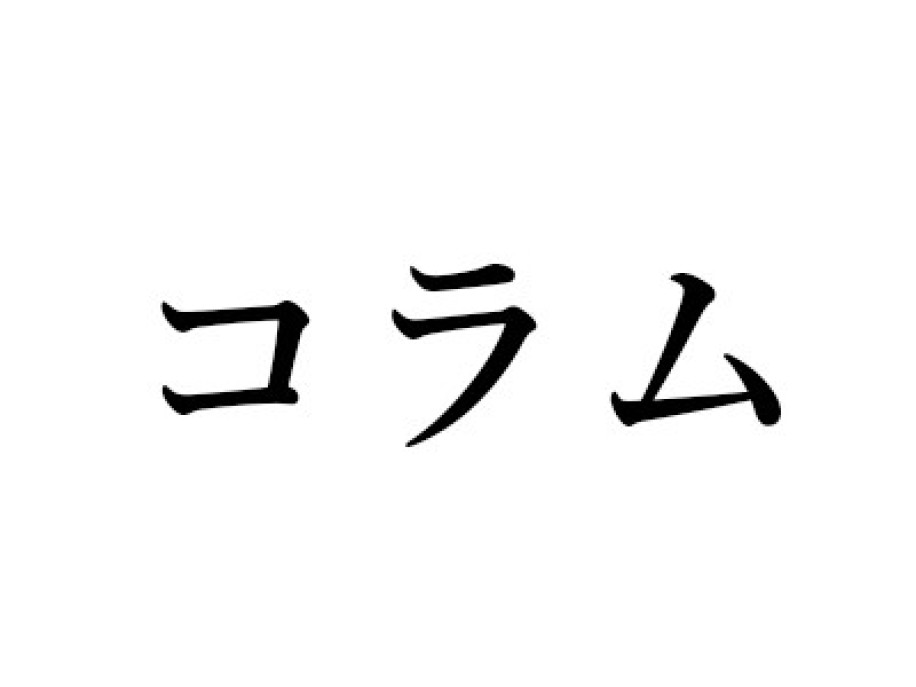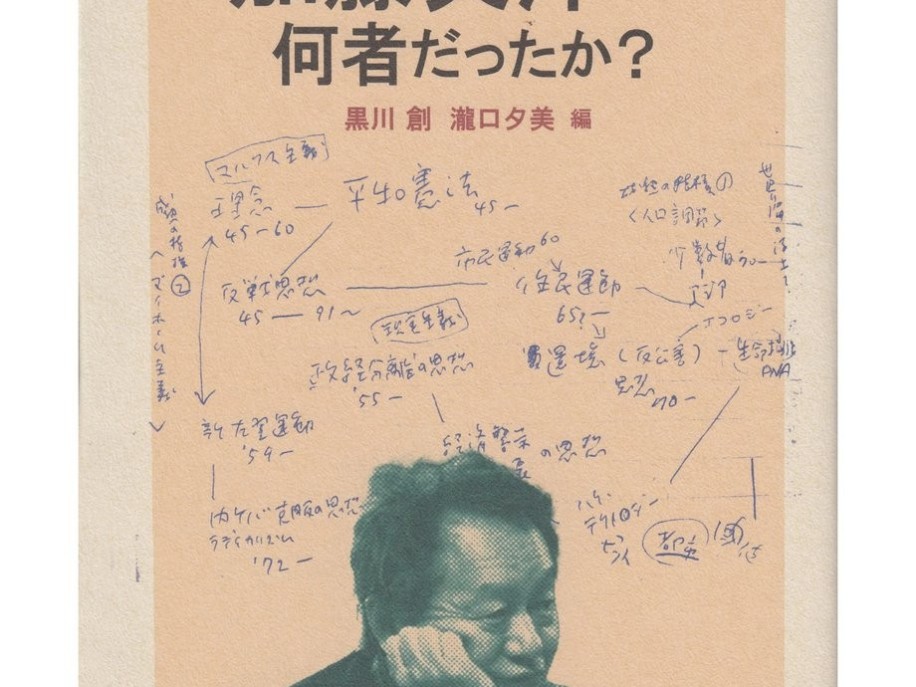書評
『〈序文〉の戦略 文学作品をめぐる攻防』(講談社)
レトリックの粋凝らされた読み物
本読みは、新しい書物を手にしたときどこから読み始めるか。「あとがき」から、という人は意外に多い。著者への敬意という意味では「まえがき」あるいは「序文」から、というのが当然だが、本書きのなかには、「あとがき」から読まれるのでは、という期待(?)で対応する人もいるようだ。いずれにせよ、読者を想定しない書き手はいない。古今の書物の序文に、著者は何を仕込んだか。この本は、そうした点に視座を据えた、珍しい研究成果である。とはいえ、文芸に冥い評子(だから本来この書評は、もっと適任の方でなさるべきだろうが)でも、読んだことのあるフランスのジェラール・ジュネットの「テクスト論」、より正確には「パラテクスト論」に、本書の出発点があることを著者は隠さない。「パラテクスト」というのは、書物の本文(テクスト)に「関して」、その周辺を飾る様々な付随的文章のことで、序文、あとがきなど直接本文に密着した「ペリ」と、本文に関してのインタヴュー記事、批判への弁論など外から繋がる文章群である「エピ」とがあるというのが、件の論の基礎である。
そこで書き手は、予想、予期できる読者の様々な反応や、場合によっては前作に対する弁明的な対応なども含めて、様々に予め工夫して、ペリテクストに仕込みをもうけることに腐心する。当然そこにはレトリックの粋が凝らされることにもなる。本書の著者は、その事情を驚くべき数の作品群を相手にして、分析し、幾つものパターンに分類し、鮮やかに明らかにしていく。驚くべき数と書いたが、大半が欧語の末尾の文献一覧には、ざっと数えても実に三百に近い、有名、無名の作品が並んでいるのだ。
物書きの端っこにいる評子の立場でも、身につまされそうなパターンも幾つかある。第9章は「剽窃」と題されているが、そこには、様々なレトリックを駆使して、自分の文章が「剽窃」の非難には当たらないことを主張する例が、幾つも挙げられている。例えば執筆の時期を強調する、原稿は早くに書かれたが、出版までに編集部で眠っている時間が長く、それで先行された、などなどの言い訳のオンパレードが、読むのも苦しい。
これは評子とは縁遠いが、第8章は「猥褻」のタイトルの下で、例えばさる原文を翻訳出版する際の「言い訳」がいくつも登場する。例えばエピクロス哲学の再現者として著名な、ルクレティウスの著作の性愛に関する文章の翻訳を刊行した詩人ドライデンの、ある意味では見事なエクスキューズなどが紹介されている。
第16章の表題は「不出来」。評子としても大いに関心をそそられるが、ここでも諸書様々である。健康状態の不全、推敲の為の時間の不足などなど、尤もらしい事例がいくつも並んでいる。
こうした諸例を著者はレトリック技術の分類、「ポリフォニー標識」における「確認」や「譲歩」、「メタ談話標識」の「ヘッジ」や「認知動詞」などを使って解明してくれており、それはそれで、言語論上の貢献として、評価される書物であろうが、純粋な読み物の読者としても、楽しい読後感を得られること必定、また多少とも書き手側に立つ人間にとっては、苦さとともに役立つ作品というべきだろう。
ALL REVIEWSをフォローする