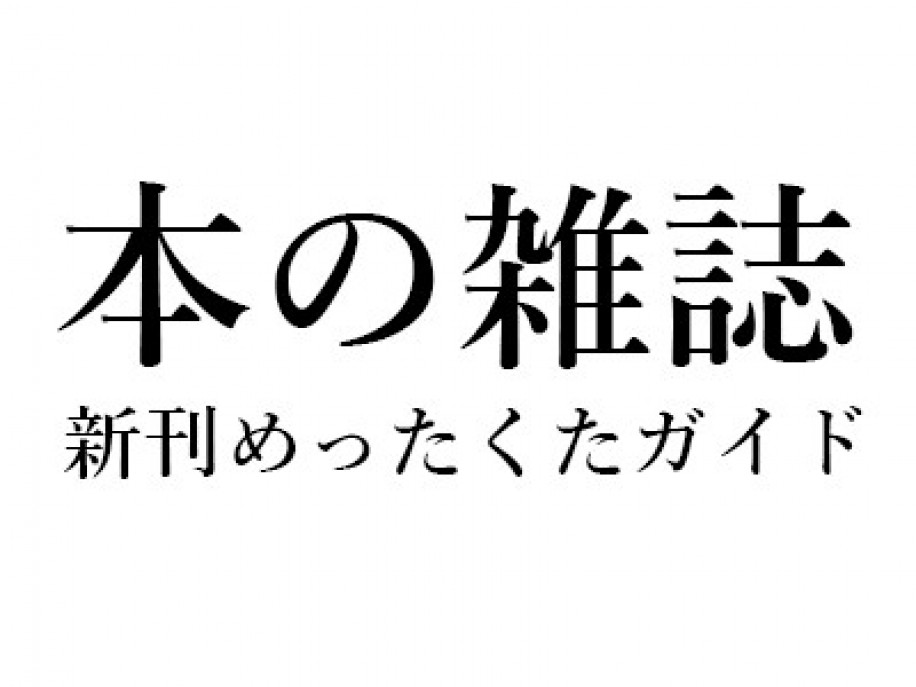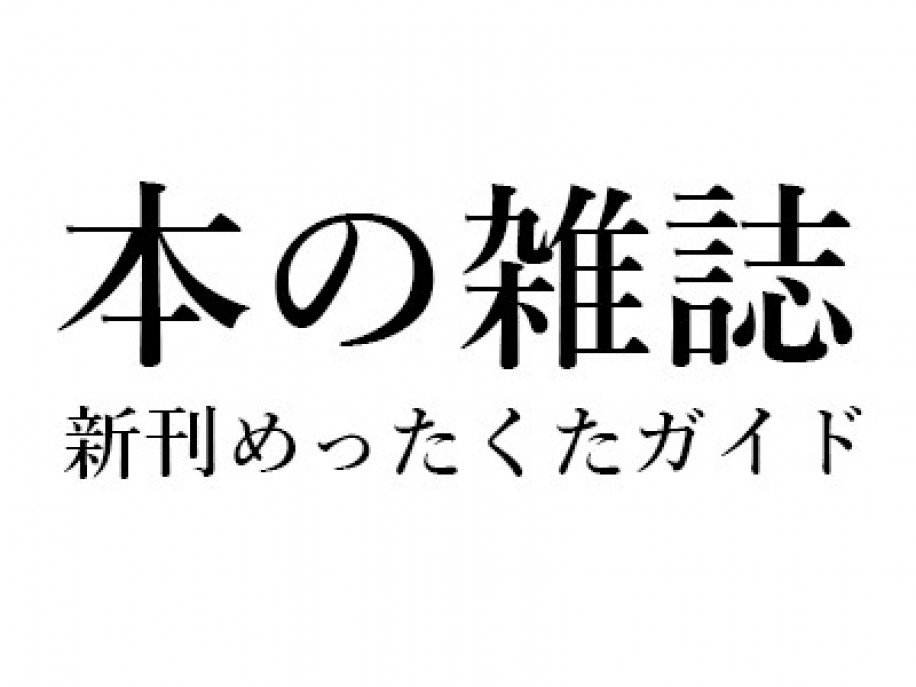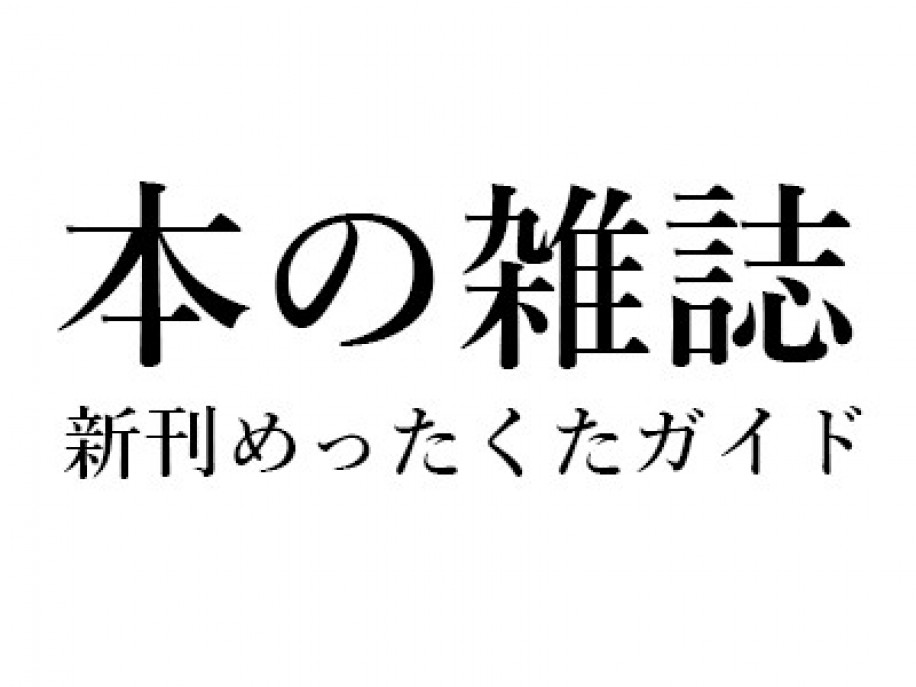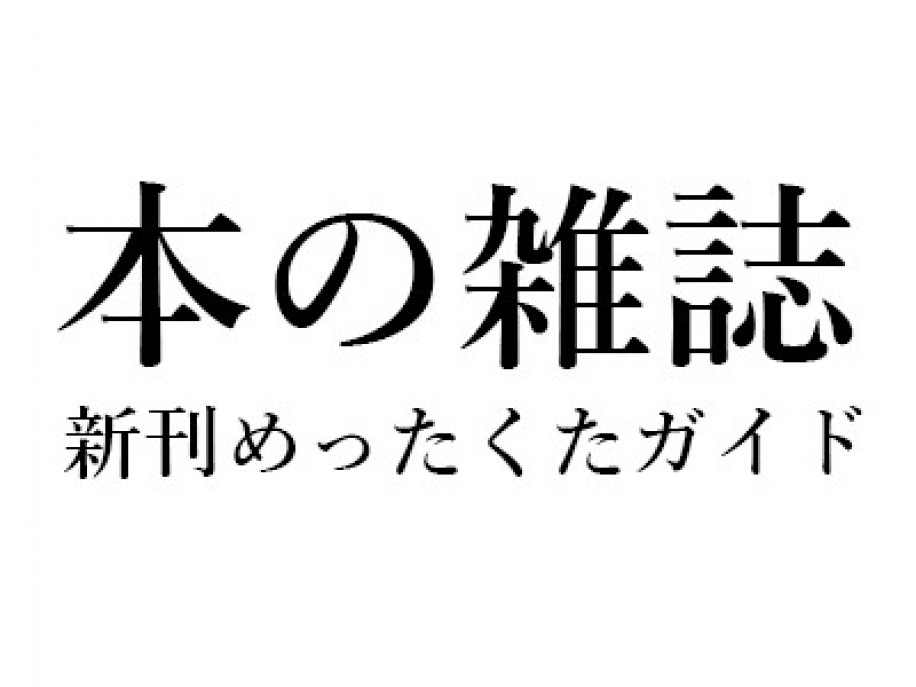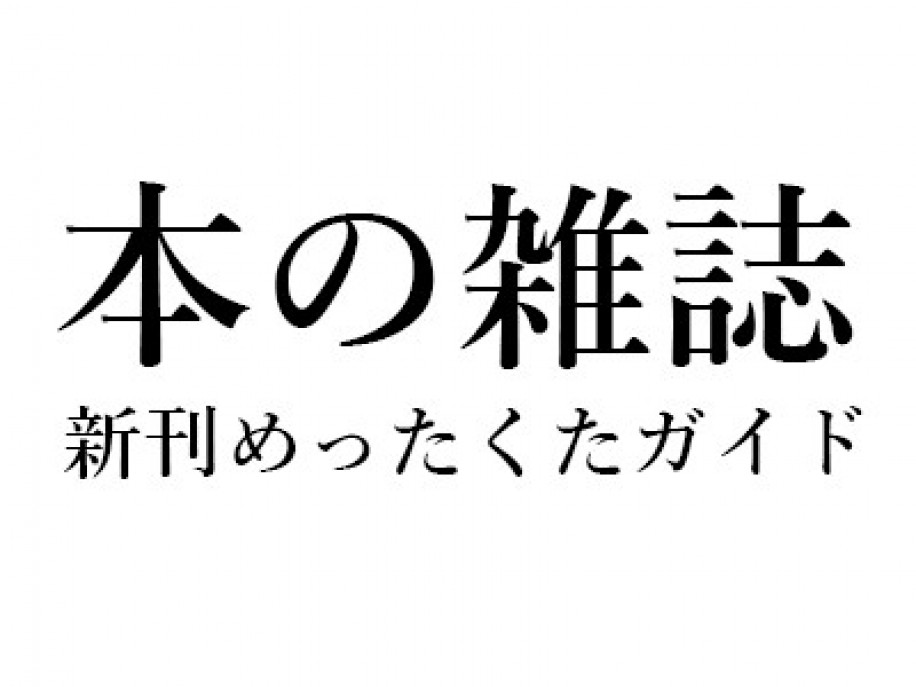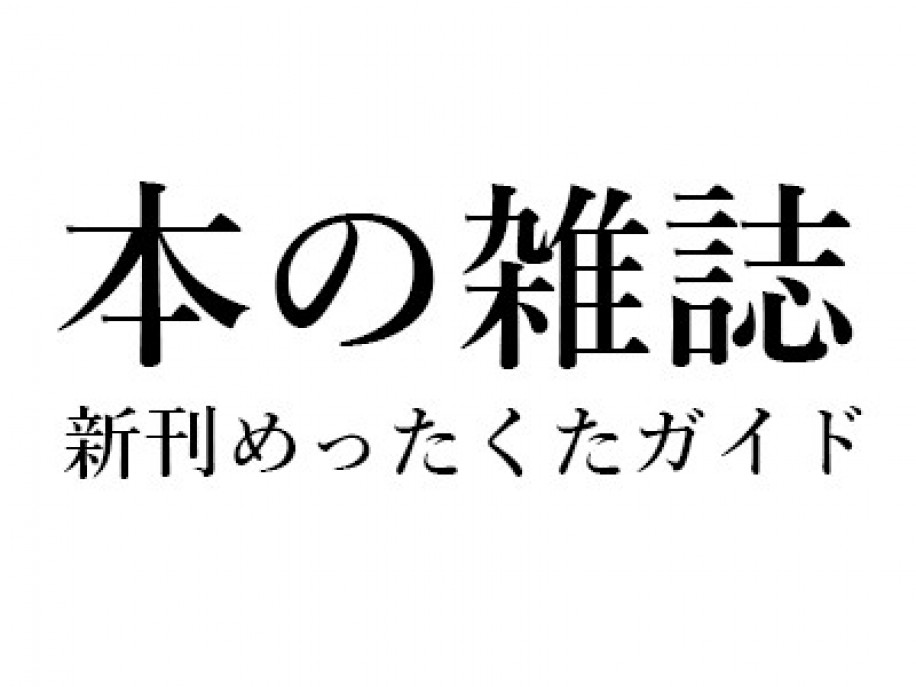文芸時評
大森望「新刊めったくたガイド」本の雑誌2001年6月号 秋山完『天象儀の星』( 朝日ソノラマ)他
ノスタルジーあふれる短篇集 秋山完『天象儀の星』の魅力
古人いわく、明けない夜はない。まあ、相手がSFだと必ずしもそうとは限らないが(小松左京「夜が明けたら」参照)それはまた別の話。あれからさらに二トンの古雑誌を処分し、トーハンの9号段ボール箱五十個に本とビデオを詰めて、ようやく自宅の改装工事が完了。そのかわり仕事場には箱が山積みだが、オレはもう疲れた。本なんか当分見たくもないので今月はここまで。というわけにもいかないので、日本の住宅事情にやさしい文庫本だけを特集する。全点、日本人作家の書き下ろし/オリジナルです。一番手は徳間デュアル文庫の新刊二冊。日本SFの新世紀特需は一段落した感じだが、デュアルの勢いはまだ止まらない。若木未生『オーラバスター・インテグラル 月光人魚』★★★は、なんと集英社コバルト文庫の人気シリーズ《ハイスクール・オーラバスター》からのスピンオフ。まさか斎伽忍(さいがしのぶ)が末弥純(すえみじゅん)のイラストで徳間から登場するとは。高校篇のコバルトに対してこっちは大学篇ですが、元シリーズを読んでいる必要はとくにない。書き下ろしの表題作は人魚幻想に新解釈を施した現代ホラーの収穫。全体にキャラクター小説的な要素は抑え気味で、コバルトとはひと味違うアダルトなムード。オーラバスターを知らない中年読者はこの機会にぜひ。
『鬼童来訪 起の章』★★★☆の一条理希も、同じくコバルト文庫(スーパーファンタジー)からの出張組。この新シリーズはあっちで書いてる現代〜近未来ものとは一八○度方向性が違い、鬼が跳梁跋扈する異世界を舞台にした伝奇時代劇。民話風に語られるプロローグの凄絶な結末から、ただごとではない気配を漂わせる。基本的にはダークなヒロイックファンタジーで、〝エルリックの鬼退治〟みたいなところもあるが、民話的な素材を大々的にとりいれつつ民俗学的な解釈に向かわないところが今は逆にユニークかも。
上遠野浩平『ブギーポップ・パラドックス ハートレス・レッド』(電撃文庫)★★★はシリーズ十冊目。〈傷物の赤〉こと九連内朱巳(くれないあけみ)と養母の関係は面白いが、霧間凪が活躍する後半は異様にストレート。あんまりわかりやすくなっちゃうとかっこよさが減退する気がするなあ。ところで、『パンドラ』の辻希美が今回再登場するんですが、今やこの名前は……。もちろん作者に責任はない。にしても、すでに違う顔がペーストされちゃってる人はどう読めばいいのか。
三鷹うい『背中にはしまもよう』(角川ティーンズルビー文庫)★★☆は、第1回角川ルビー小説賞ティーンズルビー部門優秀賞受賞のSFファンタジー。高校生の和樹は、「猫を人間にする驚異の技術」を開発した天才科学者の叔母から、浮世離れした美少女(?)の世話を押しつけられる。名前はトラ。しかしてその正体は、背中に縞模様のある雄猫……。中途半端に科学的説明が入ったり(質量保存の法則を守る必要はないと思う)、プロットが弱かったりの欠点はあるが、主要キャラ三人(二人と一匹?)は魅力的。ほとんどホモじゃないので男性読者も安心だ。
さて、今月の文庫特集日本SF篇のイチ押しは、秋山完の第一短篇集『天象儀の星』(ソノラマ文庫)★★★☆。巻末の書き下ろし「光響祭」を除く四篇は、第一長篇刊行以前に書かれた初期作品。史上最後のハヤカワ・SFコンテスト(第18回/一九九二年)で佳作入選しながらSFマガジンに載らなかった幻のデビュー作「ミューズの額縁」は、アキヤマ版《博物館惑星》の趣き。コンテストの選評で指摘された欠陥は修整されていないものの、オーソドックスな大ネタとそこから導かれる光景の美しさは今も貴重。唯一の新作「光響祭」はその姉妹篇的な性格で、やはりエキゾチシズムあふれるイメジャリーがすばらしい(アキヤマ未来史の重要キャラも登場する)。表題作と「まじりけのない光」の二本は(どちらも九四年休刊の故《グリフォン》誌初出)気恥ずかしくなるほどストレートなボーイミーツガールのロマンティックSF。こういう話を照れずに書けてしまうのが秋山完の才能だろう。近作の長篇だと、なくもがなのおやじギャグでそれを台無しにする傾向が強いんだけど、短篇ではギリギリ許容範囲の地口程度。著者のノスタルジックなSF世界に触れるには最適のショウケースだろう。
以下ホラー文庫の新刊を駆け足で。幸森軍也『あなたの待つ場所』(角川ホラー文庫)★★☆は『パワー・オフ』(井上夢人)系の人工生命SF長篇。新味に欠けるが可読性は高く、ウイルスパニック物の水準は一応クリア。五年前に出てればもっとよかった。瀬川ことび『夏合宿』(角川ホラー文庫)★★★は著者三冊目の短篇集。独特のユーモア感覚全開の「本と旅する彼女」がユニーク。小説でこんなオチが書ける人はなかなかいません。
残る三冊はハルキ・ホラー文庫から。怪作バカホラー『言霊』で話題を巣めた中原文夫の新作『霊厳村』★★☆は、昭和三十年代そのままの村に迷い込む定番の設定だが(夢見専門の一家を除き、村人は誰も夢を見ない)、村の日常描写が徹底してオフビート。人を蔑さげすんで睨む視線を競う大会とか、よくもまあ次々へんなことを考えるものである。『怪(あやし)の標本』★★★は、『幻日』(ブロンズ新社)で玄人筋から高く評価された福澤徹三の第二作品集。表題作は怪奇実話っぽいエピソードの聞き書きという趣向。インパクトでは『幻日』に一歩譲るが、やはり水準は高い。秋里光彦(高原英理の別名義)『闇の司』★★★は、「女殺油地獄」と「盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)」を下敷きに、欧米流サイコサスペンスをホラージャパネスク化する和魂洋才の一篇。完成された様式美の世界だが、撮影所の猟奇殺人から異界への転換が唐突で、やや分裂した印象を与えるのが惜しい。
最後に文庫以外のSFを一冊だけ。谷甲州&水樹和佳子の『果てなき蒼氓(そうぼう)』(早川書房)★★★は、光瀬龍&萩尾望都の『宇宙叙事詩』を思わせるイラストストーリー。風景のSFを志向する物語に挿画がキャラクターを補完し、前野昌弘の科学解説がそれをハードSFとしてまとめあげる。三位一体のバランスが絶妙だ。
【この文芸時評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする