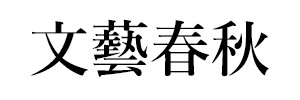対談・鼎談
『漢語と日本人』(みすず書房)
丸谷 ぼくも、お二人と同意見なんですが、意見が一致してばかりいては鼎談にならないので、少し問題点を指摘したいと思います。
中国の文学、語学関係の方には日本語を論ずるときの通弊があって、中国語および中国文学を基準にして日本語および日本文学を考えてしまう傾向が、あると思うんです。何となく専門家だという感じがするものだから、われわれは盲従してしまいがちなんですが、これはやはり、一つの参考意見として考えなければならないと思うんです。
まず第一に、中国語は強烈な歴史性をもって現在にまできている国語であって、その保守性がいわば荷厄介になっているという性格がある。ですから、新しい変革、時代による移りかわりというものをいくら強調したところで、その伝統はびくともしないという安心感があって、そのため新しい変革を無条件に肯定するという傾向が、中国文学関係の方々の日本語論にはあるような気がする。
第二に、これは言語学者一体に共通するものなのですけれども、言語というものに、新しい現象があれば、その現象は有無をいわせない絶対的なものだ、その現象がいいの悪いのと論ずるのは非科学的だという考え方が、どうも強いように思います。そうした現象を統御する基準とか、規範とかいうものを軽んじがちなような気がする。
第三に、中国文学、語学関係の方々は、美的規範が中国語にあるせいか、日本語そのものとしての美しさを軽んじるきらいがある。そのときに、拠り所は何になるかというと、言葉の便宜性、つまり、言語は一つの符牒にすぎないということになりがちだと思うんです。この著者の場合にしても、たいへん立派な、優れた学識の持ち主のようですけれども、こうした通弊を全面的に免かれているとはいい難いようですね。
山崎 たいへん上手におっしゃった(笑)。
丸谷 それと関連する一例をあげますと、
と書いていますが、これは、まったくの暴論です。佐藤春夫は、優れた文体がないといっているのですが、この人はそれを読みのがしている。
山崎 社会現象というものは、ある一つの必然的な方向に向かって流れているにしても、それを速めたり、多少遅くしたり、いろいろな抵抗体をもちこんだりするところに人間の自由、文化というものがあるわけです。
かつて言葉を新しくした人はどういうことをしたか。韓退之の例が出ていますが、この人はいろいろ新しい言葉をつくったかもしれないけれども、あえてそれを古文運動としてやったという意味合いは、やはり、感じてもらわなければいけない。
丸谷 古典主義だからこそ新しい文体が出てくるわけですね。
山崎 子規が短歌の改革をやろうとしたときに、紀貫之はつまらぬ歌詠みであって、わたしは『万葉』に帰るんだといってやったわけですね。そこに、人間の文化とか、言葉に関わる革新というものの一般的法則があるような気がするんです。
木村 おもしろいと思ったのは、挨拶の言葉が江戸時代に発達したと書かれてあるでしょう。これは非常に示唆的なことではないかと思うわけです。つまり、江戸時代になってはじめて、人間間のキメ細かな接触というものが、大衆的なレベルで出てきて、漢語もまさに潤滑油の意味で使わなければいけなくなった。いままでみたいな仏教用語とか、禅僧の言葉じゃなくてね。そこで文字どおり漢語の日本語化が大規模に進んだというふうに思うわけです。
著者は、江戸時代の人間のエネルギーの高まりが明治に入って様々な新しい漢語を生み出すもとになった、と書いていますけれども、たしかに江戸時代が、今日の日本文化とか、日本の社会の基礎の出発点をなしているんでしょうね。
山崎 中国は、漢字があるおかげで、非常に不思議な統一をつくっていると思うんです。実際にはまったく違った言葉を喋る十三の国家がありながら、漢字という視覚的な意味だけでお互いに通じ合っている。もしこれが表音文字で書かれている文化であれば、十三の国家は、ヨーロッパのように分裂していっただろうと思うんです。中国が、現在(ALL REVIEWS事務局注:本鼎談実施時期は1978年)、八億の国民を抱え、あれだけの強大な政府をもった一つの国家だというのは、文化的にいえば、一つの幻想だと思うんです。あの国は、統一するとすぐに乱れますが、乱れて当り前なんで、中国が「国家」だというのは、もともときわめて特殊な意味でいえることなんですね。
丸谷 ローマ帝国みたいなもので……。
山崎 ええ、ローマ帝国が国家だというんなら、中国も国家です。
丸谷 あの中華帝国が中華帝国として成立するためには、単に漢字が必要であるだけじゃなくて、文字による表現が決定的な重要性をもっていなきゃいけないと思うんです。だから北京の政府が最も抑圧すべきものは、ラジオとテレビだ。
山崎 このあいだ、鄧小平が日本に来たときに、美人のアナウンサーを連れてきましたね。あのアナウンサーのいうことをわたくしは全部わかったんです。北京語で喋りましたから。ところが鄧小平の言葉は一語もわからない。彼は完全な四川語で喋った。東北弁と鹿児島弁ではずいぶん違うかもしれないけれども、中国語の方言も相当なものですよ。
木村 しかし、漢字でわかり合えるということは、共通の意味をもたせ合っているということですよ。やはり、中国人としての文化的な統一性があるんです。つまり、同じ文化を保ちたい、十三の国にバラバラにしたくないという共通の気持があったからだと、わたしは思いますね。
山崎 統一国家というものが現にあることを何も否定してるわけではないんです。いわば中国そのものの内部につねに乱れる要素があるでしょう。その不思議さをいっているわけです。あれは、普通の意味のネーション国家ではなく、非常に変ったものだ、ということをいいたいんです。
木村 結局、中国は政治的統一体じゃなくて、文化的統一体なんですよ。
山崎 いや、文化的統一といっても、かなりの二重構造をもった統一ですよ。
木村 それはそうですね。ギリシャ人みたいに、アテナイ、スパルタとそれぞれ違うんだけど、外に向かっては自分たちの文化に誇りをもっている。その点ではまとまりがある。そういうことですね。
山崎 それはそうね。もう一言だけいわせていただくと、この著者は日本人が表現ににじみをもたせたり、曖昧ないい回しをしたりするということを、非常に強く感じておられるようです。
多分、中国語はにじみのない明快な言葉なのでしょうが、しかしヨーロッパ語というのもにじみのある言葉なんですね。英語にも表現をやわらげる動詞はたくさんあるし、仮定法の過去の用法などもそういう意味に使われています。
中国語というのは、大体、テンスのない言葉なんですね。ある意味でいえば、これはいちばん率直、端的な言葉なのであって、この筆者は日本語の特色を指摘しておられるようだけれども、逆に、中国語の特色を指摘しておられるんだという感じがします。
木村 すると、中国語は国連用語としてはいいわけだ。感情抜きで、ピシャピシャッと要点だけいうんだから(笑)。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
中国の文学、語学関係の方には日本語を論ずるときの通弊があって、中国語および中国文学を基準にして日本語および日本文学を考えてしまう傾向が、あると思うんです。何となく専門家だという感じがするものだから、われわれは盲従してしまいがちなんですが、これはやはり、一つの参考意見として考えなければならないと思うんです。
まず第一に、中国語は強烈な歴史性をもって現在にまできている国語であって、その保守性がいわば荷厄介になっているという性格がある。ですから、新しい変革、時代による移りかわりというものをいくら強調したところで、その伝統はびくともしないという安心感があって、そのため新しい変革を無条件に肯定するという傾向が、中国文学関係の方々の日本語論にはあるような気がする。
第二に、これは言語学者一体に共通するものなのですけれども、言語というものに、新しい現象があれば、その現象は有無をいわせない絶対的なものだ、その現象がいいの悪いのと論ずるのは非科学的だという考え方が、どうも強いように思います。そうした現象を統御する基準とか、規範とかいうものを軽んじがちなような気がする。
第三に、中国文学、語学関係の方々は、美的規範が中国語にあるせいか、日本語そのものとしての美しさを軽んじるきらいがある。そのときに、拠り所は何になるかというと、言葉の便宜性、つまり、言語は一つの符牒にすぎないということになりがちだと思うんです。この著者の場合にしても、たいへん立派な、優れた学識の持ち主のようですけれども、こうした通弊を全面的に免かれているとはいい難いようですね。
山崎 たいへん上手におっしゃった(笑)。
丸谷 それと関連する一例をあげますと、
佐藤春夫がかつて芥川賞選考の席で、このごろの若い作家には文体がないといって慨嘆したことがあるが、それは佐藤春夫が考えるような同時代的な文脈のリズムがないということでしかない。文体がないといわれたときには、すでに、別の文体が生まれ育っている証拠である。
と書いていますが、これは、まったくの暴論です。佐藤春夫は、優れた文体がないといっているのですが、この人はそれを読みのがしている。
山崎 社会現象というものは、ある一つの必然的な方向に向かって流れているにしても、それを速めたり、多少遅くしたり、いろいろな抵抗体をもちこんだりするところに人間の自由、文化というものがあるわけです。
かつて言葉を新しくした人はどういうことをしたか。韓退之の例が出ていますが、この人はいろいろ新しい言葉をつくったかもしれないけれども、あえてそれを古文運動としてやったという意味合いは、やはり、感じてもらわなければいけない。
丸谷 古典主義だからこそ新しい文体が出てくるわけですね。
山崎 子規が短歌の改革をやろうとしたときに、紀貫之はつまらぬ歌詠みであって、わたしは『万葉』に帰るんだといってやったわけですね。そこに、人間の文化とか、言葉に関わる革新というものの一般的法則があるような気がするんです。
木村 おもしろいと思ったのは、挨拶の言葉が江戸時代に発達したと書かれてあるでしょう。これは非常に示唆的なことではないかと思うわけです。つまり、江戸時代になってはじめて、人間間のキメ細かな接触というものが、大衆的なレベルで出てきて、漢語もまさに潤滑油の意味で使わなければいけなくなった。いままでみたいな仏教用語とか、禅僧の言葉じゃなくてね。そこで文字どおり漢語の日本語化が大規模に進んだというふうに思うわけです。
著者は、江戸時代の人間のエネルギーの高まりが明治に入って様々な新しい漢語を生み出すもとになった、と書いていますけれども、たしかに江戸時代が、今日の日本文化とか、日本の社会の基礎の出発点をなしているんでしょうね。
山崎 中国は、漢字があるおかげで、非常に不思議な統一をつくっていると思うんです。実際にはまったく違った言葉を喋る十三の国家がありながら、漢字という視覚的な意味だけでお互いに通じ合っている。もしこれが表音文字で書かれている文化であれば、十三の国家は、ヨーロッパのように分裂していっただろうと思うんです。中国が、現在(ALL REVIEWS事務局注:本鼎談実施時期は1978年)、八億の国民を抱え、あれだけの強大な政府をもった一つの国家だというのは、文化的にいえば、一つの幻想だと思うんです。あの国は、統一するとすぐに乱れますが、乱れて当り前なんで、中国が「国家」だというのは、もともときわめて特殊な意味でいえることなんですね。
丸谷 ローマ帝国みたいなもので……。
山崎 ええ、ローマ帝国が国家だというんなら、中国も国家です。
丸谷 あの中華帝国が中華帝国として成立するためには、単に漢字が必要であるだけじゃなくて、文字による表現が決定的な重要性をもっていなきゃいけないと思うんです。だから北京の政府が最も抑圧すべきものは、ラジオとテレビだ。
山崎 このあいだ、鄧小平が日本に来たときに、美人のアナウンサーを連れてきましたね。あのアナウンサーのいうことをわたくしは全部わかったんです。北京語で喋りましたから。ところが鄧小平の言葉は一語もわからない。彼は完全な四川語で喋った。東北弁と鹿児島弁ではずいぶん違うかもしれないけれども、中国語の方言も相当なものですよ。
木村 しかし、漢字でわかり合えるということは、共通の意味をもたせ合っているということですよ。やはり、中国人としての文化的な統一性があるんです。つまり、同じ文化を保ちたい、十三の国にバラバラにしたくないという共通の気持があったからだと、わたしは思いますね。
山崎 統一国家というものが現にあることを何も否定してるわけではないんです。いわば中国そのものの内部につねに乱れる要素があるでしょう。その不思議さをいっているわけです。あれは、普通の意味のネーション国家ではなく、非常に変ったものだ、ということをいいたいんです。
木村 結局、中国は政治的統一体じゃなくて、文化的統一体なんですよ。
山崎 いや、文化的統一といっても、かなりの二重構造をもった統一ですよ。
木村 それはそうですね。ギリシャ人みたいに、アテナイ、スパルタとそれぞれ違うんだけど、外に向かっては自分たちの文化に誇りをもっている。その点ではまとまりがある。そういうことですね。
山崎 それはそうね。もう一言だけいわせていただくと、この著者は日本人が表現ににじみをもたせたり、曖昧ないい回しをしたりするということを、非常に強く感じておられるようです。
多分、中国語はにじみのない明快な言葉なのでしょうが、しかしヨーロッパ語というのもにじみのある言葉なんですね。英語にも表現をやわらげる動詞はたくさんあるし、仮定法の過去の用法などもそういう意味に使われています。
中国語というのは、大体、テンスのない言葉なんですね。ある意味でいえば、これはいちばん率直、端的な言葉なのであって、この筆者は日本語の特色を指摘しておられるようだけれども、逆に、中国語の特色を指摘しておられるんだという感じがします。
木村 すると、中国語は国連用語としてはいいわけだ。感情抜きで、ピシャピシャッと要点だけいうんだから(笑)。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする