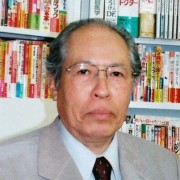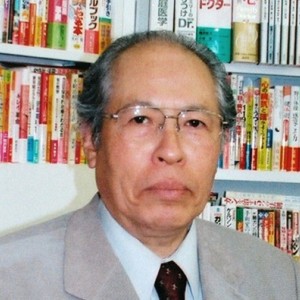コラム
ヴァン・ゴッホ『ゴッホの手紙』(岩波書店)、小林秀雄『近代絵画』(新潮社)、高橋克彦『浮世絵鑑賞事典』(KADOKAWA)
息の長い近代絵画の入門書
「絵というものはうんと費用のかかるものなのに、おそらくこの仕事にたずさわるものはひどく貧しい人たちなのでということに気がつきはじめた僕は、そのためにときどき悲しい気持ちになる」とは、『ゴッホの手紙』(硲伊之助訳、岩波文庫全三冊)の一節。一般に画家の生前の処遇と死後のそれとの落差を象徴する皮肉な例として、よく引用される文章である。カネ余り現象が惹起した悪名高い絵画投機ブームも、一般の美術への関心をも高めたと思えば怪我の功名というべきだろうが、文庫本の世界ではひところ盛んだった小型の美術全集もいまは絶版となっているようで、今後の企画待ちというところ。近代絵画に関する書目といえば、まず一九五五年いらい版を重ねている前記ゴッホによる親友ベルナールと弟テオドル宛の書簡集と、もう一冊は一九六八年に文庫入りした小林秀雄の『近代絵画』(新潮文庫)が古参の両横綱。いずれも三十刷以上も版を重ねている。
小林の絵画論はすでに古典だが、たとえばピカソの項で近代絵画成立の要件にふれ、生命とは自我のことであるがゆえに「生きるとは絵を描くことだ。以来、絵画は文化を装飾することをやめた」と喝破したあたりなど、文化の装飾となりさがった現代の絵画趣味を原理的に批判したものといえよう。
スイスの美術史家ゲオルク・シュミットの『近代絵画の見かた』(教養文庫)はドーミエ、シスレイからシャガールまで十人の画家を造形的要素から位置づけたもので、三十年以上も前の原著だが、入門書としてはいまだに生命を失っていない。
このほか近代絵画の概説書としては、図版の豊富な富永惣一『近代絵画』(保育社カラーブックス)がある。ギリシャ・ローマ時代から浮世絵にいたるヌード美術を通観した山川清・沢野井信夫『名画に見る世界の裸婦』(同)も、異色の美術史といえよう。
日本美術史に関する文庫本は、ほとんど浮世絵に限られているが、入門書としては『写楽殺人事件』の高橋克彦が作家としてデビューする以前に上梓した『浮世絵鑑賞事典』(講談社文庫のち角川ソフィア文庫)が最も充実している。師宣から清親にいたる五十九人の浮世絵師の略伝、小事典、参考文献リストなどによって構成されており、値段も手ごろ。菊地貞夫『浮世絵』(保育社カラーブックス)も便利なハンドブックとなろう。
画家みずからの文章としてはエッセイストとして鳴らした『鏑木清方随筆集』(岩波文庫)がある。昭和戦前から戦後にかけての、東京周辺の四季を描いた短い文章を集めたものだが、まだ都市の片隅に豊かに息づいていた自然の表情を捉えてみごとである。同じ作者による自伝『こしかたの記』(中公文庫)は明治文化史として必読だが、惜しくも品切れ。
近代洋画界の革新を目ざした岸田劉生は多くの文章や日記を残しているが、『美の本体』(講談社学術文庫)はその芸術観を端的に示したもの。後半には雑感集と題して創作についての率直な感想が収められている。その愛娘岸田麗子の『父 岸田劉生』(中公文庫)は強烈な個性の持ち主であった劉生の人間像とその苦闘の人生が、印象深いエピソードとともに語られている。とくに晩年、苛酷な状況の中で心身の健康のバランスを崩していく過程がいたましい。
最後に絵をじっさいに描いてみようという向きに、実作のガイドが出ているが、ここでは中村善策『風景画入門』(保育社カラーブックス)、西山英雄『日本画入門』(同)の二点をあげておこう。いずれも具体例を豊富に掲げ、材料、用具、風景画材についてもふれた親切な内容である。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア