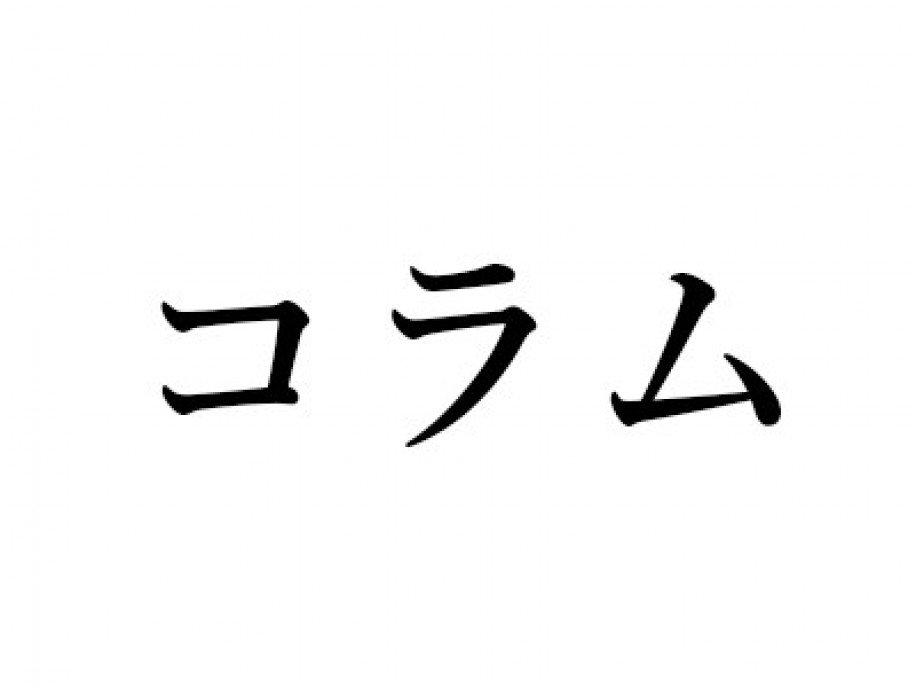書評
『地獄の季節』(岩波書店)
でっち上げられた衰耗
「不巧の名作」と呼ばれるような古典的な文学作品であっても、それなりに流行(はや)り廃りはあるもので、例えばドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』などは、一頃に比べると、もう随分と読まれなくなってしまっているのではあるまいか?私が小林秀雄訳の『地獄の季節』について考える時、何時も頭を過(よ)ぎるのはそのことで、この作品が或る世代までの文学青年達に及ぼした影響は絶大だったと思うが、それが及ぶ範囲はかなりはっきりと限定されていて、私の世代になると、そもそもこれを読んでいる人自体が極めて珍しかったし、読んでいても、何処かバカにされるような風潮があった。
その理由は、小林秀雄という人の存在感の問題に拘わっているのであろうが、それ以上に、「誤訳が多い」という例の悪評のせいでもあろう。しかし、私はそれを少し単純だと感じる。誤訳であろうと何であろうと、ともかくも、小林秀雄訳の『地獄の季節』は、この国の文学史の中に出現し、しかもその圧倒するような魅力によって一時代の人間の心を完全に捉えていたのである。その「書かれた物」としての価値は、翻訳が正確かどうかという問題とはまた違う段の話である。
さて、私自身は、明らかにそうした、この作品の魔力の圏外にいた世代であるが、今振り返ってみても、これが私の十代の頃に投げ掛けてきた問いの意味は、失われていないように思われる。そしてそれは、やはり小林訳の力に負うところが大きかったのではあるまいか?
当時の私が、この作品の何にそれほど惹きつけられていたかは明確である。私が殊に注目したのは、「錯乱 Ⅱ」の中の「行為は生活ではない、一種の力を、言わば、ある衰耗をでっち上げる方法なのだ。」という一節であった。これは、霊と肉、精神と身体、認識と行動、死と生、といった西洋的な二元論の呪縛にすっかり捕らわれていた少年の頃の私を根底から揺るがす驚くべき断定だった。「行為」が即ち「生」を意味しないとは、一体どういうことなのであろうか?
これをもし、ランボーが、臨終の床で呟いたというのであれば、よく分かる。生活を求め、詩を捨て、彼はアフリカに赴いた。しかし、彼のそうした「行為」は、結局、真に「生活」と呼ぶに足るものを齎(もたら)してはくれなかった。その苦々しい悔恨が、今際(いまわ)の際に吐露されたというのであれば、なるほど、と納得することが出来る。しかし実際には、この言葉は、『地獄の季節』の中に、つまり、彼がアフリカに行く前に書かれているのである。ランボーは、ヴェルレーヌとの放蕩生活の中で、「行為」というものが、結局は「衰耗をでっち上げる方法」でしかないことを骨身に染みて感じていた筈である。にも拘わらず、彼は、比類なき芸術の天稟(てんぴん)を捨て、敢えてその「行為」を選び、予言通り「衰耗をでっち上げ」て、死んでいった。或いは、死なねばならなかった。それが彼の「生きる」ことであった。彼の生涯の迫力は、まさしくその一点にこそ存している。
こうしたランボーの理解は、私にとっては、バイロンから三島由紀夫に至るまでのロマン主義者達の生の失敗と極めて密接な関連を有していた。前述のような二元論の矛盾の狭間で苦しみ喘いだ後、彼らが遂には筆を捨て、行動へと身を投じ、破滅しなければならなかったということ。その宿命の克服は、今なお古びない大きな問題であり、私にとっては、恐らくは生涯関わり続けるべき文学的主題となるであろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする