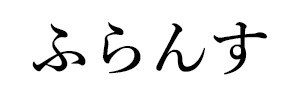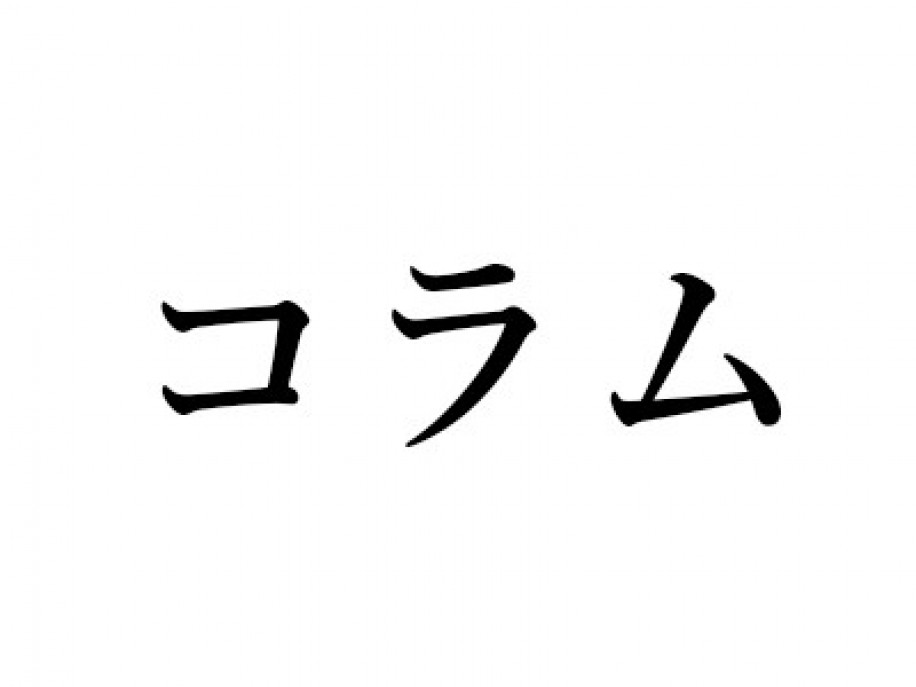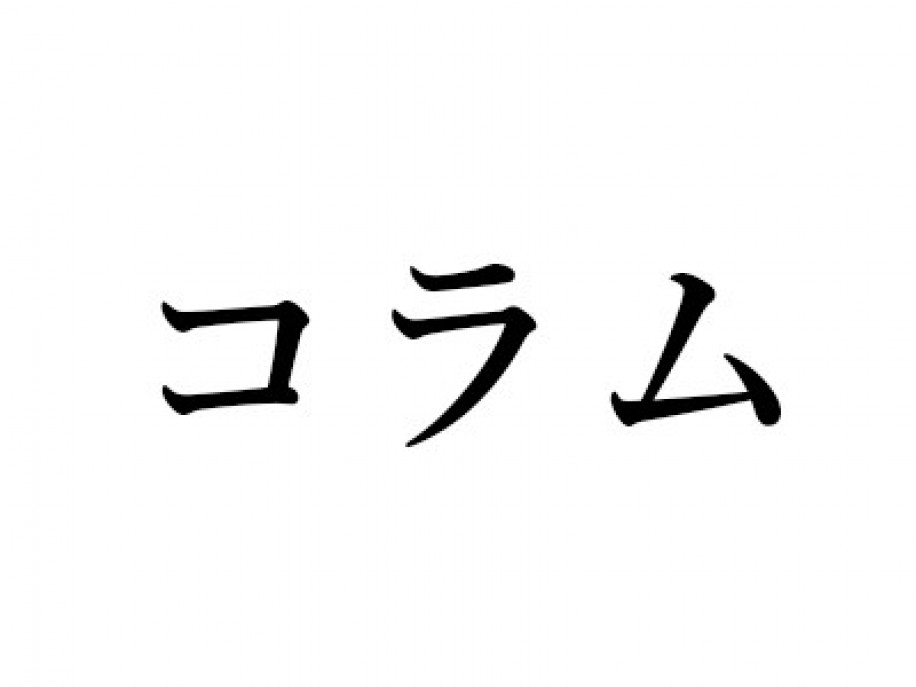書評
『フランス名詩選』(岩波書店)
君を名ざすために
日本近代詩に多大な影響を与え、ひときわ甘美な夢と憧憬をあおった言葉の群れが、腰のくだけた日常語のなかで行き場をなくしている現在、『フランス名詩選』ほどに古風で、かつ新鮮な響きを持ちうる書名はないだろう。二十世紀初頭には日本文学の富に組み込まれ、数十年のあいだ輝かしい指標となってきたボードレールやマラルメやランボーの訳詩集すらいまや平均的な書店から姿を消しており、ましてアンソロジーともなれば、講談社文芸文庫で復刊された堀口大學の『月下の一群』を除いて安価に入手できる版はなく、しかもこの大正期の月明かりに集っているのは、象徴主義からモデルニスムの詩人に限られているというありさまなのだ。数世紀におよぶフランス詩の流れを視野に入れ、読者の便をも考慮した手軽な詞華集など、望むべくもない状態がつづいていたのである。そこへとつぜんの朗報である。十四世紀から二十世紀半ばまでの詩人六十名、計九十九篇の作品を収める壮大な詞華集が、これ以上ない三人の訳者を得て、対訳文庫版でもたらされたのだ。閨秀詩人クリスチーヌ・ド・ピザン――石川淳の読者は歓喜するだろう――を皮切りに、シャルル・ドルレアン、フランソワ・ヴィヨン、クレマン・マロ、モーリス・セーヴ、ロンサール、ルイーズ・ラベ、マレルブなど、原語でもなかなか読む機会のない詩人が一望され、時代を飛んでシェニエ、デボルド=ヴァルモール、ヴィニー、ユゴー、ミュッセ、ネルヴァル、ゴーチエ、バンヴィル、そして先の大御所はもちろん、シャルル・クロ、コルビエール、グールモン、サン=ポル・ルー、トゥーレ、ミロシュ、ポッジ、ブルトン、エリュアール、セガレン、ジャリまでひと息に見渡されたあと、最後はタルデューで締めくくられる。紙面の制約上、十七、十八世紀の詩がかなり削除されているのは残念だが、原詩と訳詞を同時に味読できる快楽のまえでは瑕瑾(かきん)にすらならない。
携行可能なアンソロジーなのだから、好きな詩人の、好きな詩の載っている頁を開けばいい。しかし冒頭を飾るクリスチーヌ・ド・ピザンの、「私はひとりひとりのままでいたい、/私をひとりやさしいあの人は残して行った」という一行から本書を通読してみると、フランス詩がどれほど「愛」に取り憑かれてきたか、そしてそれらおびただしい数の「愛」が、どれほど物質としての言語に支えられた、生々しくも優い幻であったかを理解できるだろう。編者の表現をかりれば、ここにあるのは徹底的な言語操作に耕された「知の土壌」であり、いにしえの美女たちも、不在のデリーも、湖上の恋人も、イシスの女神も、髪の森に謎を隠したシモーヌも、忍び寄る足音と化した彼女も、エンジェル・フイッシュの腋の下を持つ女も、すべての愛は、彫琢された言語によって、虚空に身を持してきたのである。詩人たちが生まれてきたのは、幻の「君を名ざすためだった」(エリュアール)のであり、「愛」はまさしく言葉そのものに捧げられてきたのだ。要するに、「自由」がひとつの概念ではなくリベルテという名の女性に変貌する瞬間の昂揚を、私たちはフランス詩と呼べばいいのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする