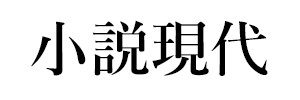コラム
村田 喜代子『名文を書かない文章講座』(朝日新聞出版)、辻 邦生『言葉の箱―小説を書くということ―』(中央公論新社)、無着 成恭『山びこ学校』(岩波書店) ほか
書きたいひとへ
文章がうまくなるとはどういうことだろうと、ときどきぼんやり考える。ものを書くことで生計を立てているので、プロのもの書きに分類される私だが、誰でもはじめはアマチュアだったはずで、アマ→プロの境はどこにあったのか、自分はいつ通過したのか。専門教育を受けてなる職業ではないので、違いがわかりにくい。
そう、知り合いの編集者に話したところ、
「いや、やっぱりプロとアマの差は歴然だよ」
この本のカルチャーセンターのエッセイ講座に関する文章でも、登場してもらった人であるが、彼は会社の関係でエッセイの教室に、「先生」をしにいくことがある。そのたびに「あー」と吐息が出るほど、つくづく感じることが二つ。なんていい題材を持っているのだろう。その出し方がなんてへたなんだろう、と。
「ちょっとこうすればいいのに、もったいないな、と思うよ」
すると、アマ→プロに移行するプロセスのひとつに、「ちょっとこうすれば」のアドバイスに聞く耳を持つことが、挙げられようか。
私がはじめの頃よく直され、今でもときどき指摘されるのは、「ここのところ、意味が取りにくい」「通りが悪い」ということだ。
「通り」とは何ぞやと問われると、説明は難しいが、自分なりに点検しながら書くようになった。
例えばこの稿の出だしとして、頭に浮かんだのは次の文。
ときどきぼんやり思うのは、文章がうまくなるとはどういうことか、ということだ。
これはとても素直だけれど、いざ字として並べると「いうこと」が近接して続き、こなれていない感がある。
二つめの「こと」を「点」とし、重複を避ける方法もあるが、「点」という言葉の指示性と「ぼんやり」の語感とが合わない。
「点」ではなく「問い」とすれば広がりが出る。が、「問い」を「思う」では、目的語と動詞の組み合わせとして変で、「思う」の方をいじらなければならなくなる。
ときどきぼんやり思っている。文章がうまくなるとは、どういうことだろう。
これだと「こと」は一つですむ。が、のっけから倒置法的に入るのは、どんなもんか。
あれこれ考え、冒頭の、
文章がうまくなるとはどういうことだろうと、ときどきぼんやり考える。
の一文に落ち着いたが、ベストかどうかはわからない。私にとって文章を書くのは、自分の気持ちにしっくりきて、なおかつ、字づらとして、また論理的にも整合性が保てるという条件とも合う言葉の並べ方を、やっとこすっとこ探り当てていく作業といえる。
そのときに、編集者から、
「こういうふうにしても、同じことが言えるんじゃない?」
と、まったく別の案を示され、
「あーっ、そうだそうだ。さんざん考えて、なんで気づかなかったんだろう。私の脳はスカスカでした」
ときれいに決着がつくことがあるから、第三者の意見は貴重だ。「文は人なり」とはたしかだろうが、教えられることで、「文」に「人」がよりよく表れるようになる。
さきにも挙げた、村田喜代子著『名文を書かない文章講座』(葦書房)はカルチャーセンターで話したことがもとになっている。語彙が多ければ、比喩を豊かに使いこなせたら……といった受講者の「名文」への思い込みを、次々とくつがえす。
実作にいそしむ著者だけあり、注意点を語る口調も、引いてくる例も、生きがよく、刺激的。自らのエッセイを題材に、地の文だけ、描写だけ、セリフだけで書いたらそれぞれどうなるか、三通りに書き分けて効果を比べるあたりなんぞ、芸を感じてしまった。
【文庫】 【単行本】
辻邦生著『言葉の箱―小説を書くということ―』(メタローグ)は、創作学校での講座をまとめたもの。文章作法にはふれず、小説とは何か、どんなところから生まれてくるかを語っている。いわば創作の源泉に分け入るわけで、人間の懊悩といった暗い話になるのではと思ったら、逆で、澄明な高揚感のようなものがみなぎって、みずみずしくさえあった。
「好きなもの」をつかんでいることのだいじさを、くり返し著者は説く。「何か好きだということは、生きる意味をそれが与えてくれているということです」。すぐれた小説家は必ず、「生命のシンボル」になるものを持っている。コンラッドは海、サン=テグジュペリは空、ヘッセなら雲……。
エッセイの場合、著者の言う小説のように「架空の事柄を言葉によって構築」する作業ではないので、同じには語れないが、そうした陽性の力のようなものが、自分をひっぱっていってくれるのは、わかる気がする。私でいえば、そこそこの好奇心とか、ものごとを悪くは受け止めない性格とか、全人的なものがうまく発動しているときに、文章もすいすい進むと感じる。村田喜代子さんの言葉を借りれば、「書く行為は何より心の運動、精神活動」「自分の内に隠れている一番自分らしい、自然でのびのびした良い姿を掘り出す作業かもしれない」。
【文庫本】 【単行本】
作文指導で有名なのは、無着成恭の『山びこ学校』(岩波文庫)だろう。山形県のとある村の中学生が、青年教師無着のもとで綴った文集で、昭和二十六年に出版されるやベストセラーに。貧困と、それのよってきたる社会のしくみに目を据えた、生徒たちの文章は、戦後民主主義教育の理想として絶賛された。
佐野眞一著『遠い「山びこ」』(文春文庫)は、成立の背景と、教え子たちのその後を追ったノンフィクションだ。マスコミにもてはやされたり、左翼のプロパガンダに利用されかかったりしながらも、農村の崩壊と、高度経済成長の裏側に消えていく他なかった過程を、あぶり出す。
「山びこ学校」出版からわずか三十年後、同じ中学で同書をテキストに用いた教師によれば、生徒たちはまず、使われている方言がわからなかったという。村が抱える問題というテーマで作文を書かせても、「問題」なる言葉の意味がつかめないようだった。貧しさからは解放されたものの、「自分が主人公になれる現実もまた失われていた」と著者。その時、その人によってでなければ、書かれ得ない文章がある。
出久根達郎さんの解説は、まさに名文。この人の本も、書きたい人にとっての文章読本たり得る。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする