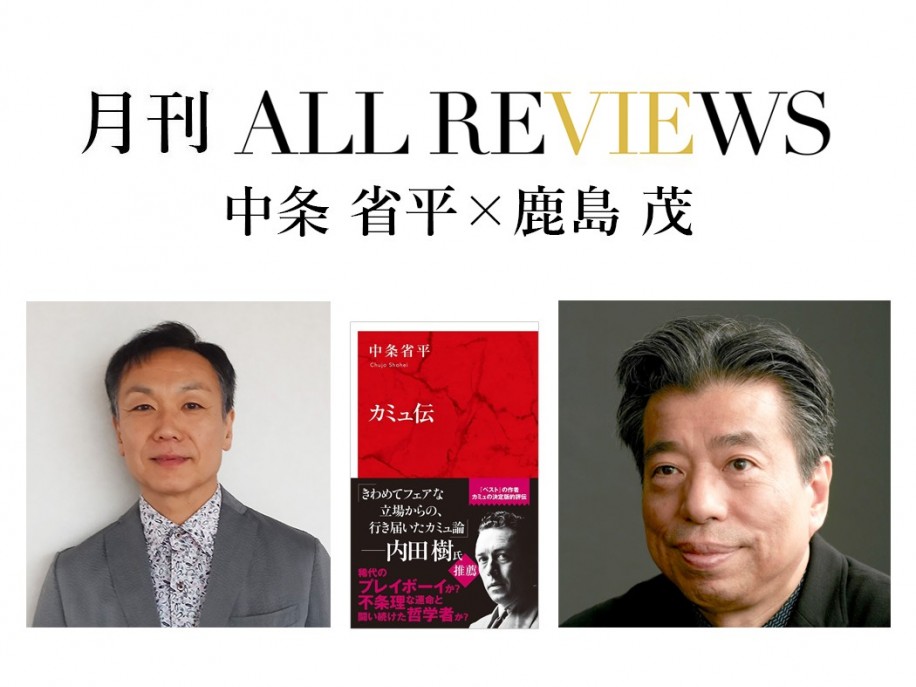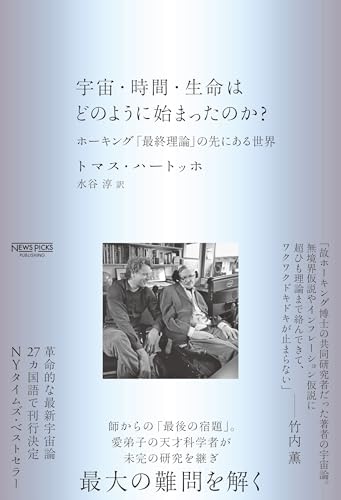書評
『ムラブリ 文字も暦も持たない狩猟採集民から言語学者が教わったこと』(集英社インターナショナル)
『ムラブリ』は、タイの文字を持たない狩猟採集民ムラブリと共に暮らし、彼らの用いる言語を学び、研究している若い言語学者の報告である。言葉だけでなくムラブリが何を考え、何を話しているかを知りたいと思うようになった時、言葉がすらすらと口から出て、聞きとりも上達したというのが興味深い。森の人を意味するムラブリは、DNA解析によって500~800年前に農耕民から独立した集団と分かった。
著者は、ムラブリ語はクレオールではないかと考えている。「所有表現の語順が『人―モノ』であること、『なに?』という疑問詞が二つの要素から成っていること、重複などの仕組みの乏しいこと」というクレオールの特徴があるからだ。この語にある三つの方言を、それぞれ500人、4人、20人が用い、しかも年寄りと若者で言葉が変わってきているという。言葉とはなんと柔軟なものなのだろう。彼らが共に暮らしたり離れたりする生活を見て著者は「言語が人々を統合し、同時に分離すること」を知る。同じ言語を話す時、ぼくらは同じだとなるのは会話が協力を求めるからだろう。人間は同じで違い、違って同じ存在であり、言語はまさにそれを示すものなのだ。
文字のないムラブリ語を学んだ著者は、「ムラブリ語を話せるようになる過程で変化した自分自身」が研究成果だと言う。言語は恣意(しい)的と言われるが、言葉が生まれた時には、そこで語り合った人に共感が生じたに違いなく、「どんな音でもよかった」とは言えず、言語を学ぶとはそれを話す仲間の中にあるその感覚を共有することではないか。ムラブリ語を話す時は、森の中で話す距離感で遠くの人に向けて話しており、ムラブリの身体性を意識するという。
言葉は人間とは何かを考える最も興味深い切り口の一つだ。文法や脳の機能などの解明だけでなく、日常生活の中での会話を追うことで、個に集中してきた人間理解を、仲間の中で生きる存在としての人間理解へと広げられるのが興味深い。違って同じ、同じで違うという人間の特徴を知る面白さも含めて。
著者は、ムラブリ語はクレオールではないかと考えている。「所有表現の語順が『人―モノ』であること、『なに?』という疑問詞が二つの要素から成っていること、重複などの仕組みの乏しいこと」というクレオールの特徴があるからだ。この語にある三つの方言を、それぞれ500人、4人、20人が用い、しかも年寄りと若者で言葉が変わってきているという。言葉とはなんと柔軟なものなのだろう。彼らが共に暮らしたり離れたりする生活を見て著者は「言語が人々を統合し、同時に分離すること」を知る。同じ言語を話す時、ぼくらは同じだとなるのは会話が協力を求めるからだろう。人間は同じで違い、違って同じ存在であり、言語はまさにそれを示すものなのだ。
文字のないムラブリ語を学んだ著者は、「ムラブリ語を話せるようになる過程で変化した自分自身」が研究成果だと言う。言語は恣意(しい)的と言われるが、言葉が生まれた時には、そこで語り合った人に共感が生じたに違いなく、「どんな音でもよかった」とは言えず、言語を学ぶとはそれを話す仲間の中にあるその感覚を共有することではないか。ムラブリ語を話す時は、森の中で話す距離感で遠くの人に向けて話しており、ムラブリの身体性を意識するという。
言葉は人間とは何かを考える最も興味深い切り口の一つだ。文法や脳の機能などの解明だけでなく、日常生活の中での会話を追うことで、個に集中してきた人間理解を、仲間の中で生きる存在としての人間理解へと広げられるのが興味深い。違って同じ、同じで違うという人間の特徴を知る面白さも含めて。
ALL REVIEWSをフォローする