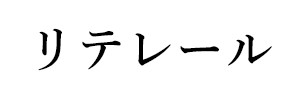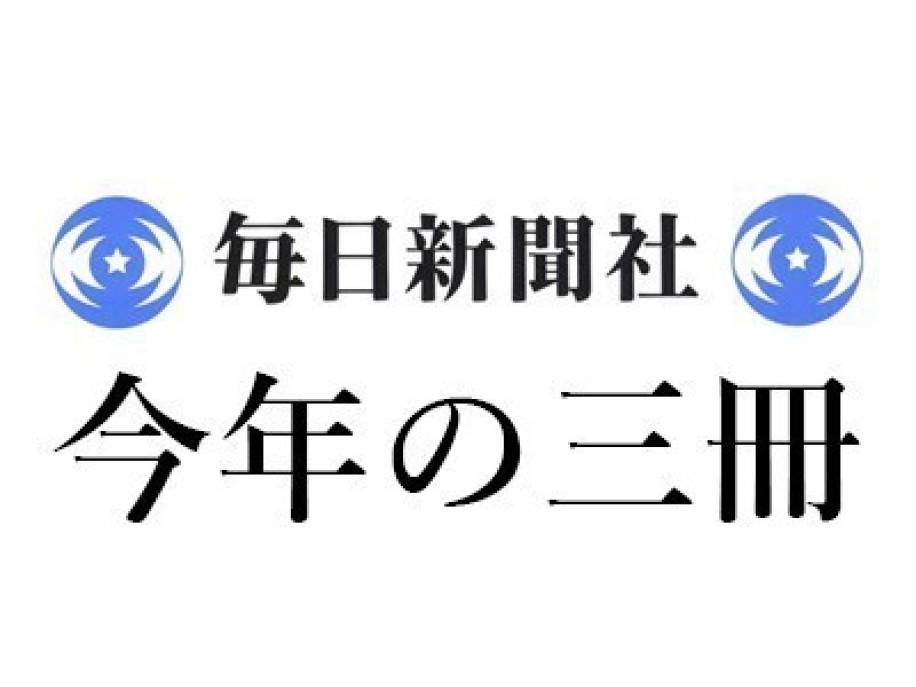コラム
島崎 藤村『家』(岩波書店)、徳田 秋声『仮装人物』(岩波書店)、芥川 龍之介『大導寺信輔の半生』(岩波書店)、ほか
わが読書「体系的」読書
私は、どちらかといえば「体系的」な読書をしてきたほうだと思う。もっとも、子供の頃には、家実が商家だったので、家に本と呼べるものは一冊もなかった。雑誌さえなかった。ただ新聞は、得意先の関係で、朝日、毎日、産経と三紙も取っていた。なかでも、産経新聞は子供用のページが充実していて、旧約聖書を絵解きにした漫画などが載っていたほか、あの山川惣治の『少年ケニヤ』が連載されていたから、これが私にとっての唯一の文化との接点となった。『少年ケニヤ』は単行本が出ると、せがんで全巻買い揃え、まだ字が読めなかったので、祖父に毎日読んでもらって、ほとんど完全に暗記してしまった。次に、『少年王者』や『少年タイガー』にも手を出した。とくに『少年王者』のペン画は、「少年ケニヤ』と比べてはるかにリアルな細密画で、脳裏に強烈な印象を残した。三十過ぎてフランスの挿絵本に狂いだしたのは、あるいはこの時の残像記憶があったのかもしれない。最近、家を建てるために、実家の倉庫を壊したところ、この三つの絵物語(懐かしい言葉)が、奇跡的に「発掘」された。『少年ケニヤ』の絵は思っていたほど鮮明なものではなく、多少がっかりしたが、『少年王者』第四集「豹(ひょう)の老婆編」は、少年王者牧村眞吾が水中でワニの腹をナイフで切り裂くシーンなど記憶以上の迫力で久々に堪能した。山川惣治の前書によると『少年王者』は最初に紙芝居として描いたのを『おもしろクラブ』に連載したものだそうで、おそらくそのために細部の描きこみが丁寧だったのだろう。
この絵物語を除くと子供の時に持っていた絵本は親類のおばさんに買ってもらった大日本雄弁会講談社の『世界探検物語』と、『世界のふしぎ』の二冊だけだったが、なにしろまだテレビもない時代だから、これも学校から帰ってくると、毎日繰り返し読んだ。この二冊も山川惣治の本と同時に最近「発掘」されたのだが三十六年ぶりにページを開いて驚いた。自分がイメージを浮かべるときのアーキタイプは、ほとんどこの二冊の中にあったのだ。なかでも鈴木御水の「アムンゼン」、古賀亜十夫の「ヘデン」、鈴木登良次の「セント・エルモのひ」、伊藤幾久造の「おおきなかげぼうし」は、記憶していたよりもさらに素晴らしい絵で本当にびっくりした。戦後のこの時期までは、戦前に活躍した画家たちがこうした子供向け絵本で糊口(ここう)の資を得ていたから、質が高かったのだろう。とにかく、「見いだされた時」が、いささかも色褪(いろあ)せていなかったのは奇跡というしかない。
ただ、この絵本に熱中したのは小学校二年生までで、その後は、当然、熱烈な漫画少年となった。毎月七日になると、板垣退助(百円札)を握りしめて『少年画報』を買いにいった。『少年』が中流階級の坊ちゃんに読まれていたのに対し、『少年画報』は「赤胴鈴之助」「ビリー・パック」「いがぐりくん」など誌面が充実していて、下層中産階級の漫画好きの少年に人気があった。ただ、いくら六大付録がついていても、月刊だからすぐ読み終えてしまう。この欲望を満たす方法は一つしかない。立ち読みである。
漫画を買いにいくのは、隣にあった「大成堂」という名のみ大きな小さな雑誌屋と決まっていたが、じつはこの店は私の家の店子だったのだ。あるとき、家主の息子という特権を生かして、かなり大っぴらに立ち読みができることを発見した。そのとき以来、この雑誌屋は私の図書館となった。『冒険王』『少年クラブ』『野球少年』『痛快ブック』など、ありとあらゆる漫画雑誌を読み尽くした。中でも一番楽しんだのは『少年クラブ』に連載されていた前谷惟光の『ロボット三等兵』で、太平洋戦争の戦史はこれ一つで学んだといってもよい。前谷惟光にはだいぶ打ち込んで、貨本屋で、『ロボット君』などのバリエーション物も全部読み尽くした。手に入るならいまでも読みたいと思う。
ところで、いくら雑誌屋で少年漫画の数が揃っているとはいえ、毎日立ち読みをしていれば、さすがに読むものが無くなってしまう。『りぼん』や『なかよし』などの少女漫画も読んで渡辺まさこの『カメリア館』や上田とし子の『フイチンさん』などの傑作にも遭遇したが、それにも限りがある。そんなとき、変な漫画雑誌を発見した。『土曜漫画』というタイトルで、わきに「土曜のようにワクワクする雑誌」という、キャッチフレーズが添えてある。開けてみて、私ははじめて大人の世界というものを発見した。我がヴィタ・セクスアリスである。以後、この雑誌屋は、こちらの方面で、きわめて吸引力の強い場所となった。『内外実話』『読切実話』『実話と秘録』といった実話週刊誌、『裏窓』『笑の泉』『世界裸か美グラフ*』『夫婦生活』『奇譚クラブ』などなど、グラフィックな面もさることながら、エクリチュールの面でも、これは、かなり強烈な感情教育とあいなった。あまりよく読むものだから、各誌のキャッチ・コピーまで覚えてしまって、後年、かの『マリ・クレール』を手にしたとき、これはファッション・ページは妻が、吉本隆明や蓮實重彦のページは夫が楽しめるのだから、「昔の『夫婦生活』と同じ《夫婦二人で読む雑誌》というコピーでいけるじゃないか」と放言して、皆の顰蹙(ひんしゅく)を買ったことがある。
しかし、こうしたエロ本(これまた懐かしい響き)も毎月全巻読んでいると、いかに敏感な感受性だろうとアキがくる。その結果、漫画とエロ本以外のありとあらゆる雑誌にも手が伸びることとなった。『ベースボール・マガジン』や『ボクシング』などのスポーツ雑誌、『航空情報』『丸』『ガン』などのオタク雑誌から、『平凡』『明星』といった芸能雑誌や『映画の友』『スクリーン』まで、さらには『主婦の友』『婦人倶楽部』などの主婦雑誌や『女学生の友』『美しい十代』などの女学生雑誌、あるいは『ヒッチコック・マガジン』や『マン・ハント』さえも、要するに浪曲とか盆栽の雑誌を除いて、小学生の頭で理解できるものはすべて読んだ。なかでも、平沢雪村主宰の『ボクシング』は一番の愛読誌で、世界ランキングを丸暗記し、試合など見たこともないのに、カシアス・クレイを苦しめた、クリーブランド・ウィリアムスというボクサーの大ファンになった。そして結局、少年少女文学全集の類は一冊も読まなかった。しかし、小さいとはいえ、一軒の雑誌屋をまるごと全部、毎月読んでいたのだから、これはやはり「体系的」な読書といっていいのではなかろうか。それに活字吸収量でいったら、この時期が我が生涯でも一番だろう。私が同世代よりも五、六歳上の人と話が合うのは、あるいはこのせいかもしれない。
こうした雑誌中心の読書は、中学生になっても続いたが、あるとき、読書感想文を宿題に出されてはたと困った。教師に指定された芥川龍之介の本を買いにいった私に隣町の本屋の店主は、その頃刊行が開始された筑摩書房の「現代文学大系」の芥川の巻を売りつけ、この文学全集はこれから毎月配本されるから、申し込みすれば届けてやるよと言った。その旨を伝えると両親は、受験の足しにでもなると勘違いしたのか、予約購読を承知した。かくして、私は毎月一冊ずつ、中学二年からまる五年間、まったく雑誌と同じような感覚で「配本順」に「現代文学大系」を読んでいった。これを「体系的」な読書といわずして、なんであろうか。配本は、芥川から始まって井上靖、島崎藤村という毒のなさそうな順番で進んでいったが、それでも一切文学作品というものに触れたことのない頭に「文学」は、それこそ砂に水が染み込むように浸透していった。もちろん、「配本順」であるから自分の好みで作家や作品を選ぶことはできない。だから、田山花袋の『百夜』などというおよそ退屈な作品でもちゃんと読んだ。しかしこの「体系的」読書にもそれなりの利点はあった。たとえば『新生』を読んでヘドがでるほど気持ち悪いと思っていた島崎藤村にも『家』などという、戦慄(せんりつ)すべき傑作があることを知ったのは、好みに任せた濫読(らんどく)ではあり得ない、「配本順」読書の功徳だろう。徳田秋声の『仮装人物』という自然主義の金字塔も、太宰治あたりから入った文学青年では、まず読むことのない作品である。
ただ、そうはいっても、配本が進むにつれて次第に自分の気質というものが読書の好みに現れるようになる。まず、芥川の『大導寺信輔の半生』と保吉ものは、下層中産階級の出身の人間としては、心穏やかでは読めない作品として強く印象に残った。もちろん思春期の常として太宰治にも入れこんで、『晩年』などはいまでも一言半句を記憶しているが、それは別にして、作品的には『ろまん燈籠』あたりの戦前の山の手の雰囲気が出ているものが好きだ。そのほか、伊藤整は、インテリの一番出したくないところをさらけ出すあのイヤラシサがなんとも好ましく、『若い詩人の肖像』は我が青春の一冊となった。しかし、リビドー的にいって自分の気質に近いのは谷崎・川端・三島・鏡花・朔太郎のライン、ちょっとはずれて有島武郎だろう。実は、中学から高校にかけてのベストを並べると、『痴人の愛』『眠れる美女』『仮面の告白』『照葉狂言』『青猫』『或る女』だから、精神分析を勉強したいまになって思うと、これはかなりアブナイ感動の仕方である。高校生になってからは、こうした古典の文学全集のほかに、現代文学も積極的に読むようになった。これには、講談社の「われらの文学」の刊行がおおいにあずかって力あった。とりわけ大江健三郎は高校生のときのアイドルで、あの新潮社の六巻の著作集も全部買って貪(むさぼ)るように読み、あと、第三の新人も漁(あさ)ったが、なかでは島尾敏雄に傾倒し、晶文社の著作集を全巻揃えた。『夢の中での日常』を読んだときの興奮は忘れられない。
海外文学は高校の図書館で、筑摩版のオレンジ色の「世界文学大系」や新潮社、河出書房の古い全集を一巻から順次読んでいった。とくに大長編はどんなにつまらないものでもすべてかたづけた。「次はこの棚」という具合に、物理的な配置が選択の基準になった。だから、『嘔吐』で、アルファベット順に本を読んでいる男が出てきたときには、非常に親近感を覚えた。この読み方からも分かるように私は案外、他律的、苦行的読書が嫌いではないのだ。「快楽としての読書」ばかりが叫ばれる今日には、むしろこうした、「苦行としての読書」というのを逆に顕揚してみたくなってくる。この手の読書のいいところは『ドン・キホーテ』『白鯨』『ガリヴァー旅行記』といった、実際には読まれることの少ない名作が、実は一番おもしろいことを教えてくれたことだろう。といっても『ジャン・クリストフ』とか『大地』などはやはり退屈で、馬鹿らしかったが、基本的には、小説は大長編を何週間も何か月もかけて読んでいくのが読書の本当の快楽だと今でも信じている。みんなが馬鹿にして読まない『静かなドン』は、『失われた時を求めて』とは違った意味で読書の醍醐味(だいごみ)を教えてくれる、数少ない小説だった。
もっとも、高校の後半からは、さすがにこうした「体系的」な苦行がいやになり、現代アメリカ文学やヌーヴォー・ロマン、現代詩に凝り出した。吉岡実『静物』と、フォークナーの『響きと怒り』は高校のときのベスト・ワンだった。
大学に入ってからは、おりから政治の季節ということもあり、吉本隆明に心酔した。『擬制の終焉』『異端と正系』『抒情の論理』『芸術的抵抗と挫折』などは、文字どおりスタミナ・ドリンクのようなもので、消耗(これも懐かしい言葉)したときに元気を回復するにはこれしかなかった。私は、こうしたファイティング吉本を知らず『言語にとって美とはなにか』とか『共同幻想論』だけを読んでうんぬんする人の言葉は一切信用していない。私は今でも強固な吉本教徒であり、自分の書いているものを含め、現在出回っている本はすべて、吉本隆明の著作に比べるとゴミだと思っている。また、吉本隆明に教えられる形で、同じ時期に三浦つとむの『弁証法とはどういう科学か』『日本語はどういう言語か』なども熱をいれて読んだ。三浦理論はいまでも有効性を失っていないと思う。
ただ、我々の世代の不思議なところは、吉本や三浦に傾倒する一方で、澁澤龍彦や種村季弘にも、同じように入れあげていた点だろう。澁澤の『夢の宇宙誌』『幻想の画廊から』、種村の『吸血鬼幻想』『アナクロニズム』は、内容もさることながら造本の素晴らしさにも強く魅了された。この時代の現代思潮社、薔薇十字社、美術出版社などの本は、まさに本そのものへの愛をかき立てずにおかぬものばかりである。さすがに澁澤の処女作は同時代には買えなかったが、澁澤の友人諸氏の処女作、処女翻訳はすべて出版と同時に買っている。なかでも種村季弘の『怪物のユートピア』、出口裕弘の『行為と夢』は、澁澤以上に親近感を感じて、いまでも時々読み返す。これらとは少し位相がずれるが、植草甚一も我が本棚の常連の一人だった。
日本文学はこの時期以降、まったくフィクションが読めなくなったが、なぜか野坂昭如だけは夢中になって、中間小説誌に載る傑作、怪作、珍作を、片っ端から読んでいった。『至福三秒』などはいま思いだしても笑いがこみあげてくる。もっとも小説は読まないかわりに、三島と坂口安吾の評論集は、熟読玩味してほとんど丸暗記した。安吾の『堕落論』や『安吾巷談』は、唯一この時期の生活の指針とすることができた本である。安吾全集の刊行だけでも、今はなき冬樹社の名前は出版史上に永遠に残るだろう。現在、この安吾のかわりをつとめているのは東海林さだおのエッセイで、処女作から始めて、いまだに新作を追いかけている。これから追っかけをやろうとしているのは武田花。写真も凄いが文も凄い。
海外文学は白水社、集英社、河出などの「新しい世界の文学」の系統に随分お世話になった。シリトーの『長距離走者の孤独』と、『土曜の夜と日曜の朝』のふてぶてしい主人公は、「やつらは狡(ずる)い。だが俺も負けずに狡い」という名セリフとともに、我が理想のヒーローとなった。また、『カタロニア讃歌』をきっかけに、オーウェルにも打ち込んで、『パリ・ロンドン放浪記』『牧師の娘』などは、まだ翻訳がなかったから原文で読んだ。SFもバラードやクラークのイギリス系統をだいぶ渉猟した。
このように教養学部にいたときには、もっぱら英米文学に親しみ、フォークナーかナサニエル・ウェスト(特に『ボルソ・スネルの夢の日常』)あたりをやろうかと考えていたのだが、なぜか文学部は、はずみで仏文を選んでしまった。そして仏文の二年間はクロード・シモンばかり読んで過ごし、卒論もこれで書いた。シモンはまったく読めないという人が多いが私はその逆で、『草』とか『歴史』とかの時間性そのもののような小説を、イメージをつまぐりながらゆっくりと読んでいくのが最高の快楽で、いまはその時間がないのが惜しい。
大学院に進んでからは、読書は楽しみではなく苦役(苦行ではない)になったので「読書遍歴」に書くべきことはあまりない。ただ、フロベールにしてもバルザックにしても、十九世紀の小説を専門に選んだのは、我ながら見事な選択をしたものと感心する。十九世紀のフランスは、文学も社会も、まったく、汲(く)めどもつきせぬ無尽蔵の宝庫だからだ。
ところで、フランス現代思想というのは私の頭にほとんど何の痕跡も残さなかったといっていい。「おれには暴力団の知り合いがいるぞ」といきがるのと同じレベルで、「フーコーが、デリダが、ドゥルーズが」と言うためにお勉強するのだったら、十九世紀の新聞でも小まめに読んでいるほうが、どれだけましかわからない。第一、十九世紀のジャーナリズムをやっていると、自分の頭の良さを見せつけようとする魂胆のアホらしさがよく解る。百年もつのは純理的な著作か、クソ・リアリズムかのいずれかで、中間は全部消える。どうせならクソ・リアリズムに徹したいものである。フランス思想では、サルトルの『想像力の問題』だけが心にかかった。サルトルは、その図抜けたパワーにより、現代フランスでは珍しい十九世紀的なアナクロ人間であるが、あるいはこんなことをいう私こそ、紛れもないアナクロなのかもしれない。
思想だったら、むしろドイツ語圏の方が、はるかに切実な問題を提起してくれる。フロイトは、翻訳と仏訳を併用してかなり真面目(まじめ)に読み、心を蒸気機関に例える局所論的・力動的見地とか、同じく証券取引所にたとえる経済論的見地に興味を覚えたが、肝心なところはドイツ語が解らなければわからないという結論に達して、途中で放棄した。翻訳では、どうしても隔靴掻痒(かっかそうよう)の感が残るからである。これは、最近ではベンヤミンについても言えて、あんまり掻痒感が強いので、いっそ一からドイツ語を勉強しようかと思っているほどである。
しかし、こうやって見てくると、「読書遍歴」などというもおこがましい、まことに貧弱きわまりない平凡な文学青年的リストであり、十七枚書くなどとうっかり言うのではなかったと後悔している。「読書しなかった遍歴」なら、充実していることは請け合いなのだが。
わが生涯の愛読書
山川惣治『少年ケニヤ』(産経新聞社)山川惣治『少年王者』(集英社)
『世界のふしぎ』(大日本雄弁会講談社)
『世界探検物語』(大日本雄弁会講談社)
前谷惟光『ロボット三等兵』(大日本雄弁会講談社)
夏目漱石『門』(新潮文庫)
島崎藤村『家』(筑摩書房)
徳田秋声『仮装人物』(筑摩書房)
二葉亭四迷『浮雲』(筑摩書房)
泉鏡花『照葉狂言』(筑摩書房)
永井荷風『濹東綺譚』(新潮文庫)
芥川龍之介『大導寺信輔の半生』(筑摩書房)
谷崎潤一郎『痴人の愛』(新潮文庫)
谷崎潤一郎『瘋癲老人日記』(中公文庫)
志賀直哉『暗夜行路』(岩波文庫)
有島武郎『或る女』(筑摩書房)
川端康成『山の音』(新潮文庫)
川端康成『眠れる美女』(新潮文庫)
萩原朔太郎『全詩集』(新潮社)
伊藤整『鳴海仙吉』(筑摩書房)
伊藤整『若い詩人の肖像』(新潮社)
石川淳『鷹』(講談社文芸文庫)
坂口安吾『堕落論』(ちくま文庫)
坂口安吾『安吾巷談』(ちくま文庫)
太宰治『晩年』(新潮文庫)
太宰治『ろまん燈籠』(ちくま文庫)
三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫)
三島由紀夫『金閣寺』(新潮文庫)
三島由紀夫『三島由紀夫文学論集』(講談社)
島尾敏雄『夢の中での日常』(講談社文芸文庫)
島尾敏雄『死の棘』(新潮文庫)
大江健三郎『芽むしり仔撃ち』(講談社文庫)
安西冬衛『軍艦茉莉』(思潮社)
中原中也『在りし日の歌』(角川書店)
吉岡実『静物』(思潮社)
セルバンテス『ドン・キホーテ』(岩波文庫)
スウィフト『ガリヴァー旅行記』(岩波文庫)
メルヴィル『白鯨』(新潮文庫)
ショーロホフ『静かなドン』(新潮社)
フォークナー『響きと怒り』(三笠書房)
フォークナー『八月の光』(新潮社)
ヘンリー・ミラー『北回帰線』(新潮文庫)
ナサニエル・ウェスト『ボルソ・スネルの夢の日常』(未訳)
シリトー『長距離走者の孤独』(集英社文庫)
シリトー『土曜の夜と日曜の朝』(河出文庫)
オーウェル『カタロニア讃歌』(現代思潮社)
オーウェル『パリ・ロンドン放浪記』(岩波文庫)
H・G・ウェルズ『タイム・マシン』(早川書房)
バラード『結晶世界』(東京創元社)
クラーク『幼年期の終わり』(早川書房)
ユゴー『レ・ミゼラブル』(新潮社)
ミュッセ『フレデリックとベルヌレット』(筑摩書房)
バルザック『ゴリオ爺さん』(新潮社)
バルザック『幻滅』(東京創元社)
バルザック『従妹ベット』(東京創元社)
フロベール『ボヴァリー夫人』(岩波文庫)
フロベール『感情教育』(中央公論社)
フロベール『ブヴァールとペキュシェ』(筑摩書房)
ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』(藤原書店)
ユイスマンス『さかしま』(桃源社)
ボードレール『悪の華』(集英社)
ボードレール『パリの憂愁』(筑摩書房)
プルースト『失われた時を求めて』(筑摩書房)
ジュール・ヴェルヌ『地底旅行』(早川書房)
アラン・フルニエ『モーヌの大将』(角川文庫)
サルトル『想像力の問題』(人文書院)
サルトル『家の馬鹿息子』(人文書院)
バタイユ『聖なる神』(二見書房)
マルセル・エーメ『壁ぬけ男』(早川書房)
セリーヌ『なしくずしの死』(集英社)
クロード・シモン『草』(新潮社)
クロード・シモン『フランドルへの道』(白水社)
クロード・シモン『歴史』(白水社)
河盛好蔵『フランス文壇史』(文藝春秋)
吉本隆明『抒情の論理』(未来社)
吉本隆明『擬制の終焉』(現代思潮社)
吉本隆明『心的現象論序説』(北洋社)
三浦つとむ『弁証法はどういう科学か』(講談社)
三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社)
澁澤龍彦『夢の宇宙誌』(美術出版社)
澁澤龍彦『幻想の画廊から』(美術出版社)
種村季弘『怪物のユートピア』(三一書房)
種村季弘『アナクロニズム』(青土社)
出口裕弘『行為と夢』(現代思潮社)
夢野久作『死後の恋』(『瓶詰の地獄』収録、角川書店)
植草甚一『ワンダー植草甚一ランド』(晶文社)
川本三郎『朝日のようにさわやかに』(ちくま文庫)
野坂昭如『エロ事師たち』(新潮文庫)
ホッケ『迷宮としての世界』(美術出版社)
ベンヤミン『ボードレール』(晶文社)
ベンヤミン『複製技術時代の芸術』(晶文社)
クラカウアー『天国と地獄』(せりか書房)
フロイト『夢判断』(人文書院)
ツヴァイク『バルザック』(早川書房)
クリヴィツキー『スターリン時代』(みすず書房)
ブランキ『革命論集』(現代思潮社)
マキノ雅弘『映画渡世』天の巻・地の巻(角川文庫)
東海林さだお『ショージ君の青春記』(文藝春秋)
ルイ・シュヴァリエ『労働階級と危険な階級』(みすず書房)
武田花『猫・陽のあたる場所』(現代書館)
*『世界裸か美グラフ』:一九六〇年までは『世界裸か美画報』名で刊行
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア