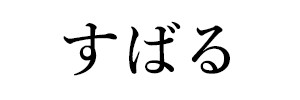作家論/作家紹介
池部 良『風の食いもの』(文藝春秋)、『心残りは…』(文藝春秋)、『酒あるいは人』(平凡社)、志村 三代子・弓桁 あや『映画俳優 池部良』(ワイズ出版)、他
最後の銀幕スタア――池部良賛江
一九七〇年秋。六時限めが終わって清掃の時間になったから机と椅子を教室のうしろにがたがたと寄せていると、男子がふたり箒(ほうき)を派手に振りまわす。ちょっとあんたたち、まじめに掃除してよ。すると、うるせえと無視され、芝居がかったひと言。「しんで、もらいます」
もうひとりが唱和。
「ごいっしょ、ねがいます」
振りまわしている箒はドスなんだそうだ。ふたりとも目がイッちゃっていた。
同年十一月二十六日。朝刊が家のなかから消えていた。へんだなと思って家捜しすると、新聞は押し入れの奥に隠してあった。一面には「三島由紀夫 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地(いちがやちゅうとんち)で割腹自殺」。そこには部屋内部のなまなましい写真が写っていた。前日二十五日、三島由紀夫が市ヶ谷に向かうとき口ずさんだ唄は「唐獅子牡丹(からじしぼたん)」、二カ月まえに封切られた東映映画「昭和残侠伝(ざんきょうでん) 死んで貰(もら)います」を観た三島が、風間重吉を演じる池部良(いけべりょう)が「何よりもよかった」と語ったと知るのは、すっかりおとなになってからのことだ。
「ご一緒、願います」は、「昭和残侠伝」シリーズ第七作「死んで貰います」の決め台詞。殴り込みにゆく池部良が高倉健(たかくらけん)に捧(ささ)げる覚悟の言葉である。あのころ駅近くにあった東映の映画館を通りかかると、着流し姿の高倉健と池部良が肩を並べて歩くでかい写真が異様な迫力で迫ってきて圧倒された。うわ、かっこいい、男子の気分もわかる、と呆然(ぼうぜん)。早熟な中一女子は未知の色気にどきどきさせられて、ころり。用もないのに遠回りして通った映画館のまえで、横目でこっそりポスターを見上げたりした。いま思い起こせば、それが池部良に出会った最初だった。
二〇〇六年夏。書店の新刊コーナーで一冊の文庫本を手に取った。すっきりと白いカバーに描かれた鰹(かつお)の線画になんともいえない情趣がある。タイトルの手書き文字にも味わいがあり、ふと読んでみたくなった。
『風の食いもの』池部良
ひさしぶりだな、池部良のエッセイ。九十年代に雑誌の連載コラムを読んだ記憶があった。なにしろびっくりするほど達者な筆運びで、あの「昭和残侠伝」のやくざとぜんぜん結びつかなかったのを覚えているけれど、それから何年も読むことがなかった。そもそも、本との縁は奇妙なところがあって、あるときぷつっと途切れもするが、ふとした拍子にふたたびあっさり繋がることがある。そういうときは縁のしっぽを逃がさないほうがいいというのが、本との長年のつきあいのなかで得た教訓である。こうして『風の食いもの』を一読、やっぱりうなった。それどころか二度も繰りかえして読み耽ったのである。
わたしが知る池部良のおおまかな足跡はこんなふうだ。
一九一八年(大正七年)、東京大森生まれ。父は画家の池部鈞(いけべひとし)、母は漫画家の岡本一平の妹。立教大学文学部英文科卒。在学中から東宝のシナリオ研究所で学び、大学卒業と同時に東宝へ入社、文芸部に配属される。監督志望だったが、あいにく助監督に空きがなく、島津保次郎監督に請われて「闘魚」に俳優として出演することになった。一躍スタアに躍り出るが、三作出演したところで昭和十七年に召集、「緑の大地」クランクアップと同時に入営して中国、ニューギニアへ。昭和二十一年復員。そののち、「青い山脈」「石中先生行状記」「坊っちゃん」「雪国」「暗夜行路」など文芸映画の主役に抜擢(ばってき)され、不動の人気を獲得する。がらりと路線を変えて新境地を切り開いたのは六十五~七十二年、東映「昭和残侠伝」シリーズ。高倉健の相棒役を好演してあらたなファンをつかむ。九十年代以降はエッセイストとしても旺盛(おうせい)な文筆活動をおこなう。
――池部良は、俳優として演技を、エッセイストとして文章をものして、昭和から平成を駆けてきた。いや、第一線に立って日本の歴史をくぐり抜けてきたというべきだろう。なにしろ昭和十七年二月、原節子(はらせつこ)や高峰秀子(たかみねひでこ)の「死んじゃ駄目よ」の声と万歳三唱に見送られて入隊以降、軍隊生活は約五年におよぶ。終戦時の階級は中尉(ちゅうい)。九死に一生を得て南方から生還を果たし、抑留ののち昭和二十一年に復員すると、映画会社が逸材を見逃すはずはなかった。復員後すぐさま東宝に請われ、ふたたび俳優として銀幕に登場する。復帰第一作はオムニバス「四つの恋の物語」(一九四七年 豊田四郎(とよだしろう)・成瀬巳喜男(なるせみきお)・山本嘉次郎(やまもとかじろう)・衣笠貞之助(きぬがさていのすけ)監督)。つづけて、戦後の民主日本のすがたを描いた「青い山脈」(一九四九年 今井正(いまいただし)監督)で大ブレイク。知的で甘いマスク、すらりとした長身、都会的で洒脱(しゃだつ)な身のこなし、泣く子も黙るオーラの輝きをふりまいてニッポンの女子を骨抜きにした。明朗快活な旧制高校生六助(ろくすけ)を演じたのは、なんと三十一歳のとき。つまり、それほど稀有(けう)な美貌(びぼう)だった。
「アイドルなんてもんじゃない、手の届かないところにいる銀幕のスタアよ。ただただうっとり仰ぎみるお方だったのよ。キムタクなんか引き合いに出すのも良さまに失礼千万だわよ」(当時の乙女談)
しかし、良さまはきのうまで兵七十名の独立小隊を率いて地を這(は)う従軍生活を送った「隊長殿」だったのです。ものすごいギャップではないか。ひとりの人間が日本の歴史の極端な明暗のなかに存在する……こんな「隊長殿」、こんな「スタア」など日本中探しても見つからない。
そのひとが書いた『風の食いもの』である。まったく独自の味わいの筆致に、わたしは目をまるくしてしまいました。綴られているのは約五年の戦争体験を土台にした食べものの話なのだが、しかし繰り言でもなく、あからさまな怒りや憤りでもなく、戦争体験自慢でも回顧でもない。まず、きっちり啖呵(たんか)を切る。
五十数年前の、あの戦争――大東亜戦争はどうして敗けてしまったのか。
敗因は、はっきりしている。
戦争に引っ張り出された兵士の、食いものの恨みに似た祟(たた)りだ。
食いものの恨み。これが一冊を牽引(けんいん)する真情である。食いものの恨みつらみを吐き出すなど東京生まれのやることじゃないと言いながら。
画家の父は「ばかやろ」が口ぐせで、三度三度の食べものにうるさかった。それに応えて母がせっせとおさんどんに精出す暮らしぶりの家に育ったから、季節に添うた質実な食卓が身に馴(な)じんでいたのである。ところが兵隊にはいれば大根の皮や魚の骨、申しわけていどの魚の身が浮いている薄い汁。アルミニウムの食器に摺(す)りきりの飯はコーリャン入りだったり、麦だったり。おかずは沢庵(たくあん)二切れ、得体の知れない魚の干物ひと切れ……餓鬼になった。輸送馬の餌用のゆで大豆をくすねて食べる、匍匐前進(ほふくぜんしん)中に発見したちび大根を引っこ抜いて匍匐しながら貪る、戦争のまっただなかに放りこまれて、食べるという行為が人間の尊厳を奪っていく事実に直面させられた。そして十九年四月、南方転進のため向かったフィリピン近海でアメリカの潜水艦に撃沈され、一団もろとも漂流。命からがら上陸した先は、ハルマヘラ島なる孤島。ジャングルにおおわれた島で兵士七十名を率いる「隊長殿」を待ち受けていたのは、ほかでもない飢えである。
とかげや蛙(かえる)はあたりまえ、なまけものやワニまで、早い話が、口に入るものはなんでも食べた。鎖骨に水が溜(た)まり、あばらが透けて見える栄養失調の兵士たちのいのちを「隊長殿」はどうにか拾ってやらなくてはならないのだから、うまいまずいなど言えるはずもない。さあ、ここでエッセイスト池部良の本領発揮だ。悲惨な食体験にもかかわらず、その筆にかかると軽妙なおかしみが滲む。たとえば、こんな場面。軍隊に入るまえ小料理屋で板前をやっていたという丸田上等兵が、だいじな「隊長殿」にうまいもんを食わせたいと腕をふるう。
「よーし、天どん作りましょ。昔取った杵柄(きねづか)だ。うまい天ぷらを揚げて見せますよ。海老(えび)だの、沙魚(はぜ)だの、めごちなんて洒落(しゃれ)たものは有りっこないですが、とかげと蛙の身を薄く切って」
「おい、そんなものが天ぷらになるのか。衣や油はどうするんだ」と言ったら、「代は見てのお戻りに、です」と敬礼をして背中を向けた。
陰惨なとかげと蛙の天丼(てんどん)なのに、冗談じみている。いよいよ追いこまれて食らうみみずも、おなじ具合。
「最後の蛋白質(たんぱくしつ)源だ。蚯蚓(みみず)を集めろ」と命令した。
「蚯蚓ですか」と七十名の兵隊さんは異口同音に怪訝(けげん)な声を吐いた。
幽鬼のようになった兵隊さんが集めた太くて長い糞(くそ)蚯蚓は、寿司屋(すしや)の盤台ほどの椰子(やし)の葉に山盛りになった。
ともあれ海水で茹(ゆ)でてみたが、何度茹で直しても褐色の泡が出る。
「これ以上煮たってしようがねえですよ」と言う高谷軍曹の進言に従って、茹でるのを中止。
茹で蚯蚓は各自の飯盒(はんごう)の中蓋(なかぶた)に摺り切り一杯が配給され、海水を蒸発させた自家製の塩をかけて食べることにした。
辛酸を舐(な)めたぞっとする体験なのに、読んでいるとやっぱりくふふと笑いがこみ上げてくる。食べものに恨みがあると啖呵を切っておきながら、「いやはやまったく」「ちょいとお聞かせいたしましょう」、懐からひょいひょいと取りだして披露してみせるのだ。ただし、その手つきには微妙な照れがある。一歩も二歩も退いて平気な顔をしてみせないと気がすまない。そこには韜晦(とうかい)の気配さえある。しじゅう文中に出てくる決めぜりふ「東京生まれの東京育ち」「江戸っ子」のフレーズも、ふつうなら嫌みになりそうなところだが、寸止めの軽妙なおもしろさに持ちこむ。これが『風の食いもの』の味わいどころ、池部良の文章の醍醐味(だいごみ)だ。
やっぱり、スタアなのです。東宝生え抜き、日本映画の黄金期にメロドラマから戦争映画、文芸映画の主役を張ってきた押しも押されもせぬ銀幕の大スタアの文章。池部良の書くものにはどれも、スタアの栄光とプライド、自意識のうしろ盾が潜んでいる。だからこそ唯一無二。悲惨きわまる戦争体験さえ華麗なエピソードに仕立ててしまう。凡人とは人種がちがう。
映画にはラストシーンという宝玉がある。一編すべてのカットを集約させ、夢まぼろしのようにいつまでも網膜に棲みつづける。わたしにとって忘れがたいラストシーンのひとつに「早春」(一九五六年 小津安二郎(おづやすじろう)監督)がある。
都会のサラリーマンの群像劇にからめて、こどもを亡くした若い夫婦の倦怠(けんたい)が描かれるこの作品は、小津安二郎の作品のなかでもめずらしいのびのびとした作風だ。夫婦役は池部良と淡島千景(あわしまちかげ)。愛人役に岸惠子(きしけいこ)。ふたりがお好み焼き屋でかわすキスは、小津映画初のキスシーンである。また、池部良にとっても、東宝の看板でありながら小津安二郎にわざわざ主演を請われて松竹映画に出演した「早春」は、俳優人生のなかでもエポックメイキングな作品になった。そのラストシーン。淡島千景演じる妻は夫の不実を知りながら許そうか許すまいか、池部良演じる夫は妻との葛藤(かっとう)や自分の行く末への不安を抱えながら詫(わ)びようか詫びまいか、たがいにこころ乱れる。ふたり押し黙ったまま二階の窓ぎわに立ち、煙を吐きながら走ってゆく山陽線の汽車をじいっと見送る。左手に池部良、右手に淡島千景。並列の立ち位置の間に横たわっている微妙な、しかしあきらかな距離。横側からカメラが捉えたツーショットには、男女の機微が鮮烈に映しだされて目に焼きついた。池部良は、小津安二郎にみごとに応えてみせていた。
映画人としての池部良を知るうえで絶好の一冊がある。それが『映画俳優 池部良』。二〇〇七年に刊行されたこの本は、池部良こそ日本映画のイコンだと評価する日本映画史研究者、志村三代子(しむらみよこ)と弓桁(ゆみけた)あやによって編まれた労作である。そのなかの「現代人」(一九五二年 澁谷實(しぶやみのる)監督)を語った際のインタヴューで、こんな肉声を引き出している。
「僕は、当時、俳優という仕事を男子一生の仕事にしようなんて思っていなかったし、俳優としてうまくやっていける自信もなかったんです。監督になりたい人間が俳優をやっているんですから、気持ちの上で矛盾だらけの生活をしていたんですよ。(中略)ふと考えたら、どの映画も二枚目だのつっころばしだのと言われてばかりで、嫌気がさしちゃったんだよね」
みずから東宝に出した企画はにべもなく断られ、いよいよ俳優を辞めようと行き詰まったとき出演したのが「現代人」だった。小津安二郎、木下惠介(きのしたけいすけ)とならんで「松竹御三家」と謳(うた)われた監督、澁谷實の緻密(ちみつ)な演技指導を受けたことで、俳優を自分の仕事として初めて意識したと告白している。
「やっぱり映画俳優っていうのは、自分で考えて、ひとつの動作のわずかな間にその人物の片鱗(へんりん)が見えないとダメだと思う。(中略)段々映画俳優というものが、『あっ、そういうもんなのか』とわかってきた。作家が小説を書くときと同じように、やっぱり俳優も考えなくちゃいけないんだという気持ちが芽生えたような気がする。それでこの『現代人』を境に、俳優を男子一生の仕事にしていきたいなと思ったんだよ」
ところで、日本映画には「文芸路線」とよばれた一連の作品群がある。一九五〇年代、純文学を原作にして仕立てた映画には独特のロマンティシズムがあり、女性を中心に絶大な集客力を発揮した。その「文芸路線」でおおきな役目を果たしたのが、ほかでもない池部良である。なにしろ小説の映画化をかたくなに拒みつづけてきた志賀直哉(しがなおや)でさえ、池部良の出演を条件に「暗夜行路」(一九五九年 豊田四郎(とよだしろう)監督)の映画化を快諾したのだから。
「僕が直接志賀先生に、『「暗夜行路」をやりたいとプロデューサーが言っているんですけど、どうでしょうか。映画化権をいただけますか』と申し上げた。そうしたら『いいですよ。但し、池部君、君が謙作をおやりになるんだったらいいです』、『それは身に余る光栄です』となって、映画化権をもらってきた」
名だたる作家にも愛されて、「破戒」(一九四八年 木下惠介監督 原作・島崎藤村(しまざきとうそん))、「青い山脈」(一九四九年 今井正監督 原作・石坂洋次郎(いしざかようじろう))、「風立ちぬ」(一九五四年 島耕二(しまこうじ)監督 原作・堀辰雄(ほりたつお))、「乱菊物語」(一九五六年 谷口千吉監督 原作・谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう))、「雪国」(一九五七年 豊田四郎監督 原作・川端康成)……ひっぱりだこ。とりわけ「雪国」は文芸映画の極めつきだろう。
主人公島村に池部良、芸者駒子(こまこ)に岸惠子、葉子に宝塚出身の新進女優、八千草薫(やちぐさかおる)。原作は、雪国を舞台に三人のあいだを綾なす恋の心理描写を繊細に表現しているが、川端康成は島村の人物像を具体的には書きこまなかった。それをどう見せるか、どう演じるか、映画人の力量が問われる。しかし、ふっくらと積もる現実の雪景色のなかで小説にあらたな肉づけをしてみせたのが池部良であり、豊田四郎であり、女優陣であり、技術陣だった。島村役を引き受けたときの心境を描く文章も、なかなかいい。映画人たちとの交流を綴った『心残りは…』の文中、島村という役柄について。
川端先生のあとがきに「つまるところ駒子の引き立て道具に過ぎないのだろう。それが、この作品の失敗であり成功なのかも知れぬ」とあり、「島村は愛し得ぬ悲しみと悔いとを胸に沈めていて、その空虚がかえって作品の中の駒子をせつなく浮き出させているのではなかろうか」とも書かれてあった。
これを読んだら、ちょっと陰気ではあったが映画俳優という筋肉が、もりっと音を立てて盛り上がるのを感じた。
完成試写を観た川端康成は、「池部さん。少し美男すぎますが、島村という男は、ああいう男だったのですか」と、川端なりの納得を口にしたという。
いずれにせよ、ひとりの生身の人間があまたの文学作品をつぎつぎに体現し、かつヒットさせるなど、そんじょそこらの俳優がなし得る業ではない。澁谷實監督にしごかれて演技に開眼した意気ごみが生来のカリスマ性に注入され、もはやこわいものなし。一九五〇年代、池部良はてんやとわんやがいっしょにやって来たような多忙ぶり、泣く子も黙るトップスタアの座に君臨した。
しかし、スタアにも転機は訪れる。池部良の大転換点、それこそ、あの「昭和残侠伝」なのだった。
ALL REVIEWSをフォローする