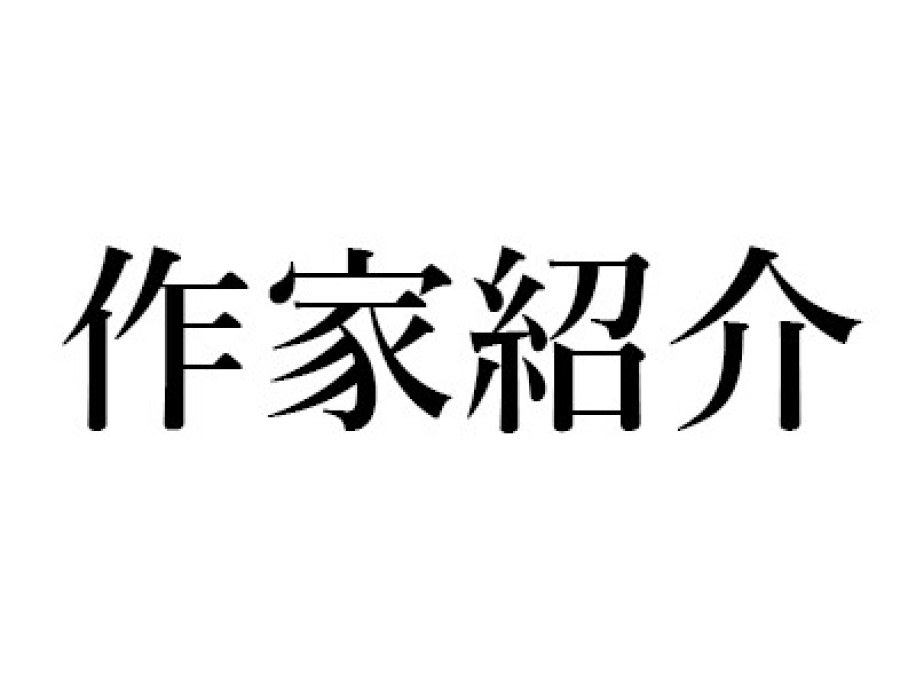書評
『遊撃の美学: 映画監督中島貞夫』(ワイズ出版)
アナーキーな精神に満ちた巨匠の全容
私にとってこの夏最高の映画体験は、東京・新文芸坐の「中島貞夫特集」だった。暑いなか連日つめかける観客の熱気も凄かったが、中島映画のごった煮的パワーは、現在の映画界にはもはや存在しない貴重なもので、見るたびに力がわき、仕事の合間をぬって夜討ち朝駆けで日参した。本書は、中島貞夫の映画マジックを解明する全作品インタビューなのだ。中島貞夫は、日本プログラムピクチャーの最後の巨匠である。
プログラムピクチャーとは、ひと言でいえば二本立て映画のことだ。一本立てになって予算も増えて映画は作りやすくなったかというととんでもない。広い観客層を狙うので、中身に制約ができて、「シャシンに毒がなくなっ」た。その点、中島貞夫は二本立て出身で、時代そのものがアナーキーだった一九六〇年代後半から七〇年代にかけて五〇本もの映画を撮った。時代劇、仁侠映画、ポルノ、戦争映画、ドキュメンタリー、実録ヤクザもの、なんでも撮ったし、なんでも撮れた。こんな大監督はもう二度と出ない。
作品歴の多彩さは、中島貞夫の思想の反映でもある。父親を犬死にさせた太平洋戦争の敗北による価値崩壊がその出発点である。中島が、深作欣二と肝胆相照らす仲だったのは、戦後の安定を拒否し、しかしニヒリズムの無力に行かず、アナーキーな精神の高揚を肯定する姿勢に共通するものがあったからだろう。
それゆえ、なによりも単一の価値観を嫌い、『あゝ同期の桜』のような特攻精神の極限を問う戦争映画も、『893愚連隊』のような「ネチョネチョ生きとる」ことを謳(うた)うだらしないヤクザ映画も、『ポルノの女王にっぽんSEX旅行』のような不思議なやさしさにみちた「エロとテロ」の映画も撮ることができた。
こうした中島のゲリラ的映画作りは、東映という会社での「企業内抵抗」と呼ばれたが、なにより金が重要な映画製作において、これほど柔軟かつ強靭な精神力を発揮した人物の記録は、高度資本主義の現代にこそふさわしい倫理の書として読める。凡百の人生論よりはるかに刺激にみちた教育的名著でもあるのだ。
朝日新聞 2004年08月29日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする