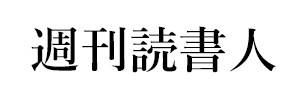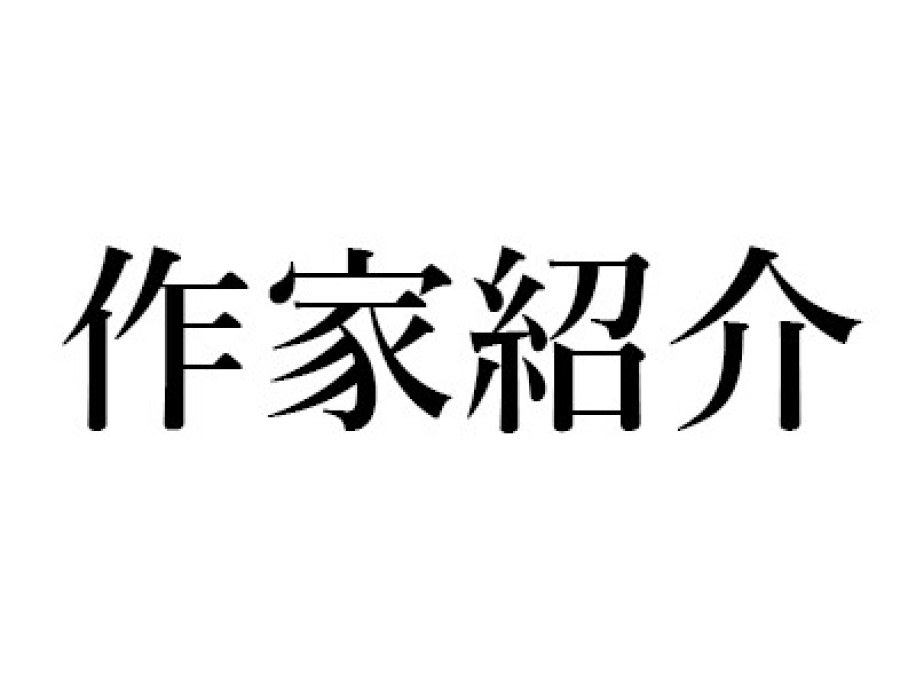書評
『時効なし。』(ワイズ出版)
小津安二郎の映画について、人はいくらでも饒舌を重ねることができる。だってそれは文化の安全地帯の内側で生じる一事件にすぎないからだ。デリダについて、人はいくらでもお酒落な雑文を書くことができる。だってそれは既成の知的秩序のなかで生じる、優雅な戯れにすぎないからだ。誰もが競って口にしている。もう文化にスキャンダルはありえない。アンダーグラウンドという領域はもはやノスタルジアに属してしまった。それがポストモダンのゲームの規則なのだと。
だが、本当にそうなのか。ここに一人の映画監督がいて、スキャンダルにもアンダーグラウンドにも時効などないのだと、ドスの利いた声を響かせているとしたら。若松孝二のこのインタヴューが語っているのは、世界にはまだけっして秩序に回収されることのない、映画の危険な領域が頑強に存在しているという事実だ。
若松の映画について語ることは、ゴダールや成瀬巳喜男について語ることとはおそろしく違っている。芸術とは無縁な、女性蔑視の暴力主義者と非難されるかもしれない。テロリストと見なされるかもしれない。ひょっとしたらそのせいでアメリカからヴィザが降りなくなるかもしれない。だから今日の映画評論家は、できることなら避けて通りたいと思っている。まわりを見回してごらんよ。若松孝二はスゴイと堂々といえる奴がどこにいる?
あらゆるフィルムを作り上げているのは政治であり、政治とはきわめて映画的な現象なのだとキチンと書いている奴がどこにいるだろう。
『時効なし。』を読むと、60年代にピンクの帝王として低予算早撮りを得意としていたこの監督が、70年代の初頭にパレスチナ人の難民キャンプを訪れ、PFLP(パレスチナ解放人民戦線)の生活をドキュメンタリーカメラに収めた時を転機として、より大きな世界へと活躍の場を拡げていったことが、きわめて興味深い挿話とともに語られている。財政的にも政治的にも、予期せざる困難が彼に襲いかかる。公安警察は機会あるたびにガサ入れを繰り返し、海外での撮影はことごとく妨害される。そのなかで若松は巧みに権力の裏をかき作品を撮りあげたかと思うと、自分の身辺にいる年少者たちが映画を撮れるように、細かな配慮を払い続ける。彼は持ち前の含羞から、けっして声高く政治を語ろうとせず、もっぱら金の苦労話しか語ろうとしない。だが延々と続く苦労話の連続から浮かび上がってくるのは、製作者としての冷静な判断力であり、教育者としての思いがけぬ側面である。
それにしてもここに描かれている男たちの友情と信頼の、なんと強靭にしてすばらしいことか。足立正生、赤塚不二夫、和光晴生、阿部薫といった面々とホモソーシャルな絆を結んでゆく若松のあり方が、本書をより魅力的なものにしている。
若松孝二は生涯に最後のフィルムとして、あさま山荘事件を描いておきたいという。
「あれを撮らないと終わらない気がするんだよね」と、語っている。映画監督に時効はない。この企画が実現したときは、自分の引退のときだとまで口にしている。おそらくそれは、ノスタルジアでも政治分析でもなく、限界状況に置かれた男たちの絆の物語となることだろう。刮目(かつもく)して待つことにしようではないか。
(追記)2007年に若松はついに『実録・連合赤軍』を撮りあげた。次は山口二矢事件を描くのだという。スゴイなあ。
【この書評が収録されている書籍】
だが、本当にそうなのか。ここに一人の映画監督がいて、スキャンダルにもアンダーグラウンドにも時効などないのだと、ドスの利いた声を響かせているとしたら。若松孝二のこのインタヴューが語っているのは、世界にはまだけっして秩序に回収されることのない、映画の危険な領域が頑強に存在しているという事実だ。
若松の映画について語ることは、ゴダールや成瀬巳喜男について語ることとはおそろしく違っている。芸術とは無縁な、女性蔑視の暴力主義者と非難されるかもしれない。テロリストと見なされるかもしれない。ひょっとしたらそのせいでアメリカからヴィザが降りなくなるかもしれない。だから今日の映画評論家は、できることなら避けて通りたいと思っている。まわりを見回してごらんよ。若松孝二はスゴイと堂々といえる奴がどこにいる?
あらゆるフィルムを作り上げているのは政治であり、政治とはきわめて映画的な現象なのだとキチンと書いている奴がどこにいるだろう。
『時効なし。』を読むと、60年代にピンクの帝王として低予算早撮りを得意としていたこの監督が、70年代の初頭にパレスチナ人の難民キャンプを訪れ、PFLP(パレスチナ解放人民戦線)の生活をドキュメンタリーカメラに収めた時を転機として、より大きな世界へと活躍の場を拡げていったことが、きわめて興味深い挿話とともに語られている。財政的にも政治的にも、予期せざる困難が彼に襲いかかる。公安警察は機会あるたびにガサ入れを繰り返し、海外での撮影はことごとく妨害される。そのなかで若松は巧みに権力の裏をかき作品を撮りあげたかと思うと、自分の身辺にいる年少者たちが映画を撮れるように、細かな配慮を払い続ける。彼は持ち前の含羞から、けっして声高く政治を語ろうとせず、もっぱら金の苦労話しか語ろうとしない。だが延々と続く苦労話の連続から浮かび上がってくるのは、製作者としての冷静な判断力であり、教育者としての思いがけぬ側面である。
それにしてもここに描かれている男たちの友情と信頼の、なんと強靭にしてすばらしいことか。足立正生、赤塚不二夫、和光晴生、阿部薫といった面々とホモソーシャルな絆を結んでゆく若松のあり方が、本書をより魅力的なものにしている。
若松孝二は生涯に最後のフィルムとして、あさま山荘事件を描いておきたいという。
「あれを撮らないと終わらない気がするんだよね」と、語っている。映画監督に時効はない。この企画が実現したときは、自分の引退のときだとまで口にしている。おそらくそれは、ノスタルジアでも政治分析でもなく、限界状況に置かれた男たちの絆の物語となることだろう。刮目(かつもく)して待つことにしようではないか。
(追記)2007年に若松はついに『実録・連合赤軍』を撮りあげた。次は山口二矢事件を描くのだという。スゴイなあ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする