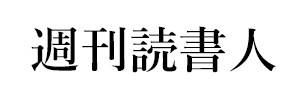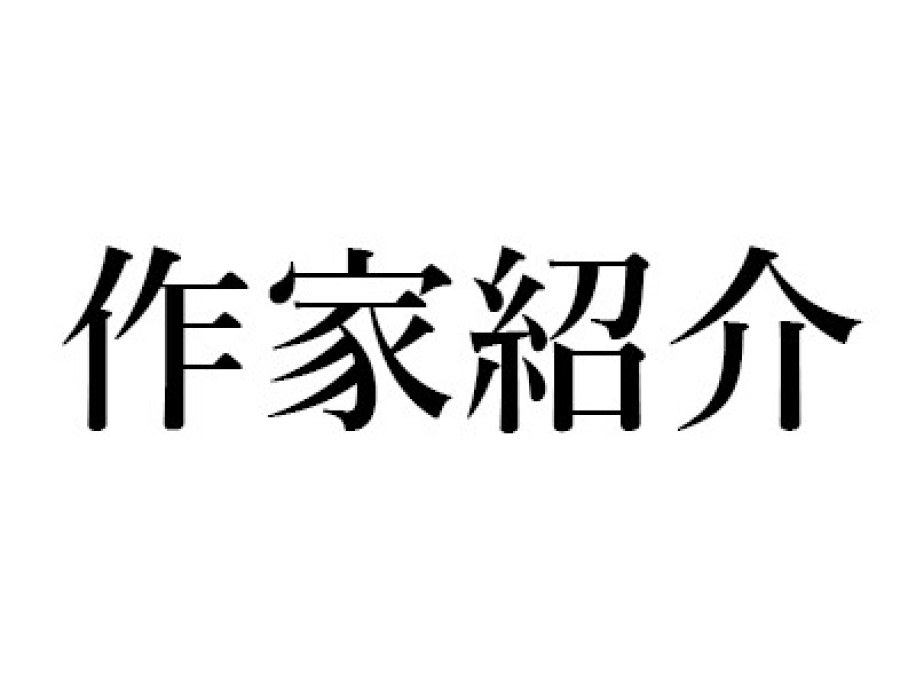書評
『映画俳優 安藤昇』(ワイズ出版)
日本の映画界がヤクザと切っても切れない関係にあることは、ハリウッドがユダヤ人と密接な関係にあることと、はたして比較できるだろうか。いずれもが社会のなかで周縁に置かれ、けっして表にでない場所から映画界に大きな権能を振るってきた点で、共通するものをもっている。日本映画史の研究をしていたわたしは、その裏筋として、日本仁侠史を本格的に勉強しなければいけないと思いあたったことがあった。
思い出してみよう。戦前の日本映画の中心は制作ではなく興行であったが、この興行の権利はしばしば地元のヤクザによって握られていた。大映を創設した永田雅一は京都の千本組の出身であったし、若松孝二ももとを正せばヤクザの若衆で、撮影現場に集まった群衆を整理することから映画界を見知ったのであった。
安藤昇もまた例外ではない。特攻隊の生き残りとして戦後の闇市社会に復員してきた彼は、渋谷に安藤組の看板を掲げ、日本で最初の近代的なヤクザ組織を築きあげた人物である。映画界の五社協定を平然と無視して、各社のスターをステージで共演させたり、力道山に詫びを入れさせるため、配下のプロレスラーを次々と監禁したり、向かうところ敵なしといった構えで戦後社会を生き抜いてきた。その安藤が東洋郵船の横井社長を襲撃した事件がきっかけで入牢し、釈放されたのちに映画俳優の道を歩んだことは、すでに多くの自伝や出演作のフィルムで語られてきたとおりである。加藤泰の『男の顔は履歴書』で安藤が沖縄戦の生き残り医師を演じたとき、彼はまだ保護観察期間中であったという。「俺が死んで泣くやつ千人、笑うやつ千人、知らぬそぶりが千人か。まとめてあばよをいわせてもらうぜ」。わたしの耳に今なお残響しているのは、『男が死んで行く時に』という曲のなかで、彼が叫んでいたこの言葉である。
本書は、かつて状況劇場に籍をおいていたさいに、映画撮影を通して安藤と知り合いとなった山口猛が、すでに俳優としては引退して久しい安藤のもとを訪れてインタヴューを行なった記録である。安藤のフィルムと著作はつねに自伝的なものであった。したがって本書を前にはじめて公開される、新しい自伝的事実などというものはもはやない。とはいうものの、それは二つの点において興味深い。ひとつは、みずからの生涯にいかなる執着も後悔もなく、まるで遠いところを眺めるかのように語る安藤の姿勢である。もうひとつは、ときおり口にされる、思いがけないディテイルの面白さである。後者の二、三を紹介しておこう。
安藤が最初に映画界と接触をもったのは、戦後の大きな東宝争議のさいに新東宝の用心棒として雇われた愚連隊の親分、万年東一の助っ人としてであったこと。最初に籍を置いた松竹で助監督だった山田洋次に、のちにヤクザを主人公にした喜劇を撮ってみないかと打診したところ、一度は断った山田がしばらくして『男はつらいよ』シリーズを発表しだしたこと。「あいつを締めあげなければいけないところだ」と、安藤はドスをきかせていう。このあたりに本書の面白さが横たわっている。
それにしても安藤昇の娘はどうして映画界にデビューしなかったのだろう。クラウス・キンスキーの娘ナスターシャの活躍ぶりを見るにつけ、それが残念でならない。本書を読むと、相当の美人であったことは、間違いないと思われるのだが……。
【この書評が収録されている書籍】
思い出してみよう。戦前の日本映画の中心は制作ではなく興行であったが、この興行の権利はしばしば地元のヤクザによって握られていた。大映を創設した永田雅一は京都の千本組の出身であったし、若松孝二ももとを正せばヤクザの若衆で、撮影現場に集まった群衆を整理することから映画界を見知ったのであった。
安藤昇もまた例外ではない。特攻隊の生き残りとして戦後の闇市社会に復員してきた彼は、渋谷に安藤組の看板を掲げ、日本で最初の近代的なヤクザ組織を築きあげた人物である。映画界の五社協定を平然と無視して、各社のスターをステージで共演させたり、力道山に詫びを入れさせるため、配下のプロレスラーを次々と監禁したり、向かうところ敵なしといった構えで戦後社会を生き抜いてきた。その安藤が東洋郵船の横井社長を襲撃した事件がきっかけで入牢し、釈放されたのちに映画俳優の道を歩んだことは、すでに多くの自伝や出演作のフィルムで語られてきたとおりである。加藤泰の『男の顔は履歴書』で安藤が沖縄戦の生き残り医師を演じたとき、彼はまだ保護観察期間中であったという。「俺が死んで泣くやつ千人、笑うやつ千人、知らぬそぶりが千人か。まとめてあばよをいわせてもらうぜ」。わたしの耳に今なお残響しているのは、『男が死んで行く時に』という曲のなかで、彼が叫んでいたこの言葉である。
本書は、かつて状況劇場に籍をおいていたさいに、映画撮影を通して安藤と知り合いとなった山口猛が、すでに俳優としては引退して久しい安藤のもとを訪れてインタヴューを行なった記録である。安藤のフィルムと著作はつねに自伝的なものであった。したがって本書を前にはじめて公開される、新しい自伝的事実などというものはもはやない。とはいうものの、それは二つの点において興味深い。ひとつは、みずからの生涯にいかなる執着も後悔もなく、まるで遠いところを眺めるかのように語る安藤の姿勢である。もうひとつは、ときおり口にされる、思いがけないディテイルの面白さである。後者の二、三を紹介しておこう。
安藤が最初に映画界と接触をもったのは、戦後の大きな東宝争議のさいに新東宝の用心棒として雇われた愚連隊の親分、万年東一の助っ人としてであったこと。最初に籍を置いた松竹で助監督だった山田洋次に、のちにヤクザを主人公にした喜劇を撮ってみないかと打診したところ、一度は断った山田がしばらくして『男はつらいよ』シリーズを発表しだしたこと。「あいつを締めあげなければいけないところだ」と、安藤はドスをきかせていう。このあたりに本書の面白さが横たわっている。
それにしても安藤昇の娘はどうして映画界にデビューしなかったのだろう。クラウス・キンスキーの娘ナスターシャの活躍ぶりを見るにつけ、それが残念でならない。本書を読むと、相当の美人であったことは、間違いないと思われるのだが……。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする