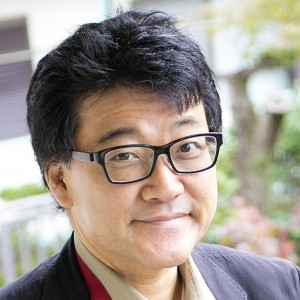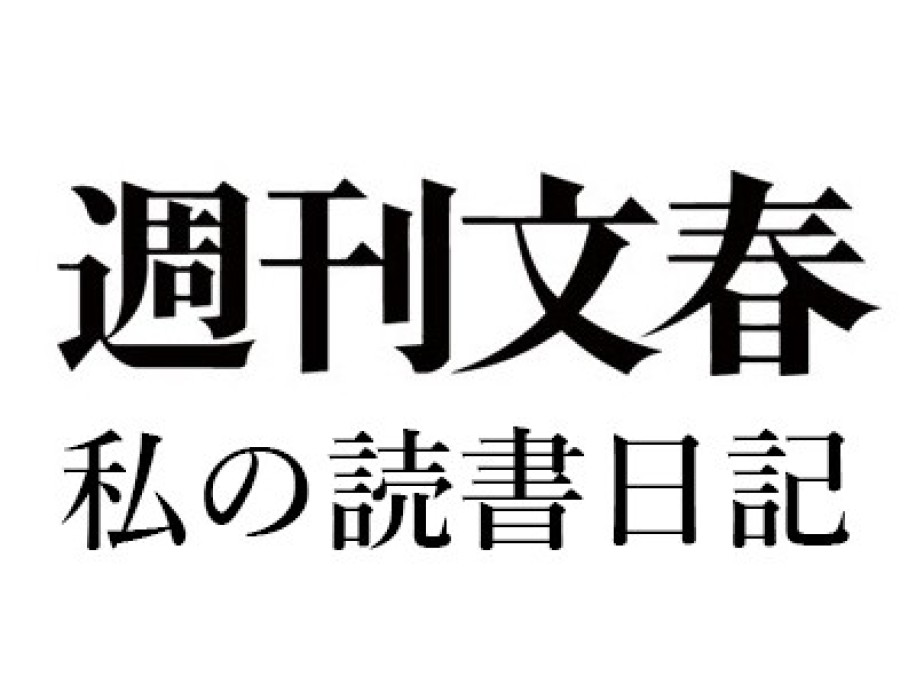前書き
『世界文学ワンダーランド』(本の雑誌社)
文学は最高のエンターテインメントだ。ぼくはそう思っている。
文学はなんでもあり。ふつうじゃ考えつかないことを平気でやる。手加減なしに無茶をする。天衣無縫破天荒御意見無用である。どうせ読むならそういうものを読みたい。
ぼくは、ジャンル小説もだいぶ読むし、べつに文学のほうが高級だとか上等だなどと思っちゃいない。これは文学だとかこれは大衆小説だとかいう区別なんて、くだらないことだろう。しょせんはマーケティング上のことにすぎない。
それをわかったうえで、あえて言う。文学こそいちばんのエンターテインメントだ。
たとえば、無差別級の小説王者決定戦を開催すれば、SFやミステリからも有力選手がエントリーしてくるだろう。具体的に名をあげるなら、スタニスワフ・レム『天の声』、G・K・チェスタトンの『木曜の男』といったあたりだ。この両作品は、ジャンル内部でも傑作の呼び声が高い。しかし、そのいっぽうで、「『天の声』はSFの枠組みを超えてしまった」とか、「『木曜の男』はミステリの作法から逸脱している」という声も聞こえる。これは称讃の言葉であると同時に、とまどいの表明でもある。ジャンルというのは求心的なものであり、特定のジャンルに馴染んだ人たちは、作品そのものの価値以上に「ジャンル小説らしさ」を愛している。ジャンルごとに、アイデンティティというか、本質というか、ジャンルをジャンルたらしめているものがある。
文学にはそんなものはない。枠組みもないし、作法も決まっていない。本質や原点や目的なんてヤボなことはいわない。もし、SFリーグがレムはちょっと困るというなら、文学へと移籍していただきましょう。ミステリ・ギルドがチェスタトンを扱いかねるというなら、文学が席を用意します。まあ、SFファンもミステリ愛好家も、そんなもったいないことは言わないでしょうが。ぼくだって文学側のヘッドハンターじゃないしね。
まあ、やっかいなのは、SFやミステリの世界にフェティッシュなファンがいるように、文学にも偏執的マニアがいることで、この連中が、ときおり「こんなものは文学じゃない」などと妄言を吐いたりする。そういうバカどもの声が大きいものだから、文学はクラくてダサくてイモいものだと、世間から誤解されてしまう。
だいたい、ラブレーが『ガルガンチュアとパンタグリュエル物語』でお尻の穴までさらけだし、ロレンス・スターンが『トリストラム・シャンディ』で無法のかぎりをつくし、ジェイムズ・ジョイスが『ユリシーズ』で良俗や常識を徹底的に踏みにじってきた――それが文学の系譜なのである。アヴァンギャルドなのだ。パンクなのだ。これでいいのだ。やりたいほうだいの世界で、いまさら上品ぶったり偉ぶったりするのは烏滸の沙汰である。
文学は、書くほうがなんでもありなら、読むほうだって自由で気ままだ。べつにルールやマナーがあるわけではない。高級レストランで食事をするわけじゃないのだ。むしろ、ぼくのイメージでは、文学というのは激辛料理とか腐敗臭のするフルーツに近い。異常・極端・珍奇であり、だからこそ人の関心を引く。ついつい挑戦してみたくなる。最初は抵抗感もあるが、あんがい美味しいかもしれない。やみつきになるかもしれない。
ジャンル小説というのは、ファストフードやファミリーレストラン、あるいは腕が確かで人の好いシェフが切りもりをするビストロで食事をするようなもので、それぞれに満足の水準は保証されている。期待を激しく裏切るようなことは、皆無と言わないまでも、あまりない。心安らかに楽しめる。しかし、逆に「なんじゃ、こりゃあ」と吃驚仰天なんてこともない。もちろん、ときには「はじめての触感」みたいな嬉しいサプライズはあるだろう。しかし、思わず箸を落とす、あるいは箸を投げるなんてことはない。
文学の場合、激辛の奥に脳が痺れるような滋味があったり、腐敗臭だと思っていたものが夢心地へと誘う芳香だったりということもありうる。まあ、ただひたすら辛いだけのカレーだったり、ほんとうに腐っている果実だったりというリスクもありますが。本書では、ぼくが身をもって挑戦をし、「こりゃすごい」「ほかで味わったことがない」「もっと食べたい」と驚嘆した、激辛キュイジーヌや怪奇フルーツを紹介している。みなさまのお口にあうかどうかは保証のかぎりではないけれど、マイルドで口あたりのよいものものに少々飽きてきたというむきには、きっと参考にしていただけることと思う。
(次ページに続く)
文学はなんでもあり。ふつうじゃ考えつかないことを平気でやる。手加減なしに無茶をする。天衣無縫破天荒御意見無用である。どうせ読むならそういうものを読みたい。
ぼくは、ジャンル小説もだいぶ読むし、べつに文学のほうが高級だとか上等だなどと思っちゃいない。これは文学だとかこれは大衆小説だとかいう区別なんて、くだらないことだろう。しょせんはマーケティング上のことにすぎない。
それをわかったうえで、あえて言う。文学こそいちばんのエンターテインメントだ。
たとえば、無差別級の小説王者決定戦を開催すれば、SFやミステリからも有力選手がエントリーしてくるだろう。具体的に名をあげるなら、スタニスワフ・レム『天の声』、G・K・チェスタトンの『木曜の男』といったあたりだ。この両作品は、ジャンル内部でも傑作の呼び声が高い。しかし、そのいっぽうで、「『天の声』はSFの枠組みを超えてしまった」とか、「『木曜の男』はミステリの作法から逸脱している」という声も聞こえる。これは称讃の言葉であると同時に、とまどいの表明でもある。ジャンルというのは求心的なものであり、特定のジャンルに馴染んだ人たちは、作品そのものの価値以上に「ジャンル小説らしさ」を愛している。ジャンルごとに、アイデンティティというか、本質というか、ジャンルをジャンルたらしめているものがある。
文学にはそんなものはない。枠組みもないし、作法も決まっていない。本質や原点や目的なんてヤボなことはいわない。もし、SFリーグがレムはちょっと困るというなら、文学へと移籍していただきましょう。ミステリ・ギルドがチェスタトンを扱いかねるというなら、文学が席を用意します。まあ、SFファンもミステリ愛好家も、そんなもったいないことは言わないでしょうが。ぼくだって文学側のヘッドハンターじゃないしね。
まあ、やっかいなのは、SFやミステリの世界にフェティッシュなファンがいるように、文学にも偏執的マニアがいることで、この連中が、ときおり「こんなものは文学じゃない」などと妄言を吐いたりする。そういうバカどもの声が大きいものだから、文学はクラくてダサくてイモいものだと、世間から誤解されてしまう。
だいたい、ラブレーが『ガルガンチュアとパンタグリュエル物語』でお尻の穴までさらけだし、ロレンス・スターンが『トリストラム・シャンディ』で無法のかぎりをつくし、ジェイムズ・ジョイスが『ユリシーズ』で良俗や常識を徹底的に踏みにじってきた――それが文学の系譜なのである。アヴァンギャルドなのだ。パンクなのだ。これでいいのだ。やりたいほうだいの世界で、いまさら上品ぶったり偉ぶったりするのは烏滸の沙汰である。
文学は、書くほうがなんでもありなら、読むほうだって自由で気ままだ。べつにルールやマナーがあるわけではない。高級レストランで食事をするわけじゃないのだ。むしろ、ぼくのイメージでは、文学というのは激辛料理とか腐敗臭のするフルーツに近い。異常・極端・珍奇であり、だからこそ人の関心を引く。ついつい挑戦してみたくなる。最初は抵抗感もあるが、あんがい美味しいかもしれない。やみつきになるかもしれない。
ジャンル小説というのは、ファストフードやファミリーレストラン、あるいは腕が確かで人の好いシェフが切りもりをするビストロで食事をするようなもので、それぞれに満足の水準は保証されている。期待を激しく裏切るようなことは、皆無と言わないまでも、あまりない。心安らかに楽しめる。しかし、逆に「なんじゃ、こりゃあ」と吃驚仰天なんてこともない。もちろん、ときには「はじめての触感」みたいな嬉しいサプライズはあるだろう。しかし、思わず箸を落とす、あるいは箸を投げるなんてことはない。
文学の場合、激辛の奥に脳が痺れるような滋味があったり、腐敗臭だと思っていたものが夢心地へと誘う芳香だったりということもありうる。まあ、ただひたすら辛いだけのカレーだったり、ほんとうに腐っている果実だったりというリスクもありますが。本書では、ぼくが身をもって挑戦をし、「こりゃすごい」「ほかで味わったことがない」「もっと食べたい」と驚嘆した、激辛キュイジーヌや怪奇フルーツを紹介している。みなさまのお口にあうかどうかは保証のかぎりではないけれど、マイルドで口あたりのよいものものに少々飽きてきたというむきには、きっと参考にしていただけることと思う。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする