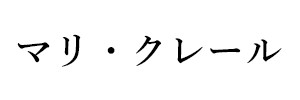書評
『描写の芸術―一七世紀のオランダ絵画』(ありな書房)
書き換えられた絵画史――フーコーの『言葉と物』の影の下に
美術史プロパーにとってはどうか知らないが、美術をも含む表象史全体の大きな枠組からヨーロッパ文化を眺めている人間にとって十七世紀オランダは興味津々たる素材がお互いにからみ合って文目(あやめ)も分かぬ、途方もなく豊かな相手である。ツヴェタン・トドロフの最新刊『日常礼讃』また、この主題だ。たとえば、目に見える世界の下に不可視の世界が否定し難く存在していたことを啓示的に指し示した顕微鏡はこの世紀のオランダが発明し、洗練していった道具である。中沢新一氏の『雪片曲線論』が巧みなレトリックで説得したように、たとえばスピノザの哲学はこのオランダのレンズ光学、レンズ研磨の手工業とは切り離して考えられない。哲学でそうだとすれば、細密への顕微鏡的という他ない強迫観念に煮つまっていかざるをえないリアリズムの病に狂っていった近代表象構造の研究家が、顕微鏡のレンズ光学の消長に無関心であってよいはずがないだろう。
ましてや十七世紀オランダは世界一と呼ばれた植物園をライデン市に抱える博物学、分類学の一大中心地である。西欧自然学の近代の火つけ役となるのは奇態にもチューリップ狂いだが、その拠点もオランダ低湿地地域であった。今日オランダと言えば風車下、風にそよぐチューリップマニア、千紫万紅、色とりどりのチューリップの姿が思いだされるわけだが、実にそれこそ表象の十七世紀、ものを見、もっとよく見るために腑分けし、整理することに狂った十七世紀オランダの名残りなのだ。しかも早々とこのチューリップの投機市場に暴落が発生した。近代最初の暴落事件で、このことがはっきりさせたのは株とか紙幣とかいう記号、メタ記号で動いている「信用」の経済機構のあやうさに他ならない。
オランダが早々と身にしみて理解した表象経済の、このいい加減さをヨーロッパが大きな規模で知るには十八紀初頭、ジョン・ローの国家的詐欺事件と南海泡沫事件の惨劇を待たねばならない。
あまり知られていないオランダ十七世紀を表象史のほうから見るとほぼそういうことだ。近代市場経済の出発点となったオランダにはとにかく未曾有の規模で物量が集散した。物量の膨満はそれに見合う名称や表現の増大を要求するから、語彙、表現の豊かさをうみ、表象作用自身の自己反省もうむ。言葉が何故言葉たりうるか、紙幣が何故紙幣たりうるかの自己検証をもうむだろう。十七世紀、ことにオランダの十七世紀にだけ焦点を絞り、表象として映画システムを自己反省しようとしているピーター・グリーナウェイのすばらしい着眼は、オランダ人プロデューサー、キース・カサンダーやオランダ人美術監督ベン・ヴァン・オスを通して正しく眺められた十七世紀オランダへの認識に発している。
まったく同じ問題は十七世紀後半から一世紀半かけてヨーロッパ全表象シーンに生じた。そのことを徹底して見たのがフーコーの『言葉と物』である。博物館も紙幣も、「言葉と物」とが一致する理想の普遍言語も、そして画布の上に現実もどきを虚構する絵画という記号も実は「表象」という一貫したマクロ・スケールから論じてみない限り、理解できない。それがフーコーの影響下に新歴史派と対応して出発したアルパースおよび彼女が編集する雑誌『リプリゼンテーションズ』周辺の人たちの大きな認識だ。レンズや地図から普遍言語まで扱う中でワン・オヴ・メニーとしての位置しか、狭義の絵画は占めえない。いわゆる「新美術史(ニューアート・ヒストリー)」の蜂火となった書が『描写の芸術』だ。
絵だけが表象であり、ファイン・アートであると思いこんでいる旧套美術史家たちへの侮蔑の本として極めて貴重である。そうしながら、いかにもというレンブラントなんかに一杯ページを割いているところが、オランダのそうしたダイナミックな表象混淆を先駆けた十七世紀プラハについて徹底した表象分析をやるダコスタ・カウフマンなどに比べるといかにも「過渡期」的だけれど、時代を先駆けた革命的一著であることは間違いない。そのことが全然分かっていない「訳者あとがき」が無残である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする