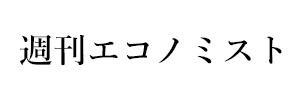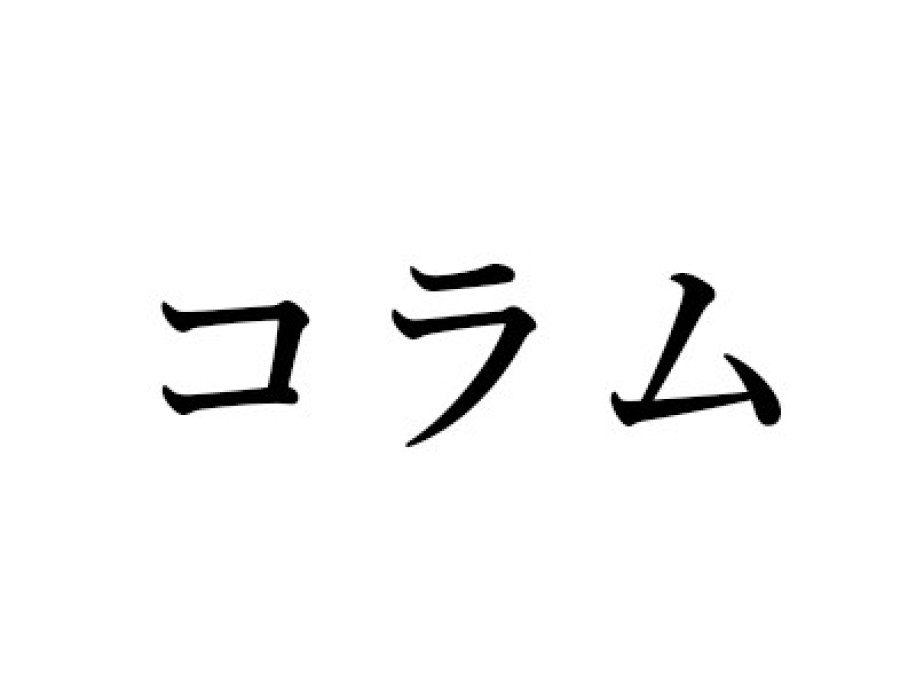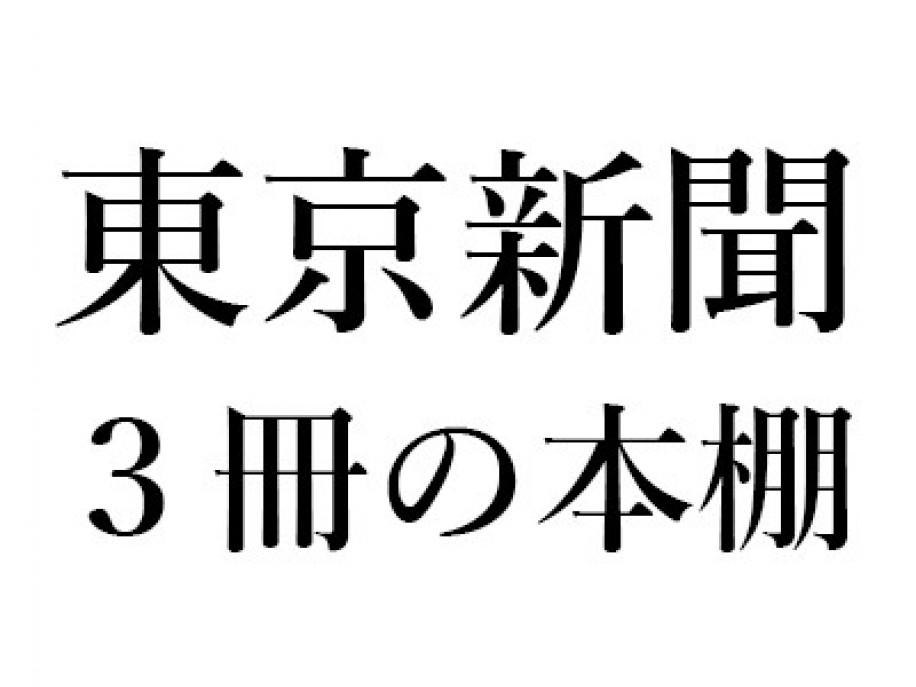書評
『ROE最貧国 日本を変える』(日本経済新聞出版社)
ROEを資本生産性と定義 「稼ぐ力」の強化を求める
「日本型スチュワードシップ・コード」や「日本版コーポレートガバナンス・コード」が相次いで提示され、ROE(自己資本収益率)という言葉がここにきてがぜん注目されるようになった。本書を貫く問題意識は、「山を動かす」。このところ日本企業の株価は大きく上昇したが、欧米諸国と比べて株式市場の長期パフォーマンスの低迷ぶりは依然として際立っている。この背景にあるのが、「世界最貧国」水準の日本の上場企業のROEだ。ROEの長期分布を見ると、分布の山の頂点にある最頻値はROE4~5%でしかない。このことがマクロにもミクロにもさまざまな問題の温床となってきた。最頻値を世界標準の12~13%まで10ポイント近く上昇させる。本書はその原因にさかのぼったうえで、将来に向けた骨太の指針と方策を提示している。
ROEは「資本効率」として語られることが多いが、本書は「資本生産性」という言葉にこだわる。運用パフォーマンスの向上という投資家目線で見ればROEは「資本効率」に過ぎない。ROEは株主にとって重要である以上に、企業経営と国民経済にとって重要な生産性指標である。品質や労働生産性の高さがかつての日本企業の競争力を支えたように、これからは資本生産性を高めることでグローバルな資金獲得競争に伍し、事業基盤を強固にしなければならない。これが本書の認識だ。従来の株主・金融サイドに立った議論は、「じゃあ、どうしたらよいのか」というアクションについては「何とかしろ」で終わってしまう。自社株買いや配当などの手っ取り早い株主還元策ばかりが注目されるという成り行きだ。
ROEを事業マージン、総資産回転率、財務レバレッジに3分解して日米欧を比較した議論が興味深い。日本の上場企業の回転率は欧米よりもむしろ高く、レバレッジにもそれほど大きな格差はない。要するにもうかっていないのである。資本構成や株主還元といった財務的工夫、社外取締役などの体制整備、法人税やのれん代償却といった制度上の対処は根本的な解決にならない。資本生産性向上の焦点は、個別事業の稼ぐ力という事業経営そのものにある。このところROEに関する論説や書籍は枚挙にいとまがない。世の中が注目するほど「玉」よりも「石」がずっと多い玉石混交状態になるのが世の常である。手っ取り早くROEを改善させるための指南書があふれる中で、本書は最も地に足の着いた議論を展開している。
ALL REVIEWSをフォローする