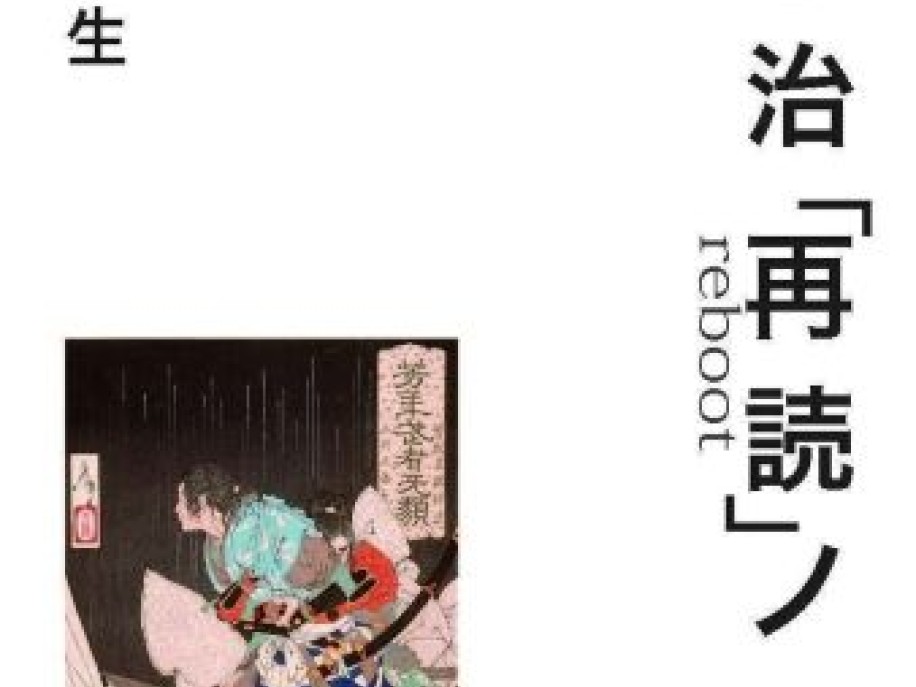書評
『性のタブーのない日本』(集英社)
エロスの匂いに惹かれ、本質に無関心
日本人は色好みか? この問いの答えはイエスでありノーだ。たとえば日本のメディア空間はきわめて「性的」である。人は死ぬまで性交渉をすべきであると煽(あお)る週刊誌広告が三大紙に掲載される。隣には性的機能を高めるサプリメントの広告。欧米の一流紙ではあまり見かけない光景だ。しかしその一方で、若者の婚姻率や性交渉経験率は年々低下しているという。セックスレスなる現象も、日本に特有とされている。性犯罪率は国際的にも最低水準で、それは結構なことなのだが、電車での痴漢被害は異常に多い。橋本治による本書は、こうした謎に明快な答えを与えてくれるわけではない。橋本は日本文学の古典をひもときながら、日本人の性意識がいかに特異なものであるかをユーモラスに論じている。その特徴をひとことで言えば(帯にもある通り)「タブーはないが、『モラル』はある」ということになる。
どういうことか。聖書にあるモーゼの十戒には「汝姦淫(なんじかんいん)するなかれ」とある。自慰行為の禁止も聖書が起源だ。つまり不倫や、生殖に結びつかない性行為は罰せられるべきタブーとされる。このように欧米のキリスト教圏には性にまつわる禁忌が多いが、ひるがえって日本はどうか。
『古事記』に記された「国津罪(くにつつみ)」には、近親姦や獣姦が挙げられている。しかし本居宣長の解釈によれば、これらは罰せられるべき罪(=タブー)ではなく、祓(はら)われるべき穢(けが)れ(=モラル)ということになる。ここにはアダムとイブが原罪を犯して楽園を追放される創世神話と、イザナギとイザナミが出会ってすぐに子作りを開始する『古事記』との違いがみてとれる。
ではなぜ、人は性を描くのだろうか。
本書でも述べられているように、橋本のデビュー作は女子高生の一人称小説『桃尻娘』だ。下ネタはあってもエロくはない本書は評判となり、にっかつロマンポルノで映画化された。映画化交渉のエピソードが笑える。エロがない小説をなぜあえて成人映画にするのか尋ねた作家に、制作側は「一般向けにしちゃうと客足が落ちる」と答えたという。そう、日本人は「エロスの匂い」に惹(ひ)かれるがエロスの本質には関心がないのである。ここにもタブー意識の希薄さがみてとれる。
最近開催された春画展が大いに人気を博したことは記憶に新しいが、平安期にも「小柴垣草紙」なる春画があった。『源氏物語』はもとより、『万葉集』から『古今和歌集』にいたるまで、あるいは連歌から俳諧の歴史においても、表現のいたるところにエロスは横溢(おういつ)していた。それは人間の生理であり、そこに生理があるのはしょうがない。ただ日本人にとっても「性」は「晴」(ハレ)に属する。現実生活の中でフィクションに「晴」を夢みようとするならば、それが描かれるのはやっぱり「しょうがない」のである。
本書を読みながら、昨年話題となった某アーティストの「わいせつか否か」を巡る騒動を連想していた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年)。古くはチャタレイ夫人裁判にはじまるわが国の「わいせつか芸術か」の議論がどこか滑稽(こっけい)にみえるのは、そこに一切の超越的なタブー意識が介在していないことによるのではないか。猥褻(わいせつ)性を巡る法律の文言解釈が醸し出すいびつな「笑い」は、アメノウズメの裸踊りが喚起した神々の哄笑(こうしょう)よりも「近代的」なぶんだけユーモアに欠けるように思われる。
ALL REVIEWSをフォローする