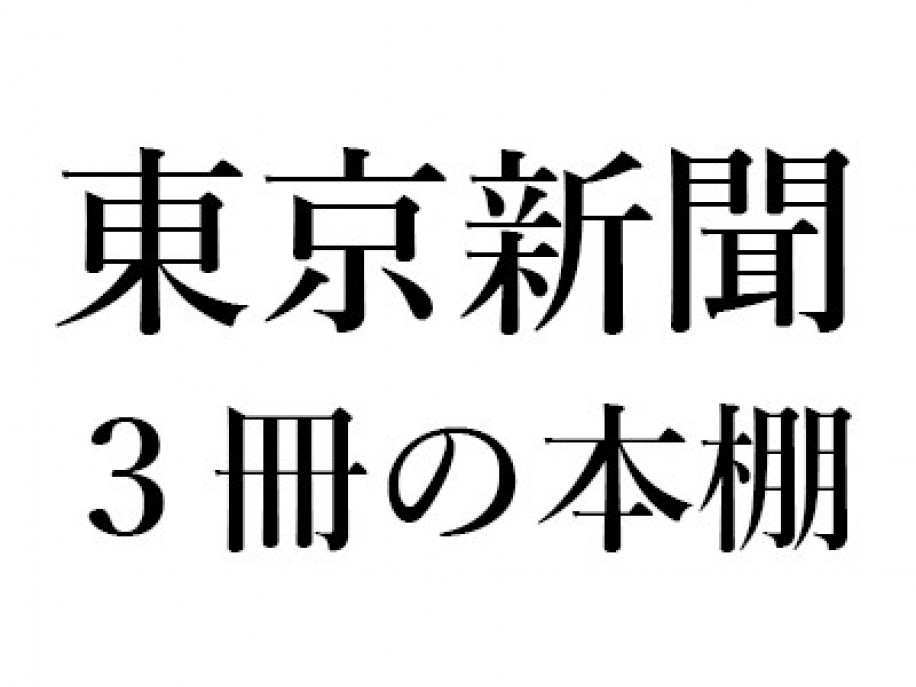書評
『幸田家のことば: 知る知らぬの種をまく』(小学館)
家族の歴史をつなぐ切れば血の出る日本語
そもそも私が幸田家の言葉に強烈な印象を受けたのは、幸田文(あや)の随筆「あとみよそわか」だった。幸田露伴の次女として生まれた文が四十四歳のとき著した一編で、父から受けた躾(しつけ)について綴(つづ)るのだが、文中に登場するのが「あとみよそわか」。この呪文めいた奇妙な言葉は、拭き掃除を終えた娘に父が放ったもの。“いったん振り返って、自分の行いに粗相がないか気を配れ”という警句なのだが、掃除を終えて安堵(あんど)した背中に浴びせるところが、容赦ない。あるいは、文に語ったという「おまえは赤貧洗うがごときうちへ嫁にやるつもりだ」。家庭のなかで語られる愛情表現のきびしさに思わず襟を正す。
本書は、その幸田家に伝わる四十ほどの言葉について書かれている。曽祖父、幸田露伴から、祖母の文、母の青木玉を通じて引き継がれた言葉の数々は、玉の娘である著者の実生活や記憶のなかに生き続けている。ただし、それらはほかではめったに聞かない。
「一寸延びれば尋延びる」
「小どりまわし」
「桂馬筋」
「とやせん かくやせん と思うときはせぬことぞよき」
「あなたのお庭に木が何本」
「魚身鶏皮」
「かけかまい」
「努力加餐」
「猫根性」
……ごく短い言葉の、なんという切れ味。本書は、これらの言葉の意味や背景を、家族の日常や祖母や母の随筆などを交えながらていねいに語るのだが、知れば知るほど言葉にこもる人情の機微、世間の道理にうならされる。びしりと一本筋が通る精神性は、学問芸術礼儀礼法を鍛え上げた露伴によるもの。いずれも、切れば血の出る日本語だ。
言葉は家族をつなぎ留める役割をも果たしている。
基準となるのは、自分がそれらのことばを残したいか、使いたいかどうかに一(いつ)にかかっている。(中略)自分が抱えている語彙はこまめにメンテナンスが必要で、理想を言えば、常にことばの手置きをよくしておきたいと思う。
温故知新や愛着にほだされて使うのではない。現在を生きながら言葉の風通しを心がけようというのだ。耳慣れなくとも、口の端にのせることによって言葉は命脈を保つのだと教わる。
幸田家での二大ほめ言葉は、「出ず入らず」と「程がいい」。前者はしばしば文が使っていた言葉で、重宝とか都合のいいものを指す。とはいえ、物選びの態度にたいする戒めが込められているのも幸田家ならでは。高級品は良くて当たり前、面白さに気をとられては不釣り合い、肩に力の入らない収まりのよさを身上とする。比較的馴染みのある「程がいい」という言葉も、「出ず入らず」という補助線を引けばいっそう生き生きとする。
幸田家ならずとも、使ってみたい言葉がたくさんある。使うあてもないのにむやみに物を抱えこむ様子を指す「持ったが病」。自分の欲のありかを見据える「欲と道連れ」。気遣いや思慮を示す「かけかまい」。親身なひとの手前勝手は「猫根性め」などと咎(とが)めてもみたい(「ねこっこんじょう」と発音するらしい)。
言葉が招き入れるおびただしい家族の記憶。言葉そのものの力のみならず、幸田家に生きたひとびとを敬慕する気持ちに何度となく胸が熱くなった。
ALL REVIEWSをフォローする