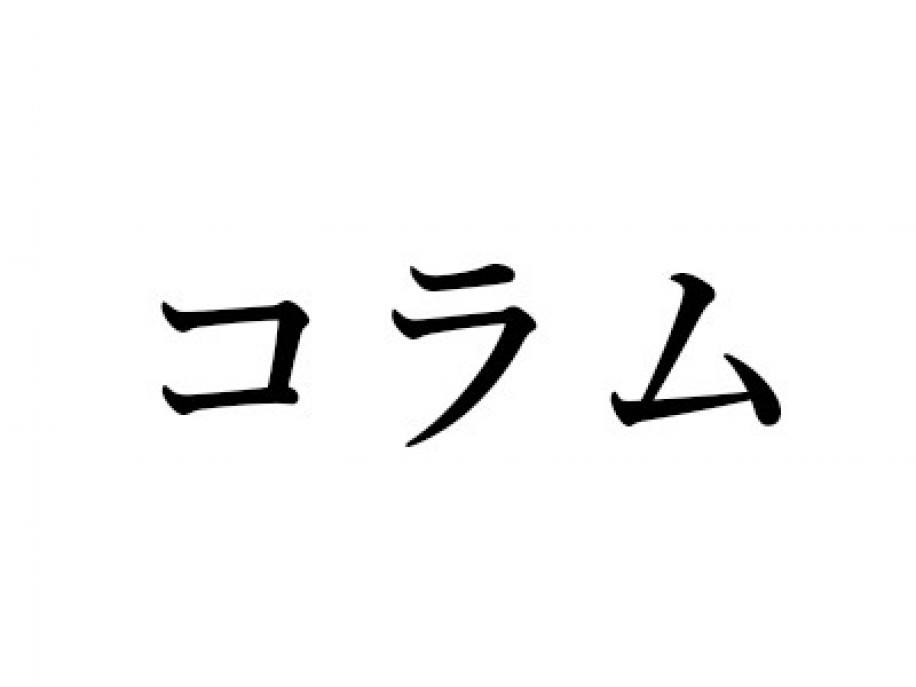書評
『奇縁まんだら』(日本経済新聞出版社)
本物の良書は作者の体温を感じさせる。本書はその好例である。内容が濃密で面白い。しかもその面白さはゴシップ的な内容によるものではない。じっさい、それらしい記述は見あたらない。むろん、登場してきた作家の思いがけない一面やこれまで知られていない事実はたくさん出てくる。しかしそれだけでなく、作家同士の付き合い方のほうも興味を引く。
紹介された文学者や芸術家は幅が広い。明治時代にデビューした島崎藤村から、四年まえに亡くなった水上勉にいたるまで二十一人にのぼる。奇縁とはうまい表現で、一つ一つの出会いにはみな物語があり、ドラマがある。
臨場感溢れる描写にまず圧倒された。とうに鬼籍に入った作家たちがまるで生き返ったように語り、笑い、動き回っている。しかも過剰な文飾はいっさいない。味のある筆致で淡々と綴られている。
文壇周辺の人から聞いた話も興味をそそる。谷崎潤一郎の妻千代の譲渡事件について、第三の男である和田六郎の子息和田周から聞いた証言は驚くものばかりだ。
小説が好きな読者なら、誰もが作家たちの素顔に興味を持つであろう。とりわけ優れた作品を読んだとき、何が作家にそう書かせたか、その感情世界が知りたくなる。だが、大正、昭和前期の作家たちはいまや遙か昔の人となった。単に彼らの生い立ちや生涯の歴史を知りたいなら、評伝を読めばよい。しかし人物伝は生の声が伝わりにくい。
作家の伝記は後世の人によって書かれることが多い。本人を直接知らない場合、第三者の証言をもとに作家像を復元するしかない。その場合、歳月に埋没された事実を掘り起こすことができても、個々の場面での感情の揺らぎは描きにくい。写真から内心の動きを読み取れないのと同じである。だから、私は「正確な」評伝よりも、彼らを描いた小説のほうを好む。
さすがに『かの子繚乱』の作家は、文士たちの表情を生き生きと活写している。映画のせりふを思わせる会話のやりとりは、実況中継のようで生々しい。抜群の記憶力というより、天賦の文章術がなせる技であろう。
本書は文壇の逸話を紹介する書物であると同時に、著者自身の交友記でもある。もともと友だちとは鏡のようなものだ。どのような人と付き合うかはその人の好みや人柄を映し出す。ましてや、知人や友人について書くことは、自らをさらけ出すことでもある。重病中の遠藤周作が編集者に支えられながら去っていく姿を見て、思わず泣いてしまったというくだりは、著者の面目が躍如としていて胸を打つ。過去の作家たちの思い出は単なる回想ではない。書き手の豊かな人間性が行間に滲み出ている。
文章にはつやがあって、ユーモアがある。そのユーモアも受けを狙うものではなく、ごく自然な文章の流れのなかでわいてきたものである。河盛好蔵は晩年、フランス語の源氏物語を書きたいと著者に打ち明けたことがある。半年後、「やっぱりフランス語で書くのはもう自分では遅すぎる。私よりずっと若いうまい人を紹介します」と言って、梅原龍三郎氏の令嬢で八十二歳の嶋田紅良(こうら)を推薦した。この辺りを読むと、おかしくて思わず吹き出してしまった。
横尾忠則の手になる挿絵も見逃せない。鮮やかな色彩は個々の作家の特徴を見事にとらえたのみならず、人物の表情の後ろにあるものまで描き出している。文章ともうまく調和が取れていて、両方を交互に眺めるのはじつに楽しい。
【この書評が収録されている書籍】
紹介された文学者や芸術家は幅が広い。明治時代にデビューした島崎藤村から、四年まえに亡くなった水上勉にいたるまで二十一人にのぼる。奇縁とはうまい表現で、一つ一つの出会いにはみな物語があり、ドラマがある。
臨場感溢れる描写にまず圧倒された。とうに鬼籍に入った作家たちがまるで生き返ったように語り、笑い、動き回っている。しかも過剰な文飾はいっさいない。味のある筆致で淡々と綴られている。
文壇周辺の人から聞いた話も興味をそそる。谷崎潤一郎の妻千代の譲渡事件について、第三の男である和田六郎の子息和田周から聞いた証言は驚くものばかりだ。
小説が好きな読者なら、誰もが作家たちの素顔に興味を持つであろう。とりわけ優れた作品を読んだとき、何が作家にそう書かせたか、その感情世界が知りたくなる。だが、大正、昭和前期の作家たちはいまや遙か昔の人となった。単に彼らの生い立ちや生涯の歴史を知りたいなら、評伝を読めばよい。しかし人物伝は生の声が伝わりにくい。
作家の伝記は後世の人によって書かれることが多い。本人を直接知らない場合、第三者の証言をもとに作家像を復元するしかない。その場合、歳月に埋没された事実を掘り起こすことができても、個々の場面での感情の揺らぎは描きにくい。写真から内心の動きを読み取れないのと同じである。だから、私は「正確な」評伝よりも、彼らを描いた小説のほうを好む。
さすがに『かの子繚乱』の作家は、文士たちの表情を生き生きと活写している。映画のせりふを思わせる会話のやりとりは、実況中継のようで生々しい。抜群の記憶力というより、天賦の文章術がなせる技であろう。
本書は文壇の逸話を紹介する書物であると同時に、著者自身の交友記でもある。もともと友だちとは鏡のようなものだ。どのような人と付き合うかはその人の好みや人柄を映し出す。ましてや、知人や友人について書くことは、自らをさらけ出すことでもある。重病中の遠藤周作が編集者に支えられながら去っていく姿を見て、思わず泣いてしまったというくだりは、著者の面目が躍如としていて胸を打つ。過去の作家たちの思い出は単なる回想ではない。書き手の豊かな人間性が行間に滲み出ている。
文章にはつやがあって、ユーモアがある。そのユーモアも受けを狙うものではなく、ごく自然な文章の流れのなかでわいてきたものである。河盛好蔵は晩年、フランス語の源氏物語を書きたいと著者に打ち明けたことがある。半年後、「やっぱりフランス語で書くのはもう自分では遅すぎる。私よりずっと若いうまい人を紹介します」と言って、梅原龍三郎氏の令嬢で八十二歳の嶋田紅良(こうら)を推薦した。この辺りを読むと、おかしくて思わず吹き出してしまった。
横尾忠則の手になる挿絵も見逃せない。鮮やかな色彩は個々の作家の特徴を見事にとらえたのみならず、人物の表情の後ろにあるものまで描き出している。文章ともうまく調和が取れていて、両方を交互に眺めるのはじつに楽しい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする