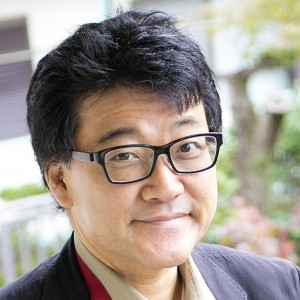書評
『フロベールの鸚鵡』(白水社)
ジュリアン・バーンズ(Julian Barnes 1946- )
イギリスの作家。辞典の編纂や、新聞の文芸欄、テレビ批評、レストラン批評などを手がけながら、小説を書きはじめる。Metroland(1980)が長篇第一作。『フロベールの鸚鵡』(1984)は、筆名で書いたミステリを別にすると第三長篇にあたり、いくつもの文学賞に輝いた。そのほかの著作に『太陽を見つめて』(1986) 、『10 1/2章で書かれた世界の歴史』(1989) 、『ここだけの話』(1991) 、短篇集『海峡を越えて』(1996)などがある。introduction
ぼくにとって、ジュリアン・バーンズは手放しで「大好き」と言える作家じゃない。作品の仕かけや、ちりばめられた素材のあれこれには、よくぞまあと舌を巻くけれど、いかにもディレッタントなかんじが気に入らない。ディレッタントといえばボルヘスだってそうだけれど、あのひとには幼児か老人のひたむきさがあって、そこがたまらなく好き。それに対してバーンズは、どこから見ても立派な大人だ。高橋源一郎氏がバーンズの作品を「サーヴィス満点の純文学」と賞していて、うまいこと言うなと思ったが、ぼくはそのサーヴィスがときどき煩わしくなる。まあ、これはイチャモンにすぎず、そう言われてもバーンズはちょっと眉をあげるだけで受けながすことだろう。小癪ではあるが、やっぱり本当の大人にはかなわない。▼ ▼ ▼
レイ・ブラッドベリに「親爺さんの知り合いの鸚鵡」という短篇がある。親爺さんとはヘミングウェイのことで、彼がハバナで過ごした晩年、いきつけのバーで飼われていた鸚鵡に、未発表の作品を語って聞かせていた。ヘミングウェイの死後、その絶筆は鸚鵡のなかにひっそりと埋もれることになったが、ある日、この鸚鵡が誘拐されてしまう。関係者は騒然。未刊のヘミングウェイを救出すべく、文学探偵ブラッドベリが捜査に乗りだす。ぼくはこの作品が妙に気に入っているのだ。鸚鵡というのがなんだかおかしい。
小説と鸚鵡というのは組みあわせやすい題材なのか、ジュリアン・バーンズも『フロベールの鸚鵡』という長篇を書いている。この作品が翻訳されたときは、早とちりの期待をしたものだ。一羽の鸚鵡が突如、フローベルの失われた傑作を語りだしたら……。いまさら未刊の作品が発見されて大騒ぎになる作家なんてそうそういるはずもないが、フロベールは確実にそのひとりだ。なんたって『ボヴァリー夫人』、なんたって近代リアリズムの巨匠である。もちろん、フランス作家にとっては迂回することのできない伝統だ。
しかし、ぼくの思惑は大はずれ。表題の「鸚鵡」は剥製だし(フロベールより先に死んでいたのだ)、バーンズはイギリスの作家だから、ヘミングウェイ-ブラッドベリのような、素直な文学的血縁もない。まあ、それでも、偉大な作家の謎に関わる鸚鵡を捜しだす文学探偵の話だから、面白くないわけがない。
探偵役のジェフリー・ブレイスウェイトは、イギリス人の医者で、かつては小説を書こうと試みたこともある。彼は、フロベールゆかりの街ルーアンで、奇妙な事実に遭遇する。『純な心』を書くにあたって、フロベールは一羽の鸚鵡の剥製をルーアン博物館から借りだしたという。イメージを得るため、執筆中ずっと机のうえに置いていたらしい。ブレイスウェイトは、市立病院に併設された博物館で、この鸚鵡が展示されているのを見るが、あとで入ったフロベール邸の跡地に建てられた記念館にも、鸚鵡が展示されている。はたして、どちらが本物なのか?
ここまでが第一章である。第二章は、まるまるフローベルの年譜にあてられる。①普通のバイオグラフィ、②兄弟や友人の死・退学処分・病気・失敗・破産などを強調した年譜、③フロベール語録を時系列でまとめたもの――という三元構成が楽しいが、このなかにも鸚鵡の謎を解くカギはない。
第三章では、新しい発見がある。しかし、発見者はブレイスウェイトではなく、彼がふとしたことで知り合ったアメリカの学者である。それにしても、「イギリスの服を買って着こんでいるが、どう見てもイギリス人には見えない。彼のようなアメリカ人は、たとえ天気晴朗であっても、この町ではいつなんどき雨が降るともしれないと心得て、ロンドンではかならずレインコートを着るものと決めてかかっているのである」という評は、フロベールばりの辛辣さではないか。こうした仕かけが、さりげなくちりばめられているのが、この作品の愉快なところだ。
さて、学者先生が見つけたのは、フロベールとイギリス女性との間に交わされた書簡。われらが文学探偵は、文豪の秘められたる情事を知りたくて駆けつけるが、あろうことか問題の書簡はすべて焼かれたあと。手紙を焼きすてるのがフロベールの意志であり、自分はそれに従っただけだというのが、アメリカ人の釈明である。ブレイスウェイトの怒りたるや殺意をはらむほどだが、はたしてフロベールの人生の隅々まで掘りかえそうという、彼の情熱は正当のものだろうか? フロベール自身は、「死は芸術家個人を消滅せしめて作品を作者から解放するものである」と言っているのに。
ここまで読んでくると、鸚鵡の謎をめぐる推理小説的興味は脇にそらされて、小説のなりたちについての疑問が浮上してくる。作品を読むときには作家自身はどうでもよく、綴られた言葉だけを問題とすべきだ。ならば、それこそ鸚鵡が語る言葉でもかまわないではないか。主体を持たない言葉、鸚鵡はその理念形である。もっともブレイスウェイト(作者ジュリアン・バーンズの分身)は、こうした抽象的な議論を採らず、あくまでフロベールの人生とその作品を具体的に反復してみせる。それも章ごとに異なった趣向を凝らして。その自在の手つきたるや、読んでいて舌を巻くばかり。
フロベール動物誌、ボヴァリー夫人の目の色をめぐる議論、鉄道ファンのためのフロベール案内なんてのまで飛びだす。あげくのはてにはフロベールの恋人だったルイーズ・コレがゲスト出演して、赤裸々な告白をしてみせるという趣向。内容的にも、技巧的にも盛りだくさん。楽しい饒舌に魅了されているうちに、いつの間にか、フロベールの生涯も、彼の作品とおなじように物語であり、そのあいだに線を引いてもしかたがないという気分になってくる。その気分をあとおしするのが、ブレイスウェイトの文章のなかにばらまかれている、小説についての蘊蓄である。ツルゲーネフ、スティーブンソン、ウィリアム・ゴールディング、ウラジミール・ナボコフ、レイモンド・チャンドラー、などなど、ジャンルも時代もさまざまな小説家の名前が繰りだされる。
ところでブレイスウェイトも、物語に対して第三者ではいられない。フロベールを真似た『紋切型辞典』を開陳しているうちはまだいいが、そのうち自分の妻の浮気をボヴァリー夫人にだぶらせたりで、なんとなくフロベール作品の登場人物じみてくる。
さて、鸚鵡はどうしたのか。謎はちゃんと解明されるので、ご安心を。鸚鵡はフロベールの遺作を隠していたりはしなかったけれど、真相の裏にあるアイロニーは、まさしくフロベールのものだ。それは読んでのお楽しみ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする