書評
『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所)
フロイトの作った精神分析用語の一つに多元的決定というのがある。夢に登場したいくつかの言葉やイメージをもとにして観念連合を働かせると、それはいくつかの結節点を中心にした網目(テクスト)を形成するが、なかでも糸が何本も出入りしている結節点は、多元的決定の中心点として、情動の負荷がもっとも強く、ある種の光を放つというものである。私はこのイメージが大好きで、自分の理想とする書物の構成として、以前に自著の後書きで取り上げたことがあるが、今回、このイメージにぴったりの本があらわれた。『世紀末異貌』に続く高山宏氏の十九世紀末論、その名も、ずばり『テクスト世紀末』である。
高山氏は、知らぬものとてない猛烈な読書家である。いや、読書家なんぞという旧弊な言葉では物足りない。むしろ、目で、かたっぱしから刺激的な書物を貪(むさぼ)り食う人(デヴォラン)といったほうがいい。さながら、蚕が桑の葉(フーユ)を猛烈なスピードで食べていくように、文字や図版の満載された海外の野心的な研究書のページ(フーユ)を貪り食い、やがて蚕が見事な絹糸のテクスト(繭・まゆ)をつくりあげるように、華麗なるテクストを織り上げていく。つまり、その方法論からして、高山氏の書物は、「テクスト」なのである。
そればかりではない。摂取された先行するテクスト(プレ=テクスト)の孕(はら)んでいた様々なテーマ群は次々と「放埒に連環」し、高山氏の「脳内部でアメーバーのように」拡大していく。氏は拡大するそのニューロン回路のスピードを手が写し得ないのがもどかしいという。これはまさに多元的決定のイメージ、つまりテクスト行為以外の何者でもない。そして、高山氏は、この多元的決定を、この十年ほどのあいだに主として英米で堰(せき)を切ったように出版され始めた図版満載のまったく新しいタイプの世紀末論を素材にして行っているのだから、経糸と緯糸を組み合わせるこのテクスト行為は、そのシニフィアンからして「テクスト世紀末」なのである。
だが、ここまでだったら、それは氏の読者にとっては、すでに前著『世紀末異貌』でおなじみのものである。こんどの『テクスト世紀末』がすごいのは、多元的決定によって生み出された結節点それ自体が、すべて、「テクスト世紀末」に関連していること、すなわち、シニフィアンとシニフィエ、いいかえれば方法論と対象が、ともに同じ構造のもとに相互反射的に構築されているということである。では結節点として氏のニューロン回路に出現した「テクスト世紀末」とは、いったい何なのか。
テクストとはラテン語で textus つまり「織り目、肌理(きめ)」を意味し、転じて、織物のように紡ぎ出された言葉、つまり物語のことを指すようになったが、高山氏の斬新な世紀末観によれば、十九世紀末に、欧米の美術、文学、そしてテクノロジーなどの分野に出現した様々な文化現象は、すべてこのテクスト性(テクスチュアリテ)を、一つの大きなオブセッションにしていたという。
まず、今日では印象派の陰に埋もれて忘れられてしまっているが、世紀末には美術の本流として高い評価を与えられていたイギリスのオリンピアン絵画とフランスの新古典派絵画が召喚される。なぜなら、ギリシャ・ローマの歴史とオリエンタリズムという壮麗な主題を口実にして好んで女性の裸体を描いたこれらのアカデミックな流派は、ほとんどセラミックといっていいほど色白の女性の肌の肌理(きめ)を、画布というテクストの上に重ね合わせようとするテクスト狂いを内包していたからだ。だがもちろん女性の白い肌は、世紀末の古典派にあっては、単にこうしたシニフィアンのレベルでのテクスト性にのみ奉仕しているわけではない。すなわち、ブルジョワの抑圧されたリビドーが、性的に放埒な時代と地域と勝手に思い込んだギリシャ・ローマとオリエントに向かって淫視的一瞥を放つとき、視線の経糸緯糸は、ギリシャの女神・オリエントの女奴隷の裸体に絡みついて、シニフィエのレベルでも、「救済の詩学と緊縛の政治学」というアンドロメダ・チェインのテクストが織りなされていく。
これとまったく同様の現象が、女性の肌を覆うテクスト、すなわち世紀末を華やかに彩る女性の衣装の襞の重なりを妄執のように描き出した風俗画家ティソとあのプルーストにおいても観察される。布地の織りなす襞の細部の描写に淫する絵筆と言葉、いいかえれば「重畳と開示の弁証法に快楽を秘めるテクストが、着衣と脱衣の弁証法にエロティシズムをつくりだす世紀末服飾モードと、間然なく一体化する」。そして、ここでもまた、幾重にも屈折した視線が、さながら刺繍(ししゅう)針のように、ティソのカンヴァスとプルーストの語りを複雑に貫いていく。たとえば、ティソの描いたキャスリーン・ニュートンが振り向きざまにこちらに投げかける視線、あるいは衣装と同時に次々と身分を取り換えていく、『失われた時』のオデットの実態を読み取ろうと、スワンと語り手が投げかける視線。
また、テクストを織りなそうとする欲望とそれを解読しようとする欲望は、同時に周囲の環境へも投げかけられる。すなわち、世紀末のブルジョワや芸術家が所せましと家具や骨董を並べ幾重にもかさなるカーテンを引いた「室内」や、ありとあらゆる商品を一カ所に集め、これに分類と体系の網目をかぶせた万国博覧会と、デパートという開放された閉鎖空間は、アルス・コンビナトリア(結合術)という世紀末のテクスチュアルな強迫観念を典型的に示す心的空間でもあったのである。
そして、この心的空間は、地下鉄や下水道などが網の目のように走る地下世界や、顕微鏡の中ではじめてその繊維構造をあかすミクロの世界といった、テクノロジーの進歩によって初めて人間の目に触れるようになったテクスチュアルなニューワールドとも相互に反射し合って、おのれのテクスト性を確認していく。
そうなのだ。高山氏が次々に召喚していくテーマそれ自体も、まさしく、シニフィアンとシニフィエの二重のレベルでテクスチュアリテを輻輳(ふくそう)し、それが方法論の二重のテクスチュアリテと呼応して無限のテクストのミ・ザ・ナビーム(中心紋)を生み出していく。それはさながらクロード・シモンのめまいを呼ぶヌーヴォー・ロマンのように、一見いかにも断片的に見えながら、その実、全体では壮麗なアンサンブルを構成して、従来の紋切り型の世紀末観をものの見事に反転させることに成功している。
本書は、これまでの高山氏ワールドの集大成であると同時に、テーマと方法論の両面でまったく新しい境地を切りひらいた傑作として、氏の著作の大きな転換点となるだろう。造本も溜息を誘うほど素晴らしい。
【この書評が収録されている書籍】
高山氏は、知らぬものとてない猛烈な読書家である。いや、読書家なんぞという旧弊な言葉では物足りない。むしろ、目で、かたっぱしから刺激的な書物を貪(むさぼ)り食う人(デヴォラン)といったほうがいい。さながら、蚕が桑の葉(フーユ)を猛烈なスピードで食べていくように、文字や図版の満載された海外の野心的な研究書のページ(フーユ)を貪り食い、やがて蚕が見事な絹糸のテクスト(繭・まゆ)をつくりあげるように、華麗なるテクストを織り上げていく。つまり、その方法論からして、高山氏の書物は、「テクスト」なのである。
そればかりではない。摂取された先行するテクスト(プレ=テクスト)の孕(はら)んでいた様々なテーマ群は次々と「放埒に連環」し、高山氏の「脳内部でアメーバーのように」拡大していく。氏は拡大するそのニューロン回路のスピードを手が写し得ないのがもどかしいという。これはまさに多元的決定のイメージ、つまりテクスト行為以外の何者でもない。そして、高山氏は、この多元的決定を、この十年ほどのあいだに主として英米で堰(せき)を切ったように出版され始めた図版満載のまったく新しいタイプの世紀末論を素材にして行っているのだから、経糸と緯糸を組み合わせるこのテクスト行為は、そのシニフィアンからして「テクスト世紀末」なのである。
だが、ここまでだったら、それは氏の読者にとっては、すでに前著『世紀末異貌』でおなじみのものである。こんどの『テクスト世紀末』がすごいのは、多元的決定によって生み出された結節点それ自体が、すべて、「テクスト世紀末」に関連していること、すなわち、シニフィアンとシニフィエ、いいかえれば方法論と対象が、ともに同じ構造のもとに相互反射的に構築されているということである。では結節点として氏のニューロン回路に出現した「テクスト世紀末」とは、いったい何なのか。
テクストとはラテン語で textus つまり「織り目、肌理(きめ)」を意味し、転じて、織物のように紡ぎ出された言葉、つまり物語のことを指すようになったが、高山氏の斬新な世紀末観によれば、十九世紀末に、欧米の美術、文学、そしてテクノロジーなどの分野に出現した様々な文化現象は、すべてこのテクスト性(テクスチュアリテ)を、一つの大きなオブセッションにしていたという。
まず、今日では印象派の陰に埋もれて忘れられてしまっているが、世紀末には美術の本流として高い評価を与えられていたイギリスのオリンピアン絵画とフランスの新古典派絵画が召喚される。なぜなら、ギリシャ・ローマの歴史とオリエンタリズムという壮麗な主題を口実にして好んで女性の裸体を描いたこれらのアカデミックな流派は、ほとんどセラミックといっていいほど色白の女性の肌の肌理(きめ)を、画布というテクストの上に重ね合わせようとするテクスト狂いを内包していたからだ。だがもちろん女性の白い肌は、世紀末の古典派にあっては、単にこうしたシニフィアンのレベルでのテクスト性にのみ奉仕しているわけではない。すなわち、ブルジョワの抑圧されたリビドーが、性的に放埒な時代と地域と勝手に思い込んだギリシャ・ローマとオリエントに向かって淫視的一瞥を放つとき、視線の経糸緯糸は、ギリシャの女神・オリエントの女奴隷の裸体に絡みついて、シニフィエのレベルでも、「救済の詩学と緊縛の政治学」というアンドロメダ・チェインのテクストが織りなされていく。
これとまったく同様の現象が、女性の肌を覆うテクスト、すなわち世紀末を華やかに彩る女性の衣装の襞の重なりを妄執のように描き出した風俗画家ティソとあのプルーストにおいても観察される。布地の織りなす襞の細部の描写に淫する絵筆と言葉、いいかえれば「重畳と開示の弁証法に快楽を秘めるテクストが、着衣と脱衣の弁証法にエロティシズムをつくりだす世紀末服飾モードと、間然なく一体化する」。そして、ここでもまた、幾重にも屈折した視線が、さながら刺繍(ししゅう)針のように、ティソのカンヴァスとプルーストの語りを複雑に貫いていく。たとえば、ティソの描いたキャスリーン・ニュートンが振り向きざまにこちらに投げかける視線、あるいは衣装と同時に次々と身分を取り換えていく、『失われた時』のオデットの実態を読み取ろうと、スワンと語り手が投げかける視線。
また、テクストを織りなそうとする欲望とそれを解読しようとする欲望は、同時に周囲の環境へも投げかけられる。すなわち、世紀末のブルジョワや芸術家が所せましと家具や骨董を並べ幾重にもかさなるカーテンを引いた「室内」や、ありとあらゆる商品を一カ所に集め、これに分類と体系の網目をかぶせた万国博覧会と、デパートという開放された閉鎖空間は、アルス・コンビナトリア(結合術)という世紀末のテクスチュアルな強迫観念を典型的に示す心的空間でもあったのである。
そして、この心的空間は、地下鉄や下水道などが網の目のように走る地下世界や、顕微鏡の中ではじめてその繊維構造をあかすミクロの世界といった、テクノロジーの進歩によって初めて人間の目に触れるようになったテクスチュアルなニューワールドとも相互に反射し合って、おのれのテクスト性を確認していく。
そうなのだ。高山氏が次々に召喚していくテーマそれ自体も、まさしく、シニフィアンとシニフィエの二重のレベルでテクスチュアリテを輻輳(ふくそう)し、それが方法論の二重のテクスチュアリテと呼応して無限のテクストのミ・ザ・ナビーム(中心紋)を生み出していく。それはさながらクロード・シモンのめまいを呼ぶヌーヴォー・ロマンのように、一見いかにも断片的に見えながら、その実、全体では壮麗なアンサンブルを構成して、従来の紋切り型の世紀末観をものの見事に反転させることに成功している。
本書は、これまでの高山氏ワールドの集大成であると同時に、テーマと方法論の両面でまったく新しい境地を切りひらいた傑作として、氏の著作の大きな転換点となるだろう。造本も溜息を誘うほど素晴らしい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
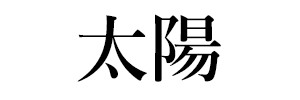
太陽(終刊) 1993年3月
ALL REVIEWSをフォローする



































