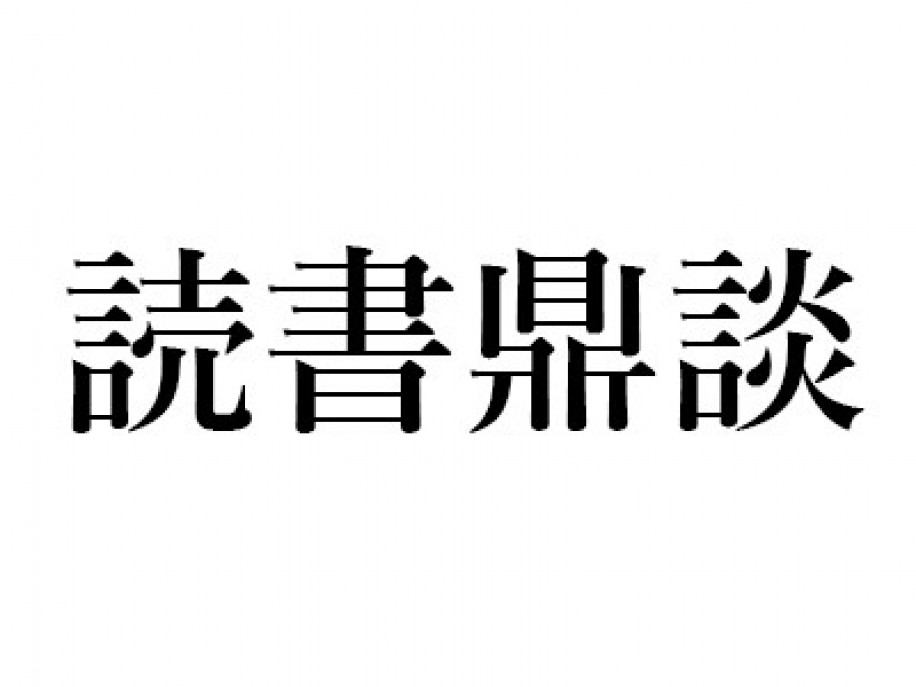書評
『死を見つめる美術史』(筑摩書房)
死体や臨終、哀悼など死についてのさまざまな図像を取り上げ、古代から近世に至るまで、死にまつわる情念がヨーロッパやメソポタミア文明においてどのように表現されたかについて、五つのテーマに分けてわかりやすく紹介されている。
身内を失う悲しみは、かつて胸部や頭部を叩く身振りや、髪のみだれによって表現されていたが、それを変えたのはキリスト教であった。人間の傲慢さを戒め、生のはかなさを悟らせるため、死体の腐敗が美術表現の対象となったが、骸骨が描かれるようになったのは解剖学が誕生した後である。霊魂はつばさを持つ鳥や蝶々として、あるいは裸の赤子として表象されていたが、運命はくるくる回る車輪に象徴されていた。いずれもフィリップ・アリエス『死と歴史』にはない指摘である。
本書は西洋美術を知る上でも役に立つが、東洋の生死観や服喪の慣習、九相の絵解きなどと比較し、東西の共通点や相違点を思い浮かべながら読むと、いっそう興味がそそられる。
【この書評が収録されている書籍】
身内を失う悲しみは、かつて胸部や頭部を叩く身振りや、髪のみだれによって表現されていたが、それを変えたのはキリスト教であった。人間の傲慢さを戒め、生のはかなさを悟らせるため、死体の腐敗が美術表現の対象となったが、骸骨が描かれるようになったのは解剖学が誕生した後である。霊魂はつばさを持つ鳥や蝶々として、あるいは裸の赤子として表象されていたが、運命はくるくる回る車輪に象徴されていた。いずれもフィリップ・アリエス『死と歴史』にはない指摘である。
本書は西洋美術を知る上でも役に立つが、東洋の生死観や服喪の慣習、九相の絵解きなどと比較し、東西の共通点や相違点を思い浮かべながら読むと、いっそう興味がそそられる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする