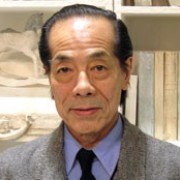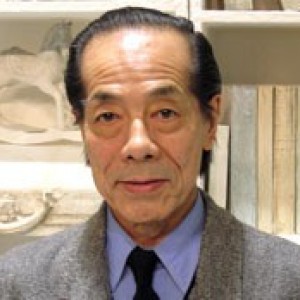書評
『印象派絵画と文豪たち』(作品社)
印象派絵画を好んだ人、嫌った人
モネやルノワールなど、印象派の画家たちが登場した十九世紀後半のパリは、また小説家のゾラや詩人のマラルメが活躍する文芸の都でもあった。世代から言えばロマン派に属する先輩の詩人ゴーティエやボードレールなども含めて、これらの文学者たちは、しばしば美術についても発言し、作品批評や画家たちとの交遊の思い出、あるいは面白い逸話などを書き残している。セルジュ・フォーシュロー『印象派絵画と文豪たち』は、それらの作家、詩人たち二十三人を取り上げ、印象派について語った文章を集めた評論アンソロジーで、印象派受容の歴史を物語る同時代の証言を提供してくれる貴重な資料集となっている。だがそれと同時に、登場しているのがいずれも一筋縄ではいかない「文豪」たちであるだけに、その発言を通じて、彼ら自身の立場や芸術観が浮かび上って来る点がはなはだ興味深い。実際、印象派に対する見方にしても、さまざまである。マネの友人であったマラルメや、モネとルノワールについて見事な文章を残したオクターヴ・ミルボーのように優れた理解を示す文人もいれば、ヘンリー・ジェイムズやイェイツのように印象派にかなり冷淡な立場もある。反対派の極め付けはトルストイで、印象派絵画のみならず、当時の演劇や音楽に対してもあからさまな反感を示している。それは、印象派に対する当時の人々の反応の一面を代表するものであるとともに、それ以上にこのロシアの偉大な文豪の芸術観をよく物語っているといえよう。
また、アンリ・ド・レニエが郷愁をこめて語っているマラルメの「火曜の会」やベルト・モリゾのサロンでの詩人、画家、批評家たちの生き生きとした交遊の模様や、ジョージ・ムアがその『自伝』のなかで回想しているパリ生活の思い出などは、この時代の熱気に満ちた芸術的雰囲気を甦らせてくれる貴重な資料として特筆したい。翻訳は全体としてきわめてなめらかで読み易い。ただ、ゴーティエのマネ論に出て来る「地方色」は「国有色」とすべきであろう。それは当時の絵画理論の基本的概念のひとつだからである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする