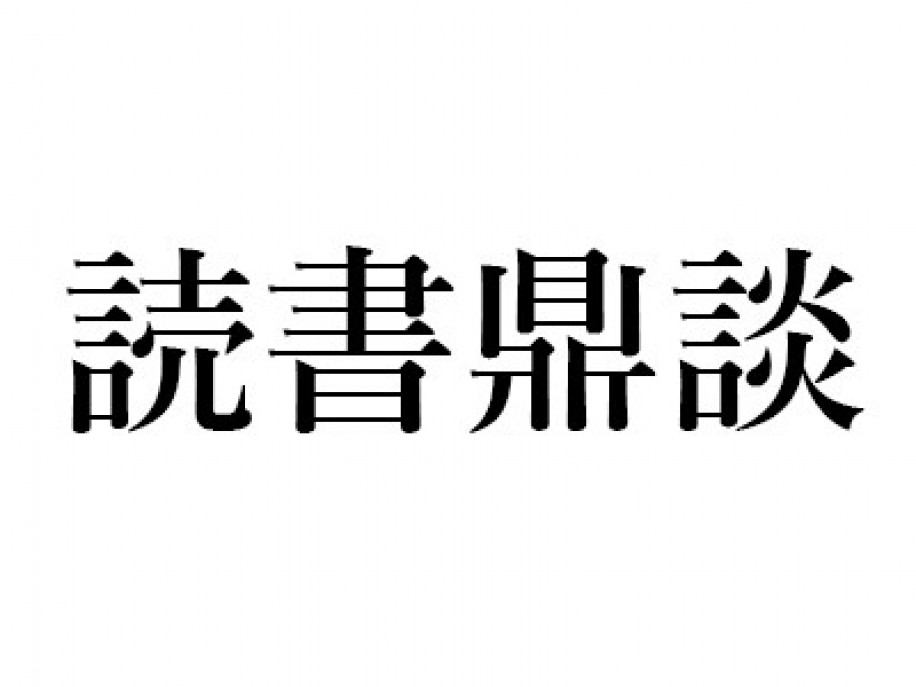書評
『印象派美術館』(小学館)
画題中心の構成、日本人の誤解解く
A また印象派の画集ですか?B まあ、そう言わずに。いままでの印象派画集とは違った観点から編集されたものなんで、日本人が印象派について抱いているイメージが変わると思いますよ。
A どんな観点なんです?
B 白樺派による紹介以来、印象派って「表現」の方に力点が置かれていましたね。
A そりゃそうでしょう。だから印象派っていうんでしょ。
B そうなんですけど、印象派のそうした受け止め方って日本人に特有なんです。印象派が登場したときフランス人は全然違う受け止め方をしたはずなんです。
A どういうことなんです。
B 日本人にとって、画題が花鳥風月・雪月花、あるいは街や村の風俗であることになんの違和感もありませんよね。
A 日本画や浮世絵というのはそういうものなんですから。
B ところが、フランスでは、全然そうではなかったんです。画題といえば、一に歴史、二に歴史で、聖書やギリシャ神話に題材を取った歴史画だけが絵画とされていたんです。いわゆるアカデミーの絵画というやつです。風景画や静物画は位がずっと下でした。
A ということは、印象派が出てきたときフランス人が驚いたのは「描き方」じゃなくて「描かれたもの」だったってことですか?
B その通り。マネの「草上の食事」の裸体も「歴史化」されないで、現代のものとして呈示されたことにショックを受けたんです。
A 印象派は「描かれたもの」に注目して見るべきだということですね。たしかに、そう考えると日本人が印象派をすんなり受け入れたというのもわかります。
B ジャポニズムの問題もそれで見るといいかもしれない。いずれにしろ、この画集は、印象派が「どう描いた」かよりも「何を描いた」かに力点を置いた初めての画集なんです。
A で、どういう風な構成になっているんですか?
B まず画題の違いを示すためにアカデミーの絵画との差をきわだたせてから、テーマ特集という項目をもうけています。「セーヌからノルマンディへ」「印象派の聖地」などで、アカデミーのアトリエから外に出た「外光派」としての印象派を特記した上で、「駅と鉄道」「劇場とファッション」「家族の誕生」「ペットの流行」「オペラ座と競馬場」といった側面に光を当てています。
A たしかに印象派というのはなによりもまず都市風俗画だったということがよくわかります。マネにしろルノワールにしろモネにしろ、当時のパリ風俗を相当細かく描きこんでいる。
B それに、題材に力点を置くと印象派の画家たちの戦略なんかも見えてくる。
A 戦略?
B たとえばマネという画家は印象派の親玉みたいに見られているけれど、自分じゃ印象派などと名乗ったことは一度もなくて、サロン(官展)に当選することだけが望みでした。だから「アプサントを飲む男」という現代パリの風俗画が落選すると、次はほぼ同じ構成で「ギタレロ(スペインのギター弾き)」を描く。マネは友人に「パリの典型を描いたから受け入れられなかったんだ。僕がスペイン人を描けば、きっと彼らも理解してくれるだろう」と語ったということです。
A マネが出たついでにいうと、この画集は個々の画家の伝記を重視していますね。
B それが特徴の一つです。絵画も人間が描くものですから、友情と離反、貧困と栄光、名誉欲と諦観なんてものが絵画にも当然出てくる。不遇だったルノワールにチャンスが巡ってくるのは大金持ちの肖像をたくさん描くようになってからだとか。
A 画家の伝記を前半と後半にわけて二部構成にしてますね。
B 同じ画家でも、モネなんか前半生と後半生では絵の質がかなり違っていますからね。
A 都合八回開催された印象派展をすべて取り上げ、その回に出品された主な作品を集めているのもグループとしての印象派の変遷を見るのに役立ちますね。
B ええ、確たる理念も統一性もなく、売れない画家の結束を図るために開かれた印象派展が第三回で大金持ちのアマチュア画家カイユボットの尽力で成功を収めたにもかかわらず、絵が売れないという現実に直面して、ルノワール、シスレーなどサロンに転じる画家が出てくる。すると、売れなくてもいいんだとするドガが第四回から印象派展を牛耳って一党を集めた「独立派展」に変容させてしまうんです。
A 芸術運動体としての印象派の変容もわかりますね。
B 日本人ゆえに印象派を誤解していた面が訂正されると同時に、印象派の魅力がまた一段と深くなる、そんな画集なんじゃないでしょうか。
ALL REVIEWSをフォローする