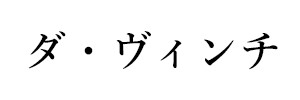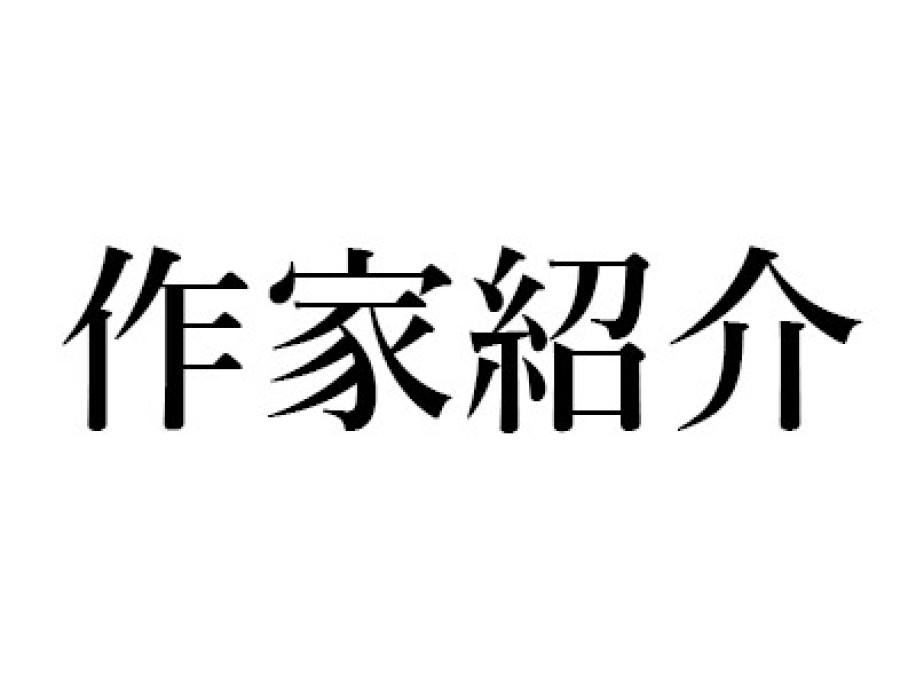書評
『イデアの洞窟』(文藝春秋)
古代ギリシャのアテネで、野犬に食い殺されたとおぼしき若者の死体が発見される。だが、その見立てに不審を抱いた者がいた。それは「人の容貌や事物の外観を、それらがあたかもパピルスででもあるかのように読むことができる」〈謎の解読者〉の異名をとる男、ヘラクレス。若者が通っていた、哲学者プラトンが運営する学園の教師ディアゴラスの依頼を受けて調査に乗り出した彼の前に、しかし、第二、第三の死体が現れて――。
という粗筋だけを聞くと、歴史ミステリーかと思うでしょ? ちっがうんだなー。でもって、これはヘラクレスを探偵役にした書物『イデアの洞窟』の翻訳を依頼された「わたし」による注釈がつけられたメタミステリーで――という説明も不十分。二重三重のトラップがしかけられた実に剣呑(けんのん)な小説なんであります。アテネを舞台にした物語は、自信たっぷりな探偵がその論理性ゆえに事件を”誤読”していくというアンチ・ミステリーの意匠をまとっており、翻訳者による注釈のパートは『イデアの洞窟』にちりばめられた「直感隠喩」的な表現の解釈を”誤読”し続けてノイローゼと化していく男のドタバタを描き、それぞれ独立して読める小説になっており、しかも、最後にはこの二つの物語全体を包括する大きなフレームまで提示されるという、メタの上にもメタを重ねた作品になっているのだ。個人的には「直感隠喩」に翻弄される翻訳者の挙動不審ぶりがかなり可笑しくて◎。「ところで、直感隠喩って何よ」と思ったあなたなら、きっと楽しめる小説です。
【この書評が収録されている書籍】
という粗筋だけを聞くと、歴史ミステリーかと思うでしょ? ちっがうんだなー。でもって、これはヘラクレスを探偵役にした書物『イデアの洞窟』の翻訳を依頼された「わたし」による注釈がつけられたメタミステリーで――という説明も不十分。二重三重のトラップがしかけられた実に剣呑(けんのん)な小説なんであります。アテネを舞台にした物語は、自信たっぷりな探偵がその論理性ゆえに事件を”誤読”していくというアンチ・ミステリーの意匠をまとっており、翻訳者による注釈のパートは『イデアの洞窟』にちりばめられた「直感隠喩」的な表現の解釈を”誤読”し続けてノイローゼと化していく男のドタバタを描き、それぞれ独立して読める小説になっており、しかも、最後にはこの二つの物語全体を包括する大きなフレームまで提示されるという、メタの上にもメタを重ねた作品になっているのだ。個人的には「直感隠喩」に翻弄される翻訳者の挙動不審ぶりがかなり可笑しくて◎。「ところで、直感隠喩って何よ」と思ったあなたなら、きっと楽しめる小説です。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする