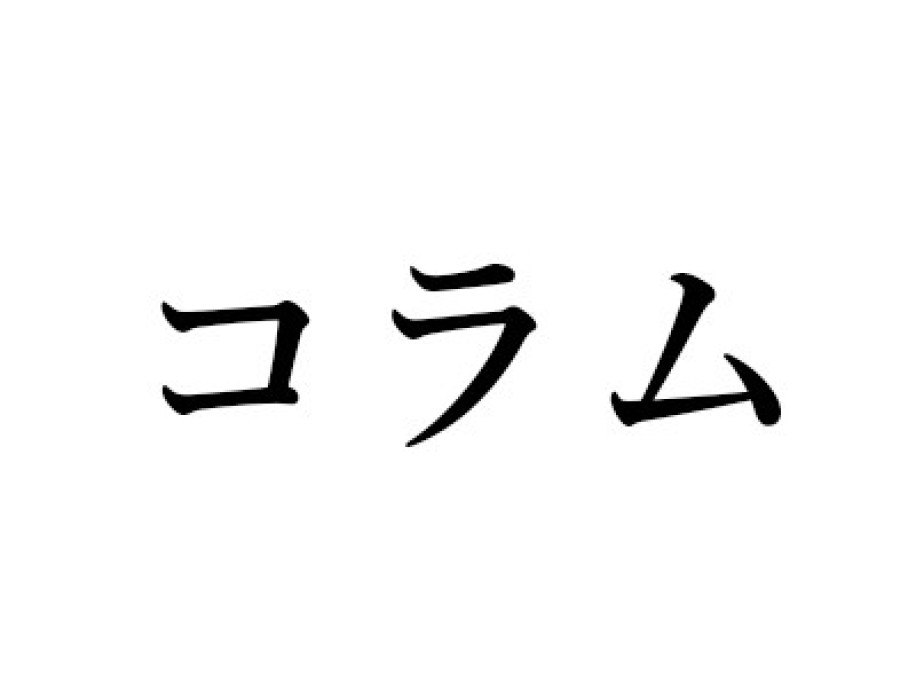書評
『オブジェを持った無産者: 赤瀬川原平の文章』(河出書房新社)
ニセ物か作品か 表現者の言葉が甦る
赤瀬川原平の名著『オブジェを持った無産者』の復刻版だ。現代思潮社という版元から1970年に出ていた。赤瀬川が亡くなったのは去年のこと(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2015年4月)。彼の言葉がこうして甦(よみがえ)ることは、嬉(うれ)しいの一言である。造本について。ソフトカバーの書物を、段ボールが包み、書名と発行所と著者名と頁数と価格が書いてある「札」が貼られ、薄いビニールでくるまれている。書物の質感とか手触りとかが重要視されなくなっている現在、この造本へのこだわりは貴重であろう。
尾辻克彦という名で小説も書いた赤瀬川が世間をアッと言わせたのは、やはり「千円札裁判」。この本には、そのときの意見陳述と最終意見陳述が収録されていてとても興味深い。事件を知らない読者も多いと思うので、少し説明を。
1963年1月、赤瀬川は“千円札”を製作する。翌年、「通貨及証券模造取締法違反」として警視庁の取り調べを受け、65年11月、印刷した二人とともに東京地裁に起訴される。
当時の美術界を代表する芸術家(たとえば瀧口修造や針生一郎)が特別弁護人として名を連ねて、裁判は70年に最高裁判所が突然控訴を棄却するまで、延々と続いた。
私の作ったものはニセ千円札ではなく、本当の千円札でもなく、千円札とニセ千円札という調和を持った紙幣という形態に対応するもの、つまり千円札の「模型」であります
赤瀬川が自説を述べる膨大な量の「意見陳述」がそのまま読めるだけでも、この本の復刊の意味は大きい。「千円札」と「ニセ千円札」と「模型」をめぐって、延々と赤瀬川は語る。「ニセ物は、発見された瞬間、ニセ物ではなくなる。それはいわゆる本物に対する、一つの対立物となるのだ」
彼の表現行為に思いを致す。
ALL REVIEWSをフォローする