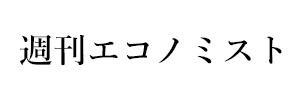書評
『新解さんの謎』(文藝春秋)
つまった困った新明解
やられた、という感じである。三省堂の新明解国語辞典がオモシロイ、といいだしたのは仕事の相棒のヤマサキノリコで、たとえば「しじん・詩人」という項目を、私の持ってた岩波の国語辞典でひくと、「詩をつくる人」とわずか六文字。が、彼女の新明解第四版をひくとどうだろう。「しじん[詩人]、詩を作る上で余人には見られぬひらめきを持っている人。〔広義では、既成のものの見方にとらわれずに直截的に、また鋭角的に物事を把握出来る魂の持主も指す〕」
とこうきちゃう。「魂の持主」というところ、ゾクゾクッとくる。
で、われらが谷根千工房では「つまった困った新明解」を合言葉に、文をつくるためだけでなく、何か物事がうまくいかぬときは新明解をひき、それを拠り所に気持ちを立て直すという「新明解ごっこ」が流行っていた。赤瀬川原平さんはその、われらが隠微な楽しみを白日のもとにさらしてしまった。
赤瀬川原平『新解さんの謎』(文藝春秋)の謎解きは、こんな具合にはじまる。
深夜、知り合いの出版社員SM嬢から「わたしはいま、しんめいかいに来てるんです」と謎の電話が来る。
彼女のまずとり出したのは、れんあい[恋愛]の項。「特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒に居たい、出来るなら合体したいという気持を持ちながら、それが、常にはかなえられないで、ひどく心を苦しめる(まれにかなえられて歓喜する)状態」
一読、「たしかに匂うね」と著者は反応する。
かえん[火炎]には火炎ビンの作り方が書いてありかぞえ方一本と添えてある。これはこわい。新解さんは火炎ビンをつくったことがあるのか。[ごきぶり]の項には「さわると臭い」だって。[ぞっこん]の用例は「私は雪子の美貌と気性に――ひきつけられていたが」と必ず名前が出てきちゃう。雪子って何なんだ。
これは面白くてかわいくてヘンな辞書である。次々用例を恣意的にコラージュして、著者ならではのシュールな「しんかいさん」像をつくり上げてゆく。
狂言回しのSM嬢は鋭い。[ヒステリー]の項には「欲求不満の女性に多い、ヒス」と書いてある。あさぢえ「女の――」、あざとい「――女の恨み」、のに「女だてらに、よせばいい――」といった用例から、「しんかいさん」の根深い女性蔑視をかぎとる。
こうして二人の探偵(もしくはディープスロート=SM嬢とロバート・レッドフォード演ずる記者=赤瀬川さんのウォーターゲートの真相究明)があぶり出した「しんかいさん」像とは――。
女に厳しく、金がない(例・そうそう、いつかの三千円を返してくれないか)。魚が好きで(例・あこうだい=顔はいかついが、うまい)、出版に批判的(例・形のうえでは共著になっているが。売文の徒)。
気まじめで、どこかかわいくて、生活の苦労が沈澱していて、どこか「毛の生えている」ような野太い感じ……。うーん、いるなあ、そういう男。
新明解は攻めの辞書だから、ワキが甘い。冒頭の[れんあい]だって考えてもごらん。好きだっていつも一緒にいたいとか、合体したいって思わないじゃない。これじゃ同性愛が排除されてるじゃない、――っていろいろギモンが湧く。
その豊かさ面白さを、揚げ足取りじゃなく鮮やかに解析した、おすすめの笑える一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする