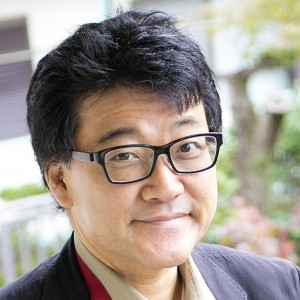書評
『競売ナンバー49の叫び』(筑摩書房)
トマス・ピンチョン(Thomas Pynchon 1937-)
アメリカの作家。コーネル大学在学中に創作を開始。長篇『V.』(1963)によって本格デビューを果たす。同作がその年度の最優秀処女作に与えられるウィリアム・フォークナー賞を受賞。これ以降、ピンチョンは公の場から完全に姿を隠し、写真も撮らせていない。きわめて寡作だが、現代アメリカ文壇の最重要作家と目されている。そのほかの著作に『競売ナンバー49の叫び』(1966)、『重力の虹』(1973)、『ヴァインランド』(1990)などがある。introduction
ピンチョンは『競売ナンバー49の叫び』一冊あればいい、というのがぼくの実感だ。『V.』や『重力の虹』は凄いっちゃ凄いけれど、基本的に物量戦略であって、ぼくのように脳容量には猫に小判だ。なにが書いてあったか途中で忘れてしまうものなあ。スタニスワフ・レムだったら、架空の書評ですますところ。その途方もない構想をピンチョンは本当に書いてしまう。ムチャなおひとだ。これは、あくまでぼくの憶測(むしろ妄想)なのだが、ピンチョンをはじめとする重厚長大メタメタ文学は、ウラジミール・ナボコフ後遺症じゃないのか。ナボコフの鮮やかな文学マジックに痺れて、しかしあの天才のエレガントな手さばきはとうてい模倣できず、不器用な物語増殖へと走ってしまう。それがいけないってわけじゃないけれど。▼ ▼ ▼
サンフランシスコを舞台にした小説をあげるとしたら、まずハメットのハードボイルドあたりがスジだろうが、ぼくの印象に強く焼きついているのは、トマス・ピンチョンの『競売ナンバー49の叫び』である。この都市の喧騒と複雑に張りめぐらされた交通網が、作品の内容とうまく照応して、迷路に迷いこんだ感覚を与えてくれる。
サンフランシスコはバスがよく発達しており、旅人が行動しようとするとき、なによりも頼りになるのが路線図だ。多色で塗りわけられた線が分岐/連絡しながら縦横に走り、ピンチョン好みの比喩で言えば、まるで電気製品の回路板である。あるいは、冷厳な秩序と謎を秘めた神聖文字。
『競売ナンバー49の叫び』のヒロインであるエディパは、サンフランシスコで秘密結社〈ザ・トライステロ〉の手がかりをつかむ。といっても、狙いを定めてこの街にきたわけではない。バークレーでハプニングがあり、あわててクルマを走らせるうちに、ベイ・ブリッジをわたるラッシュに巻きこまれてしまったのだ。倉庫が林立する勾配にクルマを止めて、ざわめく通りをさまよいはじめる。
チャイナタウンの歩道に、チョークで描かれた郵便喇叭(らっぱ)の図柄。ゴールデンゲート公園で、子どもたちが縄跳びをしながら唄う歌詞に織りこまれた暗示。バスの座席に刻まれた、「喇叭を敵にまわすなかれ」という警告。空港で息子を見送りにきた母親がふと口にした、政府が関与しない秘密の通信手段……。バスからバスへと乗りつぎながら、サンフランシスコの夜をめぐるエディパは、謎の組織に関する断片的な情報に次々と出会う。それは、まるで巨大なジグソーパズルを構成する、おびただしい数のピース。だが、たがいがピッタリ噛みあうわけではない。なかには裏返しになったピースや、別なところからまぎれこんできたピースだってあるだろう。
たとえば、エディパが酒場で出会った青年は、自分の襟につけた喇叭のバッジについて、これは「恋愛中毒者匿名会」の印だと説明する。この会の発足は、妻に裏切られて焼身自殺を企てた中年男が、ガソリンに浸った切手に郵便喇叭のマークを発見したことが契機だという。喇叭の透かしを見た男は、これはなにかの符合だと確信し、自殺に失敗した人の地下組織を結成したのだ。
喇叭の印が流通する過程で、〈ザ・トライステロ〉本体には直接つながらない、新しいなにかが生まれてしまう。縄跳び遊びの唄もそうだし、「恋愛中毒者匿名会」もそうだ。情報の伝播にともなって発生するノイズや混線。エディパはそのなかから、歪みのない情報を取りだそうと躍起になる。
彼女の探偵ぶりは、サム・スペードばりとはとても言えないが、それも仕方がない。なにせ、ついこの前まで昼はホーム・パーティに出かけ、夕方には夫の帰りを待ちながら庭のハーブを摘むような日々をすごしてきたのだ。そんな彼女が、なぜ秘密結社などに興味を持つようになったのか。
そのいきさつは、少々こみいっている。不動産業界の大立者、ピアス・インヴェラリティの遺言執行人に指名されたのが、そもそものはじまり。ピアスはエディパのかつての恋人なのだが、その関係はとうの昔に清算されたはずだった。もっともピアスはそう思っていなかったのかもしれない。その莫大な遺産を一覧にする仕事は、エディパを日々の生活から引きはなしてしまう。
彼女はピアスの弁護士のメッガーと落ちあい、一軒のバーに入るが、そこのトイレで奇妙な落書きを見つける。「洗練されたお遊びはいかが? あなたも、ご主人も、ガールフレンドも。人数が多ければ、それだけ楽しくなります。カービーにご連絡を。ただしWASTEを通じて」。その下には、輪と三角形と梯形を組み合わせた図形が描かれている。郵便喇叭の印だ。エディパの気にかかったのは「洗練されたお遊び」ではなく、「WASTE」なる通信方法(?)だ。そういえば、さっき革の郵便袋をさげた青年が、バーの客に封筒を配っていた。
〈ザ・トライステロ〉にいたる、もうひとつの糸口は、『急使の悲劇』という演劇である。神聖ローマ帝国の時代のお家騒動を扱ったもので、正当な嫡子が特別急使(郵便配達人)に身をやつして復讐の機会を狙っているという設定だ。お家騒動と絡んで、歴史の背後で権謀術策を巡らせている存在があるらしいのだが、劇の表面には出てこない。ただ一度だけ、台詞のなかに「トライステロ」の名があらわれる。
エディパが「WASTE」と「トライステロ」を結びつけたのは、ピアスの切手コレクションのなかに、喇叭の透かしが入った米国記念切手があるのを知ったときだ。コレクションの整理を担当している専門家は、エディパにその切手を見せたあと、今度はドイツの古い切手を取りだす。四隅には郵便喇叭の図案。これを発行したのは、『急使の悲劇』で嫡子が身を寄せていた郵便組織なのだ。
さらに多くの情報を総合し、エディパはある仮説にたどり着く。〈ザ・トライステロ〉は、ヨーロッパ社会の裏側で暗躍した郵便機構であり、その後アメリカにわたって、世の中の発展とともに秘密のネットワークを張りめぐらせていった。この組織の存在が明るみに出れば、歴史が覆ってしまうかもしれないい。
その一方、エディパのなかでひとつの疑念が育ちはじめる。〈ザ・トライステロ〉の実在を裏づける情報は、すべてピアスが仕組んだ悪戯ではないのか。そうすると、彼女が偶然出会ったはずの、歩道の落書きや、公園の子どもたち、空港で息子を見送る母親まで、あらかじめ用意されていたことになる。はたして、そんなことが可能だろうか。サンフランシスコの迷宮を抜けても、エディパの心は出口を見つけられずにいる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする