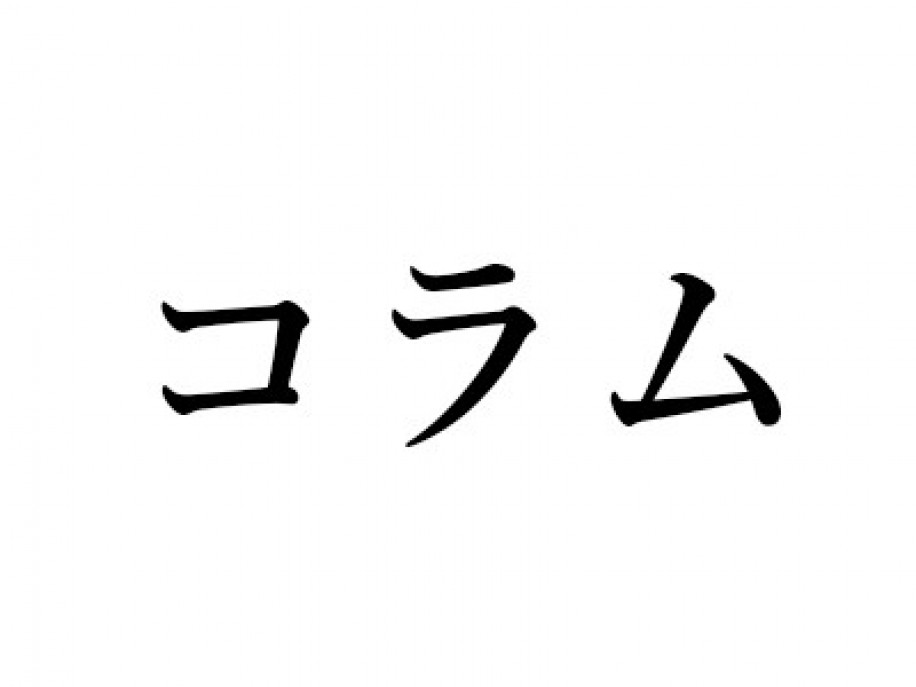解説
『吾輩は猫である』(新潮社)
「寄席がはねたあとの様に座敷は淋しくなった」
英文学を外国人が研究して何になるか。それを学校で教えて、ますます何になるか、そのうえなぜか四六時中「探偵」に見張られている。憂鬱症と癇癪(かんしゃく)の間を往還して、帰国以来怏々(おうおう)としてたのしまなかった漱石は、1905(明治38)年、高浜虚子に勧められて『吾輩は猫である』を書いた。漱石の内部にわだかまっていたユーモアと批評精神は、ここに活路を見出し、心はひさびさ開かれた。
が、日露戦争後の世の中では、みなが存分に自我を張る。個人は露出してこすれ合い、社会の雨風に打たれもする。
「呑気と見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする」
20世紀をえがいた漱石は、無意識のうちにすでに現代文学の作家であった。
内容解説
中学教師・苦沙弥先生の書斎に集まる明治の俗物紳士たちの語る珍談・奇譚、出来(しゅったい)する小事件の数かずを、先生の家に迷いこんで飼われている猫の眼から風刺的に描く、漱石最初の長編小説。江戸落語の笑いの文体と、英国の男性社交界風の皮肉な雰囲気と、漱石の英文学の教養とが渾然(こんぜん)一体となり、作者の饒舌の才能が遺憾なく発揮される。痛烈かつ愉快な文明批評にとむ古典的快作。【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする