書評
『夢十夜 他二篇』(岩波書店)
「ちょうどこんな晩だったな――という、あの言葉はこわかった」と作家の夢枕獏さんが言った。
先日、マンガ好きの人たちのおしゃべりの会に私も同席させてもらったときのことだ。あれは杉浦日向子著『百物語』(新潮コミック)の話からそちらのほうへ流れていったのだろうか、漱石の『夢十夜』の話になった。
夢枕さんは『夢十夜』がとても好きで、中でも自分の子どもを背負って森を歩いて行く男の話(第三夜)が忘れられないという。
それはこんな話だ――。背中の子どもは確かに六つになる自分の子どもには違いないのだが、言葉つきはまるで大人だし、いつのまにか眼がつぶれて青坊主になっている。その背中の子どもがフトつぶやく。「ちょうどこんな晩だったな」。
男は何のことやらはっきりとはわからぬまま、おそろしくなって足を早める。子どもは「ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ」「文化五年辰年だろう」と不思議なことを言う。そして、最後にこう言うのだ。
「おまえがおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」――と。
この話を夢枕さんはセリフもしっかりとおぼえていて、再現してみせた。私は高校だか大学時代に『夢十夜』を読んだはずだが、「えっ、そんな面白い話あったっけ?」と驚いた。すっかり忘れている。『吾輩は猫である』のアンドレア・デル・サルトやトチメンボーは頭の奥深くに刻み込まれて中学以来かたときも(というのは大げさだが)忘れたことはなかったのに。どうも私は、漱石文学の中の滑稽・皮肉・辛辣といった味にばかり惹かれていて、その幻想性のほうには興味がなかったようである。
家に帰って、さっそく『夢十夜』を読み直してみた。
十の夢の話である。夢枕さんが話していた第三夜と第七夜の話が、抜群に面白い。
第三夜の話は、あらすじを聞いただけでもこわかったが、読んでみるとさらにじんわりと、深く、こわい。
背中の子どもに「ちょうどこんな晩だったな」と言われ、「何が」と聞くと、「何がって、知ってるじゃないか」と嘲られる。
何かぼんやりと不吉な、悪い、まがまがしい心当たりがある――という、その感じがこわい。その漠たる「心当たり」がラストシーンでは百年前の人殺しの記憶となって、忽然とよみがえるのである。何だか、自分の背骨がスーッと引き抜かれてしまったかのような、立っている地面がサーッと沈下してしまったかのような――そういう種類(かたい言葉で言うなら自我の崩壊?)のショックだ。
第七夜のほうは、こんな話である。
「自分」は大きな船に乗って行く。どこへ向かっているのかも、いつ陸へ上がれるのかもわからない。「自分」は「こんな船にいるより一層(いっそ)身を投げて死んでしまおうか」と思う。
そして「自分」はある晩ほんとうに死ぬ気になって、思い切って海の中へ飛び込んだ。
そのあとの最後の数行が面白い。
この、取り返しのつかない感じ、あと戻りのできない感じ、しかも何か大きなものから置きざりにされて、「無」の中にのみこまれて行く感じがこわい。
岩波文庫版の巻末解説で阿部昭氏がみごとに指摘している通り、漱石は「追われる人間」だった。旧時代の重荷を背負いながら、先頭に立って西洋の新文化の吸収に追われる人間であった。振り捨てようのない、この国の過去。自分の血の中に流れる、この国の暗く生ぐさい記憶。罪の意識。十の夢の中には、つねにそういう「追われる人間」の不安が色濃く投影されている。
私は大学時代にシュールレアリズムの「夢の自動筆記」というのを知って、何回か自分の見た夢をメモしたことがあった。メモしておいたおかげで今でも思い出せる。
①やかんでお湯をわかしていると、一本の髪の毛が浮かんでいるので、厭だなあと思い、箸で取るのだが、取っても取っても一本の髪の毛が浮いたまま――という夢。
②庭を眺めていると、一羽の白い鳥がもがいている。よく見ると鳥の足もとというか胴体部分は四角い箱のようになっている。その箱はアコーディオンのようにヒダになっていて、鳥が羽ばたくたびに、むなしく伸び縮みしている――という夢。
その二つの夢が、いくぶんか文学的おもむきのある二大ヒット作だった。
夢の中で忘れがたい情景というのもある。どこか知らない田舎の道。曇天で、向こうにさして高くはない山があり、左手前方にカヤぶき屋根の家があり、右手に草むらがある。
温泉旅行に行ってそんな田舎道に出くわすと、なんだかクラクラッと目まいしそうな気分になる。カヤぶき屋根の家なぞはないが、道の曲がりぐあいとか空や山の見え方に、何か妙な“心当たり”=既視感(デジャヴ)があるようで。自分の半生を振り返ってもそういう田舎で暮らしたことはないので、もしかして血の中に何百年も昔の記憶がインプットされているのだろうか、などと非科学的なことを思う。わざとそう考えてみたい感じもする。
自分のことを陰気な性格とは思わないのだが、夢の中ではいつもどこかヒンヤリと淋しい気分なのが不思議だ。漱石の『夢十夜』にも、やっぱりヒンヤリと淋しい空気が漂っている。
【この書評が収録されている書籍】
先日、マンガ好きの人たちのおしゃべりの会に私も同席させてもらったときのことだ。あれは杉浦日向子著『百物語』(新潮コミック)の話からそちらのほうへ流れていったのだろうか、漱石の『夢十夜』の話になった。
夢枕さんは『夢十夜』がとても好きで、中でも自分の子どもを背負って森を歩いて行く男の話(第三夜)が忘れられないという。
それはこんな話だ――。背中の子どもは確かに六つになる自分の子どもには違いないのだが、言葉つきはまるで大人だし、いつのまにか眼がつぶれて青坊主になっている。その背中の子どもがフトつぶやく。「ちょうどこんな晩だったな」。
男は何のことやらはっきりとはわからぬまま、おそろしくなって足を早める。子どもは「ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ」「文化五年辰年だろう」と不思議なことを言う。そして、最後にこう言うのだ。
「おまえがおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」――と。
この話を夢枕さんはセリフもしっかりとおぼえていて、再現してみせた。私は高校だか大学時代に『夢十夜』を読んだはずだが、「えっ、そんな面白い話あったっけ?」と驚いた。すっかり忘れている。『吾輩は猫である』のアンドレア・デル・サルトやトチメンボーは頭の奥深くに刻み込まれて中学以来かたときも(というのは大げさだが)忘れたことはなかったのに。どうも私は、漱石文学の中の滑稽・皮肉・辛辣といった味にばかり惹かれていて、その幻想性のほうには興味がなかったようである。
家に帰って、さっそく『夢十夜』を読み直してみた。
十の夢の話である。夢枕さんが話していた第三夜と第七夜の話が、抜群に面白い。
第三夜の話は、あらすじを聞いただけでもこわかったが、読んでみるとさらにじんわりと、深く、こわい。
背中の子どもに「ちょうどこんな晩だったな」と言われ、「何が」と聞くと、「何がって、知ってるじゃないか」と嘲られる。
すると何(なん)だか知ってるような気がし出した。けれども判然(はっきり)とは分らない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けば分るように思える。分っては大変だから、分らないうちに早く捨ててしまって、安心しなくってはならないように思える。
何かぼんやりと不吉な、悪い、まがまがしい心当たりがある――という、その感じがこわい。その漠たる「心当たり」がラストシーンでは百年前の人殺しの記憶となって、忽然とよみがえるのである。何だか、自分の背骨がスーッと引き抜かれてしまったかのような、立っている地面がサーッと沈下してしまったかのような――そういう種類(かたい言葉で言うなら自我の崩壊?)のショックだ。
第七夜のほうは、こんな話である。
「自分」は大きな船に乗って行く。どこへ向かっているのかも、いつ陸へ上がれるのかもわからない。「自分」は「こんな船にいるより一層(いっそ)身を投げて死んでしまおうか」と思う。
そして「自分」はある晩ほんとうに死ぬ気になって、思い切って海の中へ飛び込んだ。
そのあとの最後の数行が面白い。
ところが――自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は厭でも応でも海の中へ這入らなければならない。ただ大変高く出来ていた船と見えて、身体は船を離れたけれども、足は容易に水に着かない。しかし捕まえるものがないから、次第々々に水に近附いて来る。いくら足を縮めても近附いて来る。水の色は黒かった。
そのうち船は例の通り黒い煙を吐いて、通り過ぎてしまった。自分は何処へ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと始めて悟りながら、しかもその悟りを利用する事が出来ずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った。
この、取り返しのつかない感じ、あと戻りのできない感じ、しかも何か大きなものから置きざりにされて、「無」の中にのみこまれて行く感じがこわい。
岩波文庫版の巻末解説で阿部昭氏がみごとに指摘している通り、漱石は「追われる人間」だった。旧時代の重荷を背負いながら、先頭に立って西洋の新文化の吸収に追われる人間であった。振り捨てようのない、この国の過去。自分の血の中に流れる、この国の暗く生ぐさい記憶。罪の意識。十の夢の中には、つねにそういう「追われる人間」の不安が色濃く投影されている。
私は大学時代にシュールレアリズムの「夢の自動筆記」というのを知って、何回か自分の見た夢をメモしたことがあった。メモしておいたおかげで今でも思い出せる。
①やかんでお湯をわかしていると、一本の髪の毛が浮かんでいるので、厭だなあと思い、箸で取るのだが、取っても取っても一本の髪の毛が浮いたまま――という夢。
②庭を眺めていると、一羽の白い鳥がもがいている。よく見ると鳥の足もとというか胴体部分は四角い箱のようになっている。その箱はアコーディオンのようにヒダになっていて、鳥が羽ばたくたびに、むなしく伸び縮みしている――という夢。
その二つの夢が、いくぶんか文学的おもむきのある二大ヒット作だった。
夢の中で忘れがたい情景というのもある。どこか知らない田舎の道。曇天で、向こうにさして高くはない山があり、左手前方にカヤぶき屋根の家があり、右手に草むらがある。
温泉旅行に行ってそんな田舎道に出くわすと、なんだかクラクラッと目まいしそうな気分になる。カヤぶき屋根の家なぞはないが、道の曲がりぐあいとか空や山の見え方に、何か妙な“心当たり”=既視感(デジャヴ)があるようで。自分の半生を振り返ってもそういう田舎で暮らしたことはないので、もしかして血の中に何百年も昔の記憶がインプットされているのだろうか、などと非科学的なことを思う。わざとそう考えてみたい感じもする。
自分のことを陰気な性格とは思わないのだが、夢の中ではいつもどこかヒンヤリと淋しい気分なのが不思議だ。漱石の『夢十夜』にも、やっぱりヒンヤリと淋しい空気が漂っている。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
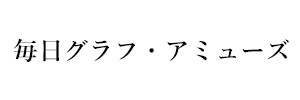
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする






































