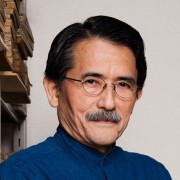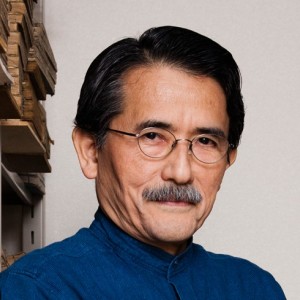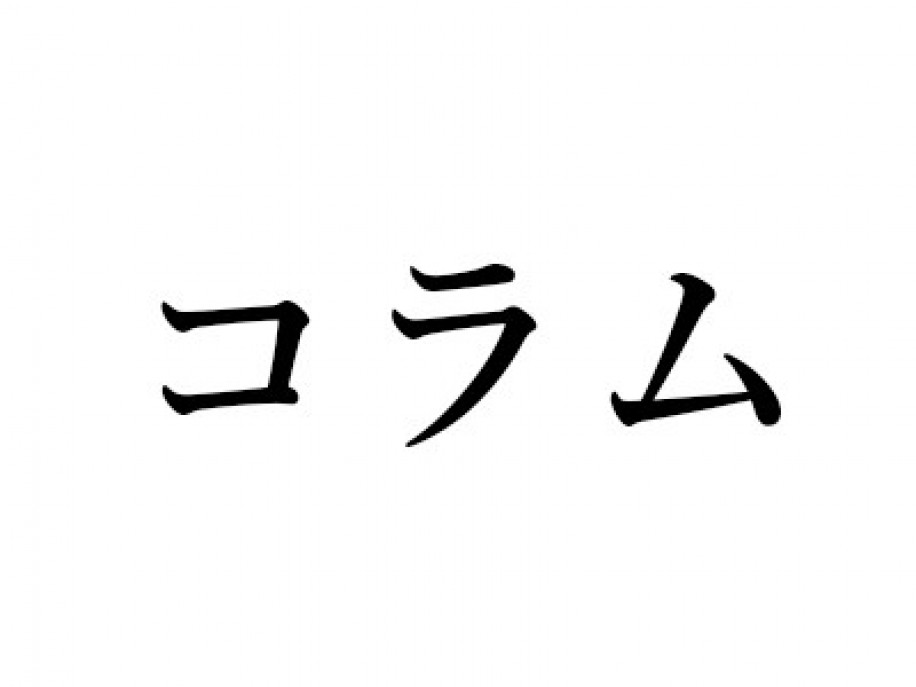書評
『吾輩は猫である 上』(集英社)
朗読と漱石
この四月から、私は、東京エフエムの衛星ラジオで『リンボウ先生の歌の翼に』という番組をやっている(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2006年)。私自身が選んだ音源でクラシック歌曲をかけ、なおかつ近代文学作品を朗読する、という番組である。こういう番組を半年やってきて、つくづく思うことは、文章には二つの種類があるということである。一つは目で読む文章。
もう一つは耳で聞く文章。
そしてこの二つの間には相当に隔たりがあるのである。
もともと日本語というのは、かなと漢字を混用し、しかもそれぞれが「意味」とはまた違ったグラフィック上の価値を持っているやっかいな言語である。
たとえば、事実上同じことを言うのであっても「良い」と書くのと「善い」と書くのでは、すでに見た目でニュアンスの違いが表れる。
あるいは、
久しぶりに夢に見しきみは語気荒く
我を責めたりはっと目覚めつ
と、短歌を普通の上の句下の句で二行書きにするのと、
ひさしぶりにゆめにみしきみは
語気あらくわれをせめたり。
はつとめざめつ。
と、三行に仮名書きして「語気」だけを漢字に書き、適宜句読点などを付加するというふうな書き方をするのとでは、読んだ時の印象はずいぶんと違う。こういう文字の配置のグラフィックな情報や用字の如何が相当に物をいうのが日本語という言語なのである。
しかるに、たとえば平安朝の物語や中世の軍記物語、勅撰集の和歌などは、ほぼ完全に「耳で聞いて享受する」文学であった。日本文学のもっとも豊潤な部分は、つまり音読による伝達を前提としていたのである。
私はその番組のなかで、森鷗外の『舞姫』と、夏目漱石の『吾輩は猫である』を朗読してみた。
すると、『舞姫』は耳で聞いただけではいったい何を言っているのかさっぱり分からない文章であって、つまりは目で字を見なくては享受できないことがほぼ自明に了解された。
次に漱石の『猫』を朗読してみると、同じ時代の文豪でありながら、こちらは耳で聞いただけで十分分かり、なおかつ、朗読のときにせりふの声色などを工夫して読むので、目で読むよりずっと面白いということも分かった。言ってみれば、鷗外のは漢文脈からいくらも離れていないのに対して、漱石の文章はほんとうの近代散文でありながら同時に日本文学の音読の伝統にも繋がっている。ああ、漱石は物語や戯作の流れに棹さしながら、同時に、ほんとうの「文章の現代」を開いたのだなあ、と私はつくづく思った。この分では、ちょっと黙読してつまらないと思っていた『草枕』なども、朗読してみたら、もしかして全然違った相貌が見えてくるかもしれない、と大発見をしたような気がした。
初出メディア
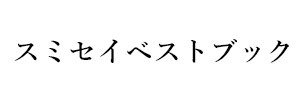
スミセイベストブック 2006年3月号
ALL REVIEWSをフォローする